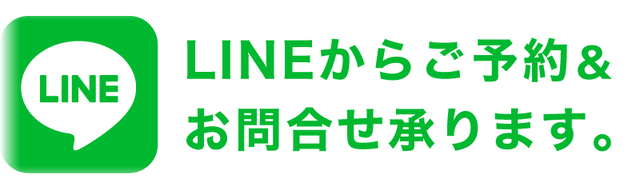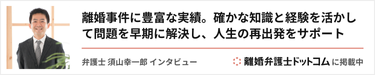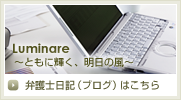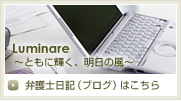兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
神戸の弁護士が離婚・別居に伴う健康保険について解説します!
離婚や離婚を前提とする別居を始める際、健康保険がどうなるのかよく分からないという方は非常に多いようです。
そこで、離婚や別居を始めるにあたって、最低限知っておきたい健康保険の基礎知識について以下に解説します。
1 公的医療保険制度
我が国では、すべての国民が公的医療保険に加入することになっています。
公的医療保険には様々なものがありますが、会社員や公務員が加入する「健康保険」、自営業者のための「国民健康保険」のいずれかに加入していることが多いと思われます。
なお、健康保険や国民健康保険に加入していても、75歳になると「後期高齢者医療保険」に切り替わります。
健康保険には、傷病手当金や出産手当金があり、扶養対象者は保険料負担がありません。
一方、国民健康保険は傷病手当金や出産手当金がなく、また扶養の概念がありません。収入がなくても一定の保険料を支払わなければなりません。
2 健康保険
会社員等が加入する健康保険は、事業主に使用されている者を被保険者とし、配偶者や子は被扶養者となります。
被扶養者に関する届出や手続は、被保険者が事業主を通じて行います。
健康保険の保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
病院で支払う医療費(一部負担金)の割合は、本人・家族とも3割(3歳以上)です。3歳未満は2割です。
3 国民健康保険
国民健康保険(「国保」と略されることが多い)は、他の公的医療保険に加入していない人が加入する保険で、自営業者(個人事業主)が主に加入しています。
国民健康保険には、健康保険のような「扶養」の概念がありませんので、被保険者は各自になります。
つまり、自営業者(父)、配偶者(母)、子で構成されている家庭の場合、それぞれが被保険者となります。
一方、国民健康保険には、「世帯」という概念があり、世帯主が、世帯全員の届出や手続を行い、保険証の交付を求めることができ、世帯全員の保険料の納付義務者となります。
国民健康保険料の保険料は、原則として各被保険者が全額負担します。
上のケースで、父が世帯主の場合、父は、自身の保険料のほか、配偶者である母、子の保険料についても納付義務があるということになります。
病院で支払う医療費(一部負担金)の割合は、本人・家族とも3割(3歳以上)です。3歳未満は2割です。つまり一部負担金は、健康保険と国民健康保険で違いは無いということです。
4 妻が別居する場合の健康保険
離婚と公的医療保険については、離婚が成立した後に変更手続を取る方が多いようです。しかし、離婚を前提に別居し、新たに就職したり、住民票上の住所を変更する方もいらっしゃいます。
このような場合、どのような手続きを行う必要があるのでしょうか。
国民健康保険に加入していた場合
同居時に夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、別居後、妻が自分が勤める会社で健康保険の要件を満たす場合、妻は自分の会社の健康保険に加入し、夫は世帯主として、国民健康保険の被保険者から妻を抹消する手続を行います。
実家に帰り、会社等に勤務する家族の健康保険に被扶養者として加入するという選択もあります。
妻が自分を世帯主として新たな住居に住民票を移し、国民健康保険に加入する場合、妻は自分を世帯主として国民健康保険の資格取得の届出を行います。
夫の健康保険の扶養に入っていた場合
同居時に夫の健康保険の扶養に入っていた場合で、妻が自分が勤める会社で健康保険の要件を満たす場合、妻は健康保険に加入し、夫は自分の健康保険の被扶養者から妻を資格抹消する手続(被扶養者異動届)を行います。
実家に帰り、会社等に勤務する家族の健康保険に被扶養者として加入するという選択もあります。
妻が自分を世帯主として新たな住居に住民票を移し、国民健康保険に加入する場合、妻自身を世帯主として国民健康保険の資格取得の届出を行います。夫は自分の健康保険の被扶養者から妻を資格抹消する手続(被扶養者異動届)を行います。
妻が国民健康保険に加入する場合は、通常、妻が夫の健康保険の被扶養者の資格を喪失したことを証明する資格喪失証明書の提出を求められますので、夫に保険証を返却し、会社で発行の手続きをしてもらい、交付を依頼しましょう。
夫が資格喪失証明書の交付に協力してくれない場合は、市町村役場に相談してみましょう。
いつ手続きを行うか
実務的には、離婚前提で別居しても、離婚が成立するまでは健康保険は同居時のまま離婚協議を進める方が多いようです。
離婚が成立し、関係が確定的に決まってから行う方が何かと都合が良いからです。
国民健康保険は、住民票の世帯単位での加入ですので、別居し、住民票を移した場合、別々に国保に加入する必要があります(就学のために住民票を移動した場合などの例外あり)。
世帯主である夫に世帯全員の保険料の納付義務があったのに、住民票を移したことにより、妻に保険料の納付義務(子連れ別居の場合、子の保険料も)が生じるという事態について、よく検討しておく必要があります。
5 夫婦が別居する場合の子どもの健康保険
離婚を前提に、妻が子を連れて別居した場合、妻の保険については上のとおりです。
子についてはどうなるのでしょうか。
妻の健康保険に入れたい場合
同居時に国民健康保険に加入していた場合で、別居後、妻が就職した会社で健康保険の要件を満たす場合、妻は会社の健康保険に加入し、子を扶養に入れます。夫は世帯主として、国民健康保険の被保険者から妻を抹消する手続を行います。
夫の健康保険の扶養に入っていた場合
同居時に夫の健康保険の扶養に入っていた場合で、妻が就職した会社で健康保険の要件を満たす場合、妻は健康保険に加入します。夫は自分の健康保険の被扶養者から妻を資格抹消する手続(被扶養者異動届)を行います。
この場合、子は共働きである夫と妻のどちらの被扶養者となるのでしょうか。
これについては、2021年(令和3年)8月1日から以下のルールが適用されています。
夫婦の年間収入の差額の割合が、
① 1割超の場合、年間収入が多い親の被扶養者とする。
② 1割以内の場合、主として生計を維持する親の被扶養者とする。
基本的には収入が多い方の扶養に入れると考えておけばよいでしょう。
子の扶養について、夫の健康保険から妻の健康保険に移動する場合、夫の健康保険の資格喪失証明書の提出を求められる場合があります。
具体的な手続は、ご自身の健康保険組合に相談するようにしましょう。
妻が国民健康保険の場合
妻と子が同一世帯であれば、妻を世帯主とする国民健康保険に子を加入させることができます。
子が夫の健康保険の被扶養者であった場合は、夫の健康保険組合の資格喪失証明書が必要となる場合があります。
夫が協力してくれない場合、夫の組合に直接相談してみてもよいでしょう。
6 離婚後の健康保険
実務的に最も多いのは、離婚が成立するまでは保険は同居時のままにしておき、離婚が成立した直後に保険の手続を行うというものです。
国民健康保険に加入していた場合
同居時に夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後、妻が自分が勤める会社で健康保険の要件を満たす場合、妻は自分の会社の健康保険に加入し、夫は世帯主として、国民健康保険の被保険者から妻を抹消する手続を行います。
実家に帰り、会社等に勤務する家族の健康保険に被扶養者として加入するという選択もあります。
妻が自分を世帯主として新たな住居に住民票を移し、国民健康保険に加入する場合、妻は自分を世帯主として国民健康保険の資格取得の届出を行います。
夫の健康保険の扶養に入っていた場合
同居時に夫の健康保険の扶養に入っていた場合で、離婚により被扶養者の資格を失います。
妻が自分が勤める会社で健康保険の要件を満たす場合、妻は健康保険に加入し、夫は自分の健康保険の被扶養者から妻を資格抹消する手続(被扶養者異動届)を行います。
実家に帰り、会社等に勤務する家族の健康保険に被扶養者として加入するという選択もあります。
妻が自分を世帯主として新たな住居に住民票を移し、国民健康保険に加入する場合、妻自身を世帯主として国民健康保険の資格取得の届出を行います。夫は自分の健康保険の被扶養者から妻を資格抹消する手続(被扶養者異動届)を行います。
妻が国民健康保険に加入する場合は、通常、妻が夫の健康保険の被扶養者の資格を喪失したことを証明する資格喪失証明書の提出を求められますので、夫に保険証を返却し、会社で発行の手続きをしてもらい、交付を依頼しましょう。
夫が資格喪失証明書の交付に協力してくれない場合は、市町村役場に相談してみましょう。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚サービス案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 家族信託
- 成年後見制度
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日