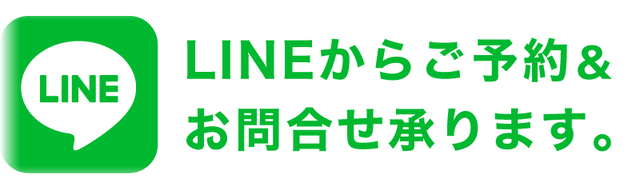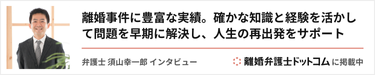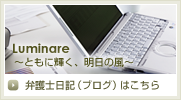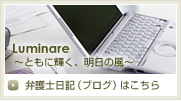弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
相続関連の法改正情報
相続登記がされないことによる所有者不明土地の問題が、最近クローズアップされています。
所有者不明土地とは、
1 登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
2 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地をいいます。
所有者不明土地問題研究会によると、2016年時点の所有者不明土地面積は、約410万haもあり、九州本島(約367万ha)の面積を上回るとのことです。
所有者不明土地は、
1 所有者の探索に膨大な時間と費用がかかる
2 土地が管理されずに放置されていることが多い
3 土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難になる
4 公共事業・復興事業が円滑に進まない
5 民間取引が阻害される
6 隣接土地への悪影響、などの問題点が指摘されています。
今後、高齢化の進展により、ますます所有者不明土地の増大が懸念されることから、政府は重要な課題として法改正を行い、対策を講じることとなりました。
2021年(令和3年)4月、改正民法、改正不動産登記法、相続土地国庫帰属法が成立し、2021年(令和3年)12月に、具体的な施行日が決定されました。
改正民法は、2023年(令和5年)4月1日の施行、相続土地国庫帰属法は2023年(令和5年)4月27日に施行されます。
改正不動産登記法は2024年(令和6年)4月1日に施行され、相続登記が義務付けられます。
今回の法改正や新法で重要なのは、施行日前に発生した相続も対象になる点です。義務を課したり、制裁を科したりする法改正等は、通常遡及適用しないのですが、今回は対象になります。もっとも猶予期間が設けられているものもありますので、期日についてよく確認しておくことが重要です。
参考:法務省民事局 「所有者不明土地関連法の施行期日について」
相続税の申告には期限がありますが、相続登記は現行表情、いつまでに登記しなければならないといった期限の定めは無く、放置していても罰則がありません。
このため、相続登記をしなかったり、後回しにされてしまうことが多く、そうしている間に新たな相続が発生するなどして関係者が増え、その結果、誰が所有者で誰が管理しているのか不明になってしまうという事態が生じます。
今回の改正は、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日と改正法施行日(令和6年4月1日)のいずれか遅い方の日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付け、正当な理由の無い申請漏れには過料(10万円以下)の制裁が設けられました。
3年の期限内に間に合わない場合、相続人申告登記制度が新設されました。
登記名義人の相続人である旨と住所、氏名などを申し出れば、登記官がその者の氏名・住所等を職権で登記します(持分は登記されない報告的登記になります)。
この制度を利用すれば、相続開始から3年が過ぎても過料の対象となりません。単独で申請が可能であり、登録免許税も非課税です。
相続登記と同様、住所変更登記も義務ではありませんでした。このため、自然人、法人を問わず、住所移転のたびに費用をかけて登記手続を行うのを負担に感じ、放置されがちでした(実際には、売却時等に現住所に名義移転するケースが多かった)。
今回の改正で、所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられました。
相続登記の場合と同様、正当な理由の無い申請漏れには過料の制裁が設けられました。
また、他の公的機関等から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記をする新たな方策も導入されます。
自然人の場合、登記申請の際に氏名・住所のほか生年月日等の「検索用情報」の申出を行うと、登記官が検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに照会し、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得します。登記官は取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更登記を行うことについて確認をとった上で、変更登記をします(非課税)。
土地を相続したものの、遠方にあったり、利用予定が無いなどの理由で手放したいが、買い手が付かないなどの理由で放置されるケースが増加しています。
このたび、相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度が創設されました。
相続土地の国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地所有権を取得した者(共有地の場合は共有者全員)が申請し、一定の要件を満たす場合に、審査手数料及び10年分の管理費相当額の負担金を納付し、当該相続土地を国庫に帰属させることを可能とする制度です。
要件としては、以下に該当しないことが求められます。
- 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 崖がある土地
- 権利関係に争いがある土地
- 担保権等が設定されている土地
- 通路など他人に使用される土地 など
10年分の管理費は、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)が市街地(200㎡)で約80万円、原野で約20万円程度のようですので、同程度の納付が必要になることが見込まれます。
要件を満たさないことが見込まれる土地の相続が問題となっている場合、当該土地を相続することのメリット・デメリットをよく検討する必要があります。
相続が開始しても、相続登記を行わず、遺産分割協議すら行わないで放置しているケースが増えています。
長期間放置された後、あらためて遺産分割協議を行おうとすると、相続が繰り返されて相続人が増加していたり、そもそも相続財産の内容が分からなくなっていたり、証拠が散逸していたりして、一層遺産分割が難しくなります。
今回の改正で、遺産分割長期未了の状態を解消するための方策として、遺産分割協議に期間が設定されました。
相続開始から10年が経過すると、原則として法定相続割合で分割されることになります。
施行日は2023年(令和4年)4月1日ですが、施行日より前に発生した相続については5年間の猶予がおかれました。
施行日時点で既に10年が経過していたり、施行日前に相続が開始しているが10年の経過が2028年4月1日より前の場合、2028年(令和9年)3月末が期限となります。
分割協議では、特別受益や寄与分を考慮することも可能ですが、改正後は、期間を過ぎると原則として考慮されなくなることが見込まれますので、特別受益等を主張したいなら、早めに遺産分割協議を始め、完了することが必要になります。
民法の相続法制については、昭和55年に配偶者相続分の引き上げ、寄与分制度の新設等がなされて以降、大幅な改正がなされていませんでししたが、法制審議会で約3年に及ぶ審議を経て、平成30年7月、改正法が成立しました。
今回の改正の主なものとしては、次の5つです。
- 「配偶者の居住権を保護するための方策」として、配偶者短期居住権、配偶者居住権が新設されました。
- 「遺産分割等に関する見直し」として、配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示推定規定)が新設されたほか、相続人全員の同意がない場合であっても、特定の相続人による一定額の払い戻しを金融機関に求めることができる仮払い制度を新設されました。
- 「遺言制度に関する見直し」として、自筆証書遺言の方式が緩和されました。財産目録等はパソコンで作成することが可能となります。
併せて、法務局における自筆証書遺言の保管制度も新設されました(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」)。 - 「遺留分制度に関する見直し」として、従来のような遺留分減殺請求権の行使による物権的な効果を否定し、金銭債権化されることになりました。
- 「相続の効力等に関する見直し」として、現行法の規律を見直し、法定相続分を超える承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することが出来ないとされました。
- 「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」として、これまで寄与分の対象とならなかった相続人以外の親族などについて、一定の要件のもとで、相続人に対し、一定の金銭の支払を請求する仕組みを新設しました。
改正法の施行期日が、改正項目によって段階的になっていますので注意が必要です。
- 改正法の原則的な施行期日は、2019年7月1日。
- 自筆証書遺言の方式緩和は、少し早く、2019年1月13日。
- 配偶者の居住権を保護するための方策については、2020年4月1日。
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)については、2020年7月10日。
改正内容だけでなく、いつから施行されるのかについても目配りをしておく必要があります。
改正の各論については、改めて少しずつ以下に追記していきます。
配偶者は、相続開始時に、被相続人の建物に無償で居住していた場合、以下の期間について、居住建物を無償使用する権利(配偶者短期居住権)が認められることになりました。
①配偶者が居住建物を含む遺産分割に関与する場合には、居住建物の帰属が確定する日までの間(但し、最低6か月間は保障)
②居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には、新たに居住建物の所有者となった者から消滅請求を受けてから6か月間
現行では、最判平成8年12月17日の判例法理に従い、配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と配偶者との間で使用貸借契約が成立していたと推認し、配偶者の居住権を保護してきました。
しかし、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や、被相続人が反対の意思を表示していたような場合、使用貸借は推認されず、配偶者の居住権が保護されない事態が生じる恐れがありました。
今回の改正により、被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示していた場合にも、常に6か月間は配偶者の居住が保護ざれることになりました。
遺産分割までの暫定的な権利ではありますが、即座に明け渡しを求められる、といった事態から配偶者は保護されることになります。
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身又は一定期間、無償で配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利(配偶者居住権)が新設されました。
配偶者短期居住権と比較すると、
①権利の存続期間が終身であること(遺言等で期間の定めをした場合を除く)、
②権利は当然に発生するのではなく、設定行為が必要であることが相違点です。
今後は、遺産分割または被相続人の遺言等によって、配偶者に配偶者居住権を取得させることが出来るようになります。
また、家庭裁判所の審判でも、
①共同相続人の合意がある場合、
②居住建物の不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められる場合、
には、配偶者居住権の設定が可能とされています。
主な効力は以下のとおりです。
①登記請求権があります(新法1031条)
②第三者対抗要件は配偶者居住権の登記のみです(「占有」は不可)。
③妨害停止請求権があります。
④譲渡は不可です(新法1032条2項)
⑤建物所有者の承諾なく増改築、第三者に使用収益させることは不可(新法1032条3項)
消滅事由は以下のとおりです。
①配偶者の規律違反
②死亡
③存続期間満了
現行制度では、相続時、配偶者が居住建物を取得すると、居住建物の評価額によっては他の財産を受け取れなくなってしまい、配偶者の生活費不足の懸念が生じるという事態も考えられました。
今回新設された制度により、配偶者の居住権を確保しつつ、他の財産を取得できる可能性が増えることとなりました。
今後は、この制度がどこまで一般的なものとなっていくかの注視が必要です。
実務的には、長期にわたる配偶者居住権の価値をどう評価するのか(配偶者居住権の負担付不動産の評価)、配偶者がまだ若い場合「終身」の利用を認めるのかが適切なのか、といったことが大きな問題となってくるものと予想されます。
現行制度では、被相続人が生前、自らの意思に基づいて贈与を行ったとしても、当該贈与は遺産の先渡し(特別受益)とみなされ、持ち戻しの対象となります。
配偶者が取得する権利は、贈与が無かった場合と同じになり、被相続人が配偶者に対して行った趣旨が遺産分割の結果に反映されませんでした。
特別受益は、相続人間の実質的公平を図る制度ですので、当然と言えば当然の帰結でした。
今回の改正では、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、民法903条3項の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定し、原則として、遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして持ち戻しの計算をする必要がなくなりました。
これにより、配偶者は、結果的に、より多くの財産を取得できることになり、被相続人が行った遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となります。
現行制度では、平成28年12月19日最高裁判決により、相続財産に含まれる預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人の一人が自己の相続分のみを単独で払い戻しをすることが出来なくなりました。
(上記判決が出される前は、相続開始と同時に相続人に相続割合に応じて当然に分割・帰属すると判断されていました。)
相続発生直後は、葬儀費用の支払いや当面の生活費、相続債務の弁済など、資金需要が生じることが多いところ、遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払い戻しが出来ないことになり、相続人にとっては困る事態となることが懸念されました。
今回の改正では、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応することが出来るように、2つの制度が導入されました。
1つ目は、家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策です。預貯金の仮分割の仮処分について、家事事件手続法200条2項の要件を緩和し、家庭裁判所に審判又は調停の申し立てがあった場合において、相続債務の弁済、相続人の生活費の支弁等を考慮し、他の共同相続人の利益を害しない限り、申し立てにより、預貯金の一部又は全部を仮に取得させることができる(家事事件手続法200条3項)とされました。
2つ目は、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが受けられる制度の創設です。遺産に属する預貯金のうち、一定額については単独での払い戻しが認められることとなりました。具体的には、預貯金の各口座残高の3分の1に当該相続人の相続分を掛け合わせた金額(但し、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定められる額を上限とする)を払い戻すことが出来るようになりました。
今回の法改正で、遺産分割における一部分割の規定が新設されました(新民法907条)。
①遺言で禁じられた場合を除き、共同相続人はいつでも協議で遺産の一部の分割が出来る。
②相続人は、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求することが出来る。
③但し、一部分割により他の相続人の利益を害する恐れがある場合は、この限りでない。
お分かりのとおり、従来の実務を追認し、明文化したものです。
平成28年最高裁判決により、預貯金債権も分割対象となりましたが、例えば預貯金だけを先に分割する、といった活用が予想されます。
もっとも、残りの遺産(例えば無価値の不動産等)が放置されるといった事態が懸念されます。
遺産分割前に遺産に属する財産が一部の相続人により処分(不正取得等)された場合、不公平な結果が生じることが指摘されていました。
遺産分割は、分割時に存在している遺産をどう分けるかという話ですので、分割時に存在していない遺産は対象外であることから生じる不公平でした。
今回の法改正において、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことが出来るとされました(新民法906条の2第1項)。
これにより、不正な処分がなかった場合と同じ結果の実現が期待されます。
現行制度においては、自筆証書遺言を作成する場合には、全文自書する必要がありました。財産目録も全文を自書しなければならず、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることは出来ませんでした。
このため、財産が多数ある場合には全文の自書は相当な負担となっていました。
今回の改正により、自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、通帳の写しや不動産の登記事項証明書等を目録等として添付するなどして遺言を有効に作成することが可能となりました。
但し、自書によらない部分の目録は1ページごとに署名・押印しなければならないとされています。
改正民法の審議過程において、遺言書本文と財産目録の一体性確保の見地から、契印や同一印による押印を要件とすることが検討されました。
しかし、現行民法上でも、遺言が複数ページに渡る場合でも契印を要求しておらず、実印の押印を要求しているものでも無いことから、契印等を求めても変造防止の効果は限定的であり、逆にこのような要件を付すと方式違反が増えるおそれがあるなどの事情もあり、契印、同一の印による押印までは要求しないことになりました。
方式が緩和されたこと及び後述する法務局による保管制度の創設により、自筆証書遺言の利用が増加することが見込まれます。
自筆証書遺言には、保管をどうするかという問題が必ず付きまといました。
紛失、保管場所の忘却の恐れがあるほか、分かりにくいところに保管した結果、自分が死亡した後、家族に発見してもらえなければ意味がありません。
かといって分かりやすい場所に保管していると、相続人による毀棄・隠匿・変造の恐れもあります。
今回、法務局(遺言書保管所)において自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。この手続きについては民法の改正ではなく、新法が制定されました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。
この制度を利用するには、まず遺言者が法務局に自ら出頭し、封緘していない自筆証書遺言を提出して保管の申請を行います。
遺言書の保管に関する事務は、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。
この際、法務局は内容の審査までは行いませんが、外形的に自筆証書遺言の方式に適合しているかの確認を行います。
法務局は遺言書そのものを保管し、遺言書の画像情報を磁気ディスクに保管します。
保管の申請をした後、遺言者は出頭して保管の撤回書を提出し、保管の申請を撤回することができます。
相続人等は、相続開始後、法務局に対し、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付や遺言書原本の閲覧の請求をすることができます。
遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知するとされています。
新法により保管された遺言書については、家庭裁判所の検認手続は不要となります。これにより、公正証書遺言と同様、遺言者の死亡後、直ちに自筆証書遺言に基づいて相続登記や遺産である預金の解約等が可能となります。
法務局が関与することにより、遺言無能力、方式不備による無効、偽造、変造の懸念といった自筆証書遺言のデメリットが多くの場合で解消され、検認手続も不要となって相続人の負担も小さくなり、上述の方式緩和と合わせて自筆証書遺言の利用の増加が期待されます。
現行制度では、遺留分減殺請求権が行使されると当然に物権的効果が生じ、共有状態が生じることになりました。
価額賠償が行われない場合、共有物分割の手続きが必要となり、極めて時間と手間、コストがかかる事態となってしまっていました。
事業承継の支障となっているという指摘もありました。
改正法では、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが出来ることとなりました。
受遺者は、金銭債務を負うことにはなりますが、共有化は免れ、単独所有となります。
今回の見直しにより、遺留分減殺請求権の行使により当然に共有関係が生ずることを回避することが出来、かつ遺贈や贈与の目的財産を受遺者に与えたいという遺言者の意思を尊重することが出来ることとなりました。
遺留分権利者としても、その多くは共有ではなく、金銭をもらうことによる解決を望んでいるのであり、これが正面から認められることになりました。
受遺者が中小企業等の後継者である場合には、会社資産や自社株式を単独所有できることとなり、中小企業等における事業承継にとっても好都合となります。
金銭債権化された点について、金銭を直ちには準備できない受遺者または受贈者に配慮して、受遺者等の請求により、裁判所が金銭債務の全部または一部の支払いにつき、相当の期限を許与することが出来るとされました。
現行制度では、相続人への贈与(特別受益)は全て遺留分額算定の基礎となる財産に算入されていました。
したがって、何十年前の贈与でも、遺留分減殺の対象とされていました。
改正法では、相続人への贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り算入されることになりました。
したがって、実務的に紛争になりがちな相続開始の10年以上前に行われた(証拠も少ない)特別受益、自社株の贈与等は遺留分減殺の対象とはならなくなり、議論しなくて済むことになります。
従前の実務では、早くから後継者を決めて事業承継のために自社株の贈与等を行っても、相続人の一人に対する贈与は、何十年前のものであっても遡って遺留分の基礎に算入されるため事業承継の障害となっていました。
今後は贈与等を行った後、10年以上生存していれば遺留分の基礎から外れることが明確となりましたので、早期の事業承継を促す契機になるものと思われます。
現行制度では、多くの遺言で採用されている「相続させる」旨の遺言等により承継された財産については、包括承継であることを前提に、登記なくして第三者に対抗することが出来るとされていました。
しかしながら、上記実務は、遺言の有無や内容を知りえない相続債権者・債務者・取引関係者の利益を害する可能性があり、登記制度や強制執行制度の信頼を害する恐れがあると指摘されていました。
改正により、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記・登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとされ、第三者の取引の安全が確保されることとなりました。
現行制度では、相続人以外の者が被相続人の療養看護等を行っても、相続財産を取得することは出来ませんでした。
例えば、夫の母と同居していた妻が、夫の死亡後、夫の母の介護をしていたような場合、夫の母の死亡時、相続人は夫の母の介護等を全く行っていなくても相続財産を取得することが出来る一方、妻は相続人ではないため、相続財産の分配を受けることが出来ませんでした。
改正により、被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与を行った被相続人の親族は、相続人に対し、寄与に応じた金銭を請求することが出来るようになりました。
これにより、介護等の貢献に報いることができ、関係者の実質的公平が図られることが期待されます。
上記請求につき、当事者間で協議が調わない場合には、特別寄与者は、家庭裁判所に対し、協議に代わる処分を請求できることとされました。
家庭裁判所は、一切の事情(寄与の時期・期間・方法・程度・相続財産の内容等)を考慮して、額を定めることになります。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚サービス案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日