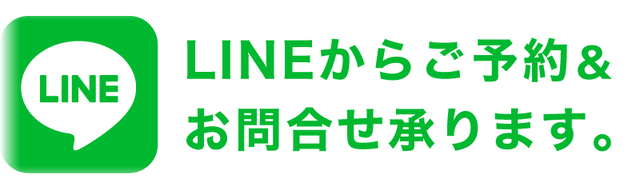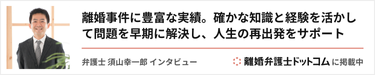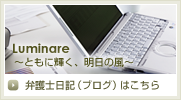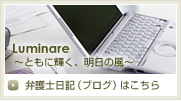弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の方式(原則)
自筆証書遺言は、遺言の内容の全文、日付及び氏名を自書するとともに、押印をすることによって成立します(民法968条1項)。
全文の自書が要件とされているのは、自書であれば筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき、それによって遺言が遺言者の真意に基づくものであると判断できるためです。
自書とは、遺言者が自らの手で書くことをいいます。手が不自由である場合には、足や口で書いた場合も自書となります。
他人の代筆によって作成された場合は、遺言者の言葉をいかに正確に筆記したとしても自書とは認められません。また、ワード等の文書作成ソフトで作成された文書や音声を記録したテープ、ビデオについても、自書の要件をみたしません。
自分で文字を書くことが困難な場合は、自書能力が不要な公正証書遺言か秘密証書遺言によるべきといえます。
他人の添え手による補助を受けて書いた遺言の効力については原則として無効ですが、最高裁は、以下のとおり、例外的に有効となるための3要件を示しました。
最判昭62.10.8は、他人による添え手による補助を受けた自筆証書遺言について、
①遺言者本人が自書能力を有し、
②他人の添え手が、始筆もしくは改行にあたり、もしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ
③添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合は、例外的に自書の要件をみたすとしました。
この判決に従えば、他人の補助は、遺言者の手を文頭等の適切な場所に導く等の最低限の程度にとどめるべきといえます。
また、「全文」とは、遺言事項を書き記した部分、すなわち本文をいいます。
日付は、遺言書作成時の遺言者の遺言能力の有無についての判断や、複数の遺言書が存在する場合の各遺言作成時期の前後の確定のために必要です。
自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成し、作成条項について証人が存在しないことが多いことから、遺言の成立時期を明確にするため、遺言書に日付の記載が必要とされています。
① 年月日
日付の記載は、遺言の成立時期を明確にするために要求されているので、年月日を明らかにして特定の日を表示しているといえるように記載する必要があります。
判例では、「○月吉日」のような遺言は、特定の日を表示したものとみることができないことから、日付の記載を欠くものとして無効とされています。
なお、日付も自書によることが必要ですから、日付印等を使用した場合には遺言は無効となります。
② 記載場所
日付の記載場所については特に定めがありません。
遺言書本体に日付を記載せず、これを封筒に入れた上で、その封筒に日付を自書した事案でも、遺言は有効とされた例があります(福岡高判昭27.2.27)。
ただし、封筒はすりかえることが可能であり、遺言者の死後に紛争となってしまう可能性がありますので、遺言書本体の冒頭ないし末尾に記載することが確実だといえます。後述の氏名の記載及び押印の場所についても同じことがいえます。
③ 記載すべき日付
遺言成立の日付を指し、原則として、遺言書の全文を記載した日付を記載する必要があります。
④ 遺言書が複数枚にわたる場合
遺言書が複数枚にわたる場合でも、その遺言書が1通の遺言書として作成されているときは、日付の自書はそのうちの1枚についてされていれば足り、必ずしも1枚ごとにする必要はありません。
遺言者の署名および押印についても同様のことがいえます。
我が国では、重要な文書は署名ないし記名の後に押印するのが通常であるという理由から、遺言書にも押印が要求されています。
押印は、全文の自書等と同様、遺言者の同一性および真意を確保するとともに、これにより文書が完結したことを担保するための要件とされています。
遺言の押印に用いる印は、実印である必要はなく、いわゆる認印でも構いません。また、拇印ないし指印でもよいとされています(最判平元・2.16判時13063)。
しかし、栂印ないし指印については、遺言者の死亡後には対照すべき印影がないのが通常でしょうから、紛争を防止する観点から、極力避けた方がよいといえます。
押印の場所について民法上規定はありませんが、遺言書自体に署名した上で、その横か下に押印するのが通常です。
遺言書が複数枚にわたる場合、連続した一通の遺言書であることを示すために契印をするのが通常です。
民法上、遺言の要件として契印を行うことは挙げられていませんので、契印がなかったとしても、遺言の内容、遺言書の体裁からみて、一通の遺言書であると判断できれば、遺言は一個の遺言として有効であると考えられています。
押印は遺言者本人がするのが原則です。他人に押印させた場合でも、遺言者自身が押印したのと同視できるような特別の事情があれば例外的に有効とされているケースもありますが、遺言者本人が押印することが確実です。
一旦作成した自筆証書遺言に加除訂正する場合、方法を誤ると、遺言書が無効となりますので、加除訂正をする際は注意が必要です。
遺言書の加除その他の変更の方式は、
①遺言者自身によりなされること 、
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること、
③付記部分に署名すること、
④変更の場所に押印すること
です(民法968条3項)。
民法が遺言について、訂正箇所への署名まで要求するという厳格な方法を採用したのは、他人による遺言書の改ざんを防止するためです。
上記方式に従わないでした加除訂正は無効であり、その加除訂正はなされなかったものとして扱われます。
この場合には、加除訂正に方式違背があるだけで、当該遺言書全体が当然に無効となるわけではありませんので、加除訂正の前の記載が判読可能であれば、訂正前の文言が記載された遺言として扱われることとなります。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日