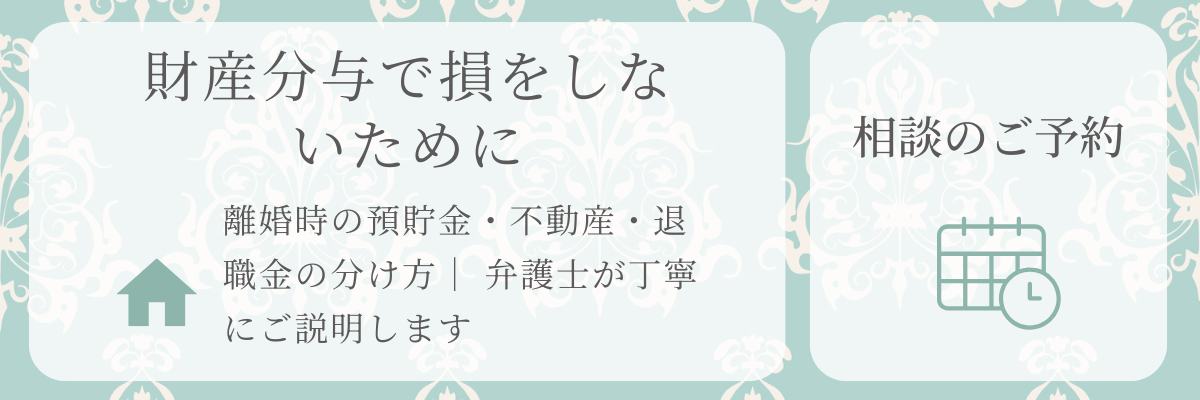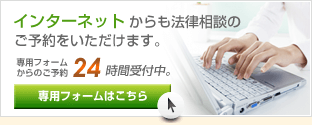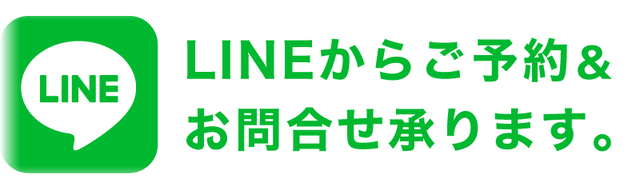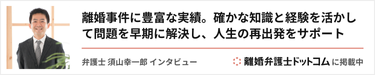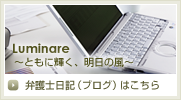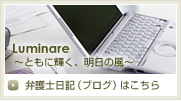弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
財産分与で損をしないために|神戸の弁護士が分かりやすく解説
離婚にあたって行う「財産分与」は、夫婦が婚姻中に築いた財産をどのように分けるかを決める、非常に重要な手続です。
進め方や考え方を誤ると、
「本来もらえるはずの財産を受け取れなかった」
「後からやり直したいと思っても手遅れだった」
という事態にもなりかねません。
このページでは、財産分与の基本から実務上のポイントまでを整理して解説しています。話し合いを始める前に、ぜひ一度ご確認ください。
①財産分与の基礎知識(最初に読む)
②財産分与の対象となる財産
③財産評価と基準時(いつ・いくらで分けるか)
④不動産・住宅ローンがある場合
⑤将来財産・収入に関する問題
⑥財産隠し・争いがあるケース
⑦財産分与に応じない場合・手続の流れ
⑧期限・税金・特殊な分与
①財産分与の基礎知識(最初に読む)
離婚時の「財産分与」とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産をどのように分けるかを決める手続です(これを「清算的財産分与」といいます)。
財産分与を検討する際には、感情や印象だけで判断するのではなく、次の3つの視点を順に整理して考えることが非常に重要です。
① どの財産が分与の対象になるのか(対象財産の特定)
② いつの時点の財産を基準に分けるのか(基準時)
③ その財産をどのような割合・方法で分けるのか
このページでは、これら3つのポイントを軸に、実務上よく問題となる論点を順を追って解説しています。
以下の各項目が、「どの段階の問題にあたるのか」を意識しながら読み進めていただくと、財産分与全体の考え方が理解しやすくなるはずです。
財産分与は、最終的には当事者同士の話し合いによって、双方が納得できる分け方を模索していくことになります。
もっとも、実務上は、婚姻期間中に形成された財産については、夫婦双方の寄与(貢献度)は原則として等しいと考えられ、特段の事情がない限り、50%ずつ分ける(2分の1ルール)のが一般的です。
実際の裁判実務においても、この2分の1ルールが修正されるケースは極めて稀といえます。改正後の民法768条3項は、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と規定しています。
実務上の注意点
①現物で分ける場合の注意点
不動産や自動車など、名義の変更が必要となる財産については、現在の名義を必ず確認したうえで、名義変更に必要な書類を確実に受け取っておくことが重要です。
② 現金で分ける場合の注意点
財産を換価して現金で分ける場合は、できる限り一括払いとすることをおすすめします。
分割払いとした場合、支払う側の経済状況や支払意思が変化し、支払いが滞るケースが少なくありません。
やむを得ず分割払いとする場合には、初回の支払額を多めに設定する、支払期間をできるだけ短くするなどの工夫が必要です。
③ 協議離婚の場合の書面化の重要性
協議離婚では、財産分与について合意したとしても、その内容を文書にしておかなければ、後に「言った・言わない」といった紛争が生じるおそれがあります。
そのため、協議離婚の場合でも、合意内容を明記した離婚協議書や公正証書を作成し、双方が署名・押印しておくことが重要です。
④ 分割払いの場合のリスク対策
分割払いを認める合意をする場合には、万一支払いが滞った場合に備え、可能な限り強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきましょう。これにより、相手が支払わなくなった場合でも、裁判を経ることなく、預貯金や給与などの差押えを行うことが可能になります。
財産分与における2分の1ルールは、現在の実務において確立された原則です。
もっとも、例外的に、2分の1ルールの修正が認められる可能性があるケースも存在しますが、実務上はその範囲は極めて限定的である点に注意が必要です。
たとえば、次のような場合です。
- 夫婦の一方が、芸術家・発明家・プロスポーツ選手など、特別な才能や能力を有することで高額の収入を得ている場合
- 医師などの高度な専門職として、専門資格・専門技術に基づき高収入を得ている場合
これらのケースでは、専門家となるための資格や高度な専門技術を、婚姻前に、時間・費用・労力をかけて習得していると評価される場合があるからです。
このような場合には、2分の1ルールの例外を主張する側が、次の点を具体的に立証する必要があります。
- 専門資格・専門技術・才能を婚姻前に習得していたこと
- その習得のために、個人として相当な努力・費用を要したこと
- その能力や才能が、一般的なものではなく、特異性を有するものであること
- 婚姻後の財産形成について、他方配偶者の寄与がない、または極めて小さいこと
一方で、
- 配偶者が家事や育児を十分に行っていなかった
- 日常的に「無為徒食」の生活を送っていた
といった主張は、程度の問題にとどまることが多く、実務上、2分の1ルールを修正する理由とはされていないのが実情です。
また、そのような生活実態自体が争点となることも多く、多数のエピソードを挙げたとしても、直ちに修正理由として認められることは殆どありません。
②財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻後に協力して形成した財産です。
名義が夫婦のどちらになっているかにかかわらず、原則として分与の対象になります。
代表的な対象財産には、次のようなものがあります。
- 現金・預貯金
- 財形貯蓄
- 不動産
- 株式などの有価証券(NISA口座を含む)
- 暗号資産
- 積立型の生命保険
- 学資保険
- 自動車
- 退職金
- 私的年金(個人型確定拠出年金(iDeCo)など)
- 自営業者の場合の事業用財産
これらは、婚姻期間中に形成されたものであれば、夫名義・妻名義を問わず、財産分与の対象となります。
負債(借金)がある場合の考え方
借金などの負債については、プラスの財産から控除したうえで財産分与を検討するのが実務上の考え方です。
その際には、
「どちらの名義で負債があるのか」
「離婚後、どちらが返済義務を負うのか」
といった点を踏まえて、個別に判断されます。
保険の扱いについての注意点
生命保険については、被保険者が誰であるかではなく、契約者が誰であるかが重要です。
積立型保険の場合、契約者名義を確認したうえで、その解約返戻金相当額が分与対象となるかを検討します。
事業用財産の取り扱い
事業用財産については、個人事業の場合は、原則として財産分与の対象となります。
一方で、法人名義の財産そのものは、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし、
- 当該法人の株式
- 出資金
については、個人が保有する財産として財産分与の対象になります。
離婚時の財産分与では、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。
夫婦の協力によって形成されたとはいえない財産は、「特有財産」として、財産分与の対象から除外されます。
特有財産に該当する主なもの
一般的に、次のような財産は特有財産とされます。
- 婚姻前から有していた財産
- 婚姻後に贈与または相続によって取得した財産
このように、当該財産の形成について他方配偶者の寄与が認められない場合には、特有財産として扱われます。
婚姻前取得財産でも分与対象となる場合がある点に注意
たとえば、結婚前から不動産や自動車を所有していた場合でも、婚姻後の収入からローン返済が行われていれば、その返済相当部分は財産分与の対象となります。
「名義が婚姻前だから全て特有財産」という理解は、必ずしも正確ではありません。
専有品・夫婦間贈与の扱い
社会通念上、一方の専有品と評価できる
- 衣類
- 宝飾品
- 個人的に使用する持ち物
や、夫婦間で贈与された財産は、特有財産として扱われます。
特有財産の立証責任は誰にあるか
特有財産であることは、それを主張する側が立証責任を負います。
また、
- 相続した金銭を原資として不動産を購入した場合
- 特有財産が形を変えた場合
であっても、特有財産性そのものが自動的に認められるわけではなく、原資との明確な紐づけが必要です。
立証は「財産ごと」に必要です
特有財産の主張は、個々の財産ごとに行う必要があります。
調停手続では、「基準時(別居時)の残高 − 婚姻時の残高」といった包括的な計算方法が用いられることもありますが、訴訟では原則として認められていません。
普通預金は特有財産性を失いやすい
普通預金は、日常的な入出金が行われることが多く、婚姻後の給与や生活費と混在することによって、基準時において特有財産性を喪失していると評価されるのが一般的です。
そのため、「基準時残高から婚姻時残高を控除する」という主張は、訴訟では認められない可能性が高いといえます。
生命保険の特有財産性
生命保険については、次のように取り扱われます。
- 親(または祖父母)が保険料を支払っていた場合
- 特有財産を原資に保険料を全額前納している場合
は、特有財産となります。
また、婚姻前から継続している保険については、
- 婚姻前に支払った保険料に対応する解約返戻金相当額は特有財産
計算方法は
- 基準時の解約返戻金 − 婚姻時の解約返戻金 となります。
株式・有価証券の注意点
婚姻前に取得した株式は、原則として特有財産となりえます。しかし、婚姻後に、
- 継続的・頻繁な売買を行っている
- 追加入金を行っている
ような場合には、婚姻後財産と混然一体と評価され、特有財産性を失う可能性があります。
婚姻前購入の住宅ローン付き不動産
婚姻前に一方が住宅ローン付きで購入した不動産についても、婚姻後の収入から返済が行われていれば、婚姻時から基準時までの返済相当部分は財産分与の対象となります。
計算式の一例:不動産の時価×(住宅ローン残高減少額÷購入価格)
特有財産の主張は専門的判断が不可欠です
特有財産の判断は、
- 原資
- 取得時期
- 管理状況
- 混在の有無
といった要素を踏まえた専門的な検討が必要です。
当事務所では、
「特有財産として主張できるかの見通し」
「立証資料の整理」
「調停・訴訟それぞれを見据えた戦略」
まで含めたサポートを行っています。財産分与で不利にならないためにも、早めに専門家へご相談ください。
離婚を検討する際、「子ども名義の預貯金まで財産分与で分ける必要があるのか」
という点は、非常に多くの方が悩まれるポイントです。
結論:名義ではなく「実質」で判断されます
子ども名義の預貯金であっても、必ずしも財産分与の対象外になるわけではありません。財産分与では、名義ではなく、原資と管理状況とい「実質」を重視して判断されます。
話し合いで解決できる場合
夫婦間の協議により、
- 子ども名義の預貯金は子どものための財産である
- 親権者となる側が管理を引き継ぐ
と合意できるのであれば、財産分与の対象から外すことはもちろん可能です。実務上も、このような形で解決されるケースは少なくありません。
話し合いがまとまらない場合の判断基準
協議が成立せず、裁判所が判断することになった場合には、次の点が重視されます。
- 預貯金の原資が夫婦の収入であるか
- 通帳・キャッシュカード・銀行印の管理を親が行っていたか
- 入出金の判断を親がしていたか
これらに該当する場合、子ども名義であっても、夫婦の実質的な共有財産と評価され、財産分与の対象とされる可能性があります。
財産分与の対象とならないケース
次のような場合には、子どもの固有財産として財産分与の対象外となります。
- 子どもが一定の年齢に達し、自ら預金を管理している場合
- 原資が、
- 出産祝金
- お年玉
- 親族からの贈与
- 子ども自身のアルバイト収入
などであり、夫婦の収入によらないことが明らかな場合
学資保険の取り扱い
学資保険についても、原則的な考え方は同様です。
保険料の支払原資が夫婦の収入であれば、財産分与の対象となる可能性があります。
もっとも、実務では、解約して返戻金として分けるのではなく、親権者となる側へ名義変更し、保険契約を継続するといった方法で処理されるケースが多く見られます。
子どもの将来と不利にならないために
子ども名義の預貯金や学資保険は、金額だけでなく、子どもの将来や親権問題とも密接に関係する重要な論点です。表面的な名義だけで判断すると、思わぬ不利益を受けることもあります。
当事務所では、
- 財産分与の対象になるかどうかの見通し
- 交渉段階での整理方法
- 裁判になった場合のリスクと対策
を踏まえ、具体的事案に即したアドバイスを行っています。
子ども名義の財産についてご不安がある方は、早めにご相談ください。
財産分与の話し合いでは、不動産や預貯金だけでなく、自宅内にある動産(家具・家電・生活用品など)をどちらが取得するのかも問題となります。
もっとも、動産の扱いについては誤解されやすいポイントが多く、感情的な対立に発展することも少なくありません。
実務でよくある取り扱い
実際の協議では、
「それぞれが今後の生活に必要な動産を取得する」
「不要な動産は処分し、その費用を折半する」
といった方法で解決するケースが多いのが実情です。
裁判になった場合の動産の評価
協議がまとまらず、家庭裁判所で判断される場合、自動車などを除く一般的な動産は、特別な事情がない限り「経済的価値は認められない」と扱われるのが通常です。
そのため、家具・家電・日用品などが財産分与の中心的な争点となることは、実務上あまり多くありません。
「細かい動産まで裁判で公平に分けてもらえる」と期待される方もいますが、実際には判断の対象外とされることが多い点には注意が必要です。
高級時計・宝飾品の取り扱い
一方から他方へプレゼントされた高級時計や宝飾金については、
「贈与であることが明らか」
「社会通念上、個人的な使用を予定したもの」
と評価される場合、受け取った側の特有財産として、財産分与の対象外とされることが多いと考えられます。
動産の扱いで揉めそうな場合は早めの相談を
もっとも、購入時期や購入資金、使用状況などによって結論が変わることもあり、一律には判断できません。
動産は金銭的価値が小さい一方で、感情的対立が激化しやすい分野です。
無用な争いを避け、離婚後の生活を早期に安定させるためには、法的な見通しを踏まえた冷静な判断が重要です。
動産の取り扱いでお悩みの方は、早い段階で一度ご相談ください。
離婚に際して、「ペットは財産分与でどう扱われるのか」という問題は、金銭以上に感情が絡みやすい重要な論点です。
結論:ペットは原則として財産分与の対象ではありません
ペットは、物として評価し金銭的に分け合うという財産分与の趣旨になじまないため、原則として分与対象財産とは扱われません。
裁判実務においても、ペットを金銭評価して清算する判断は多くありません。
どちらがペットを引き取るかが中心的な問題になります
問題となるのは、「ペットをどちらが引き取るのか」という点です。
双方が引き取りを希望する場合、財産分与だけでは解決が困難となり、次の事情が考慮されることが一般的です。
- 現在、主としてペットの世話をしているのはどちらか
- これまでの飼育の中心的役割を担ってきたのはどちらか
- 子どもがいる場合、子どもが日常的に可愛がっているか
- 離婚後の飼育環境・生活状況
これらを総合的に考慮した結果、親権者となる側が引き取るケースが多いといえます。
飼育費用の負担について
ペットを引き取る側が、飼育費用(餌代、医療費等)を負担するのが原則です。
もっとも、引き取りを希望するものの、経済的余力に不安がある場合には、次のような解決方法が検討されることもあります。
- ペットを離婚後も夫婦の共有物と位置づける
- 飼育する側の管理のもとで、他方が一定額の飼育費用を分担する
ただし、この方法は継続的な関係が前提となるため、後日の紛争リスクを十分に検討する必要があります。
金銭的評価は行わないのが一般的です
ペットについては、どちらが引き取るかのみを定め、財産的価値はゼロと評価し、金銭的な精算は行わないという取り扱いが、実務上は一般的です。
ペットを巡る争いを長期化させないために
ペットは家族同然の存在である一方、法的には扱いが限定的であるため、感情と法的評価のギャップが紛争を長期化させがちです。早期に法的な見通しを把握し、冷静な落としどころを検討することが重要です。
当事務所では、
- ペットの引き取りに関する整理
- 合意書への具体的な落とし込み
- 将来紛争を防ぐための条項設計
まで含めたアドバイスを行っています。ペットの扱いでお悩みの方はご相談ください。
離婚に際し、「個人事業の設備や資産も財産分与で分ける必要があるのか」という点は、事業者の方にとって特に重要な問題です。
結論:名義にかかわらず、原則として財産分与の対象となります
夫婦の一方が個人事業を営んでいる場合や、夫婦が共同で事業を行っている場合には、その事業のために購入した設備・備品・その他の事業用財産は、たとえ一方名義であっても、婚姻期間中に取得したものであれば、原則として実質的な共有財産と評価され、財産分与の対象となります。
ここでも重要なのは、名義ではなく、取得時期と原資という「実質」です。
対象となりやすい事業用財産の例
- 事業用の機械・設備・工具
- 店舗内装・什器
- 業務用車両
- 事業用として購入したパソコン・備品 など
これらは、事業継続に使用されていても、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産と評価される可能性があります。
財産分与の対象とならないケース
もっとも、次のような場合には、財産分与の対象外(特有財産)となります。
- 事業用財産が相続によって取得されたものである場合
- 相続した財産を換価し、その代金を原資として取得した事業用財産である場合
この場合、婚姻中に取得されていても、原資が相続財産であることが立証できれば、分与対象とはなりません。
実務上の注意点:事業継続とのバランス
事業用財産は、単純に「半分に分ける」ことができないケースも多く、
- 評価方法
- 事業継続への影響
- 金銭清算の可否
といった点を踏まえた柔軟な調整が必要になります。
安易に争いになると、事業そのものの存続に支障が出るおそれもあります。
事業用財産が関係する離婚では早期相談が重要です
事業用財産の財産分与は、一般的な家計財産や動産・不動産とは異なり、専門的な判断が不可欠です。
当事務所では、
- 財産分与の対象となる範囲の整理
- 特有財産の主張・立証方針
- 事業継続を前提とした分与方法の設計
まで含めたサポートを行っています。個人事業や会社経営に関わる財産分与でお悩みの方は、早めにご相談ください。
医師が経営に関わる医療法人の場合、「医療法人の持分は離婚時の財産分与の対象になるのか」という点は、極めて重要かつ専門的な問題です。
平成18年の法改正後に設立された医療法人
平成18年の医療法改正により、平成19年4月1日以降、新たに「持分あり」の医療法人は設立できなくなりました。そのため、この日以降に設立された医療法人については、社員としての地位に財産的価値は認められず、財産分与の対象とはなりません
単に医療法人の社員であるという理由だけで、分与請求が認められることは原則としてありません。
法改正前に設立された「持分あり」医療法人の場合
一方、平成19年4月1日以前に設立され、その後も持分なし医療法人へ移行していない医療法人(いわゆる経過措置型医療法人(持分あり医療法人))については、話が異なります。
この場合、出資持分には財産的価値があり、財産分与の対象となります。
持分とは、
- 社員が退社した際に、出資割合に応じて払戻しを受ける権利
- 医療法人が解散した場合に、残余財産の分配を受ける権利
を意味し、明確な経済的価値を有しています。
具体例で見る持分の価値
たとえば、
院長と別の医師が、それぞれ1億円ずつ出資して設立した医療法人が現在、10億円の評価を有している場合
院長は、退社時に出資割合(50%)に応じて、5億円の払戻しを受ける権利を有することになります。
このような持分は、理論上は非常に高額となり得ます。
実務上の最大の問題点:評価の難しさ
もっとも、財産分与において、医療法人の持分をそのまま理論値で評価することは、実務上ほとんどありません。その理由として、
- 非上場株式と同様、評価方法が極めて難しいこと
- 経営に深く関与する社員が、現実的に容易に退社できないこと
- 実際に払戻請求がなされた場合、医療法人の経営や医療提供体制に重大な影響を与える可能性があること
などが挙げられます。
このため、裁判実務や交渉の場面では、事業継続性や換価困難性を考慮したうえで、一定の減額評価が行われるケースが多いと解されています。
医療法人の持分が絡む財産分与は高度な専門分野です
医療法人の出資持分が関係する場合、
- 財産分与額が高額になりやすい
- 法務・会計・税務が複雑に絡み合う
という特徴があり、通常の財産分与とは全く異なる対応が求められます。
そのため、
- 離婚・財産分与に精通した弁護士
- 医療法人の評価に詳しい公認会計士・税理士
が連携して検討することが不可欠です。
医療法人の持分が関係する離婚・財産分与については、早期の専門相談を強くおすすめします。
③財産分与と基準時(いつ・いくらで分けるか)
離婚にあたっては、離婚前に別居するケースが非常に多く、「別居してから離婚成立までの間に財産が増減した場合、どの時点の財産を基準に分けるのか」という疑問がよく生じます。
結論:原則は「別居時」が財産分与の基準時です
財産分与は、夫婦が婚姻生活の中で共同して形成した実質的共有財産を清算する制度です。
そのため、実務では、「夫婦の経済的な共同生活が終了した時点、すなわち、別居時」
が、財産分与の基準時とされています。
別居以降は、原則として夫婦の協力関係が失われているため、それ以降の財産の増減は、分与の前提となる「共有財産の形成」とは評価されないからです。
例外:別居後の事情が考慮されることもあります
もっとも、個別の事情によっては、別居後の財産の変動を一切考慮しないことが著しく不公平となる場合もあります。
そのような場合には、
- 別居後の財産の増減
- その原因や経緯
についても、「一切の事情」として考慮されることがあります。
したがって、実務上は、
- 別居時の財産内容を正確に把握する
- 別居後に財産の増減があったかを確認する
- その変動を考慮しないことが公平かどうかを検討する
というプロセスで、基準時の妥当性を検証する必要があります。
「家庭内別居」は基準時になりにくい
いわゆる家庭内別居については、
- 同居している以上、光熱水費や住居費などを共同で使用している
- 経済的協力関係が「完全に消滅した」と評価することが難しい
という理由から、家庭内別居の開始時点を財産分与の基準時とすることは通常ありません。また、
- 「いつから家庭内別居だったのか」という点は客観的に特定しづらく
- 財産分与の基準時には明確で客観的な時点が求められます
このような事情から、同居したまま離婚調停が申し立てられた場合には、調停申立日を基準時とするのが一般的です。
単身赴任・進学による別居は基準時になりません
単身赴任や子どもの進学のために別々に暮らしている場合は、夫婦の経済的協力関係が継続しているのが通常であるため、財産分与の基準時とはなりません。
ただし、単身赴任中に夫婦関係が悪化し、その後、経済的協力関係が完全に失われたといえる時点があれば、その時点が基準時となり得ます。
もっとも、明確な時点を特定できない場合には、離婚調停の申立日を基準時とするケースが多いといえます。
一時的な帰宅は「同居再開」にはなりません
別居後に、
- 用事のために一時的に帰宅した
- 荷物を取りに立ち寄った
といった事情があっても、同居が再開したとは評価されません。
また、
- 平日は職場付近で生活
- 週末のみ帰宅していたが、次第に帰宅しなくなった
というように、なし崩し的に別居に至った場合には、
- 最後に帰宅した日を特定できる場合は、その日を基準時とすることもあります
- しかし、その後も断続的な立ち寄りがあるなど、判然としない場合には、離婚調停申立日が基準とされることが多いと考えられます。
基準時の判断は財産分与全体を左右します
産分与の基準時は、
- 預貯金残高
- 保険の解約返戻金
- 株式・不動産の評価
など、分与額そのものに直結する極めて重要なポイントです。
誤った基準時を前提に進めてしまうと、大きな不利益につながる可能性があります。
当事務所では、
- 基準時の見通し判断
- 別居後の財産変動の整理
- 調停・訴訟を見据えた主張構成
まで含めてサポートしています。
財産分与では、
「どの財産を分けるのか」
「その財産をいくらとして評価するのか」
という2つの異なる問題を区別して考える必要があります。
財産の「範囲」と「評価時点」は別の問題です
別居から離婚成立までに相当の時間がかかると、その間に、
- 上場株式の株価が変動する
- 不動産価格が上下する
といった事情が生じることがあります。
このような場合、どの時点の価格を用いるのかが問題となります。
結論:評価の基準時は「離婚時」です
財産分与において、対象財産の評価は、原則として離婚時を基準に行われます。
これは、財産分与が「夫婦が離婚する際に、共有財産を最終的に清算する制度」であるためです。
実務上の整理
実務では、次のように整理されます。
- どの財産が財産分与の対象になるか
→ 別居時を基準に確定する
- 確定した対象財産をいくらと評価するか
→ 離婚時を基準に評価する
つまり、「対象財産の範囲は別居時、評価額は離婚時」というのが基本的な考え方です。
注意点:評価時点が結論を左右することもあります
評価時点の違いによって、
- 株式評価額
- 不動産価値
などが大きく変わることもあり、分与額そのものに直結する重要な論点となります。
そのため、
- 評価時点に争いがないか
- 特殊な事情により修正が必要か
といった点も含め、慎重な検討が求められます。
専門的判断が必要な場面です
対象財産と評価時点の整理を誤ると、「本来得られるはずの分与額を大きく下回る」といった不利益が生じる可能性もあります。
当事務所では、
- 財産分与の対象財産の整理
- 評価時点・評価方法の検討
- 調停・訴訟を見据えた主張構成
まで含めてサポートしています。評価額の変動が大きい財産が含まれる場合は、早めに専門家へご相談ください。
財産分与の金額は、感覚的に決められるものではなく、一定の手順に沿って算定されます。
ここでは、実務で用いられる原則的な算定の考え方を説明します。
算定のステップ①|別居時の財産を確定する
まず、財産分与の基準時である別居時において、夫婦それぞれの名義で保有している財産を洗い出します。
この段階では、
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 保険の解約返戻金
など、名義を問わず存在する財産をすべて把握することが重要です。
算定のステップ②|特有財産を控除する
次に、別居時点で存在する財産のうち、
- 婚姻前から保有していた財産
- 相続や贈与によって取得した財産
などの特有財産を控除します。
この控除後に残った財産が、夫婦が婚姻生活の中で共同して形成した「実質的共有財産」となります。
算定のステップ③|積極財産と消極財産を整理する
財産分与は、婚姻後に形成された積極財産(プラスの財産)を清算する制度です。
そのため、
- 積極財産が存在しない場合
- 積極財産から消極財産(借金など)を控除した結果、マイナスとなる場合
には、原則として財産分与請求権は発生しません。
算定のステップ④|2分の1ルールを用いた算定
積極財産から消極財産を控除した結果、なおプラスの財産が残る場合に限り、財産分与が問題となります。
この場合、夫婦の一方に特段の事情がない限り、「2分の1ルール」をベースとして分与額が算定されます。
つまり、「実質的共有財産÷2」が、基本的な分与額となります。
負債超過の場合でも話し合いは可能です。
なお、理論上は「負債超過」の場合であっても、
- どの財産を誰が取得するか
- 誰がどの負債を引き受けるか
といった点について話し合いで取り決めを行うこと自体は可能です。
ただし、これはあくまで合意による処理であり、法律上当然に財産分与請求権が認められるわけではありませんし、債権者を拘束するものでもありません。
算定方法の誤りは大きな不利益につながる可能性があります
財産分与の算定では、
- 財産の把握漏れ
- 特有財産の見落とし
- 負債の扱いの誤り
によって、本来より大きく不利な結果になることも少なくありません。
当事務所では、
- 財産の洗い出し
- 分与対象か否かの整理
- 実務に即した分与額の試算
まで含めたサポートを行っています。財産分与の金額に不安がある方は、早めにご相談ください。
財産分与は、基準時(原則として別居時)に存在する財産を清算する制度です。
そのため、原則としては、基準時より前に自分名義の預貯金を払い出していたとしても、その事実自体が直ちに分与額に影響するわけではありません。
原則:払い出し自体は直ちに問題になりません
基準時前の時点で預貯金を現金化していたとしても、
それが通常の生活費ややむを得ない支出であれば、当然に不利な扱いを受けるものではありません。
例外:不自然な多額の払い出しがある場合
もっとも、次のような事情がある場合には、例外的な扱いがなされます。
- 基準時の直前に
- 多額の預貯金の払い出しが行われており
- その使途について、払い出した側が合理的な説明をできない場合
このようなケースでは、基準時において、払い出した額に相当する財産を現金その他の形で保有していたものと推認し、その金額を含めて財産分与額が算定されることがあります。
いわゆる「使途不明金」を、実質的に隠匿財産と同様に扱う考え方です。
「直前」とはいずれの期間を指すか
どこまでを「基準時の直前」と評価するかは、事案ごとに判断されます。
実務上は、
- 基準時の数か月前
- おおよそ半年程度前
までに行われた多額の払い出しであれば、「直前」と評価される可能性があります。
安易な払い出しは大きな不利益につながります
不自然な資金移動は、かえって裁判所から不利な推認を受け、分与額が増額される結果につながることもあります。
一方で、
- 正当な生活費
- 医療費や事業経費
- やむを得ない支出
であることを、客観的な資料により説明できる場合には、不利に扱われない可能性もあります。
早めの整理と専門的アドバイスが重要です
預貯金の払い出しは、説明可能か、時期・金額が不自然でないか、といった点が、極めて重要になります。
当事務所では、
- 預金の動きの整理
- 使途説明の可否の検討
- 不利な推認を防ぐための主張構成
まで含めたサポートを行っています。基準時前後の預貯金の動きについて不安がある方は、ご相談ください。
離婚に先立って、夫婦の一方が自宅を出て別居に至るケースは非常に多く見られます。
その際、別居する側が、夫婦の実質的な共有財産を持ち出してしまうという問題が生じることがあります。
よくあるトラブルの例
典型的なのが、夫婦の一方が、他方配偶者名義の預金通帳やキャッシュカードを持ち出し、預貯金を引き出して生活費等に使用し、離婚時には、口座残高が大きく減っている
といったケースです。
原則:持ち出した額は「先取り」したものとして扱われます
財産分与の基準時は、原則として別居時です。
そのため、別居後に、他方配偶者の預貯金を払い出して費消した場合、その払い出した金額は、財産分与を先行して取得したものと評価します。
具体的には、持ち出した金額を、最終的な財産分与額から控除する形で清算されるのが原則です。
実務上よく用いられる調整方法
別居後、「持ち出した側が婚姻費用の支払いを受けていない」「生活費としてやむを得ず使用した」といった事情がある場合には、持ち出し額と未払いの婚姻費用を関連づけて清算することも実務上よく行われます。
たとえば、
- 未払いの婚姻費用が50万円
- 持ち出して費消した金額が30万円
という場合には、30万円分を婚姻費用の一部として充当し、残り20万円を未払い婚姻費用として精算するといった解決が考えられます。
不利な評価を避けるために重要なポイント
持ち出した財産の扱いは、金額、時期、使途の合理性によって評価が大きく変わります。
特に、高額、使途不明、別居直後といった事情が重なると、不利な判断を受ける可能性が高まります。
④不動産・住宅ローンがある場合
離婚時の財産分与において、住宅ローンが残っている自宅をどう扱うかは、解決が難しい重要な問題です。
実務では、まず「住宅の時価」と「住宅ローン残高」の関係を確認することから検討します。
①住宅ローン残高が家の価値を上回る場合(オーバーローン)
住宅ローンの残債務額が、住宅の時価より高い場合(オーバーローン)には、売却代金だけではローンを完済できないため、原則として売却は困難です。
銀行(住宅ローン債権者)は、残債務が全額弁済されない限り抵当権の抹消に同意しないのが通常であり、不足分を自己負担できなければ売却はできません。
この場合は、
「現在の名義人が所有名義を維持し、ローン名義人がそのまま返済を継続する」
という処理が原則となります。
【名義変更して住み続ける場合の注意点】
例えば、夫名義の住宅を、財産分与を原因として妻名義に変更し、妻が毎月ローン相当額を夫に支払って住み続ける、という合意がされることもあります。
しかし、
- 多くの住宅ローン契約では、完済前の名義変更は禁止されています
- ローン支払い中の名義変更は、金融機関との関係では契約違反となる可能性があります
さらに、仮に名義変更をしても、抵当権とローン債務が夫名義のまま残る場合には、妻は「夫の住宅ローンの担保として自宅を差し入れている状態」となります。
夫が将来ローンの支払いを停止すれば、住宅は競売にかけられ、退去を迫られるリスクがあります。
このように、抵当権を残したまま名義だけを変更する場合には、「将来の支払能力」「約束が履行される見込み」を十分に慎重に検討する必要があります。
②住宅の時価がローン残高を上回る場合(余剰がある場合)
住宅の時価が住宅ローン残高を上回る場合には、「住宅の価値=時価−ローン残高」
として評価します。
この場合、財産分与の方法として、主に次の選択肢が考えられます。
- 居住を継続する一方配偶者が、余剰分の一定割合(通常は半額)を金銭で支払う方法
- 住宅を売却してローンを完済し、残った余剰を分ける方法
- 金融機関の承諾を得て債務者変更を行い、居住を継続する方法
③財産分与請求権が発生しない場合でも注意が必要です
住宅の時価よりローン残高の方が大きい場合(オーバーローン)には、住宅自体についての財産分与請求権は、原則として発生しません。
もっとも、住宅以外に預貯金等の財産がある場合には、それらを含めて全体で財産分与を検討します。
また、オーバーローンであっても、住宅ローンは婚姻共同生活のために負担した債務であるため、夫婦間では、分担方法について協議する必要があります。
ただし、これはあくまで「夫婦内部の問題」であり、金融機関に対する関係では、ローン名義人が全額の返済義務を負います。
④別居後に支払った住宅ローンの扱い
別居後に、夫または妻の一方が住宅ローンを返済していた場合には、離婚時の評価額から「別居時点のローン残高」を控除して検討することが一般的です。
別居後の返済については他方配偶者の寄与が認められないため、離婚時点のローン残高ではなく、別居時の残高を基準とするのが適切であるとの考え方です。
⑤連帯債務・連帯保証がある場合の注意点
夫婦が連帯債務者になっている場合や、一方が他方の連帯保証人になっている場合、住宅を取得しない側が「債務や保証から外れたい」と考えるのは自然です。
しかし、そもそも単独では審査が通らなかったために連帯債務・連帯保証となっているケースが多く、離婚を理由に、金融機関が免責に応じることは殆どありません。
この点を踏まえたうえで、
- 住居をどうするのか
- ローン関係をどう整理するのか
を検討する必要があります。
実務では、「住宅を取得する側が、金融機関と交渉し、相手方を連帯債務・保証から外れるよう努める」という内容を調停条項に盛り込むことがあります。
しかし、金融機関が応じるか否かは金融機関次第ですので、事前に金融機関へ確認を行い、他の保証人を立てるなどした場合に、免責が認められる一定の見通しがある場合に限って入れるのが相当といえます。
住宅ローン付き(特にオーバーローン)の自宅の解決は難易度が高い
住宅ローンが絡む財産分与は、
- 法律
- 金融実務
- 将来の生活設計
が密接に関わり、第三者である金融機関が関係することから話し合いだけでは解決することが出来ません。また、裁判所も金融機関にローンの扱いを強制することは出来ません。
したがって、事案の類型として、住宅ローン(特にオーバーローン)の自宅の処理を伴う財産分与は難易度が高いということを理解しておく必要があります。
自宅と住宅ローンの扱いで悩まれている場合は、早めにご相談ください。
離婚にあたり、夫婦が居住していた自宅不動産を夫名義から妻名義へ変更し、妻が住み続けるというケースは少なくありません。
もっとも、不動産の名義変更は税金との関係が非常に複雑であり、譲渡のタイミング(離婚前か、離婚後か)によって課税関係が大きく変わる点に注意が必要です。
以下では、離婚時に不動産を譲渡する場合に問題となりやすい税金について整理します。
①離婚前の名義変更は「贈与税」が課税される(原則)
婚姻中に、不動産の名義を一方配偶者から他方配偶者へ変更する場合、その多くは税法上「贈与」と扱われます。
夫婦間の譲渡であっても、
✔ 扶養義務の範囲を超える
✔ 実質的に財産の移転と評価される
場合には、贈与税の課税対象となります。
実務上、不動産の価額は基礎控除額(110万円)を大きく超えるため、離婚前に名義変更を行うと贈与税が課税されるケースが多いのではないかと思われます。
②離婚前でも「配偶者控除」により贈与税が非課税となる場合
一定の要件を満たす場合には、夫婦間の不動産贈与について「配偶者控除」を利用でき、2,000万円まで贈与税が非課税となります。
配偶者控除の主な要件
- 婚姻期間が 20年以上
- 居住用不動産、または居住用不動産取得のための金銭の贈与であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに当該不動産に居住し、その後も居住する見込みがあること
この要件を満たせば、基礎控除(110万円)と合わせて最大2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
※ 贈与税が非課税でも、贈与税の申告は必要です。
③配偶者控除が使えても「不動産取得税」は課税される
注意が必要なのは、配偶者控除によって贈与税が非課税になった場合でも、別の税金がかかる点です。
離婚前の贈与による不動産取得では、贈与税は非課税でも不動産取得税は課税されます。
不動産取得税
- 税率:原則4%
- 現在は軽減措置により、土地・居住用家屋は3%
一方で、離婚後に「財産分与」として不動産を取得した場合には、不動産取得税は原則として課税されない、という見解があります。
しかし、不動産取得税は都道府県税ですが、都道府県によっては、『不動産取得税は「不動産の所有権の移転」に着目して課せられる流通税であり、有償無償、登記未登記に関係なく課せられる税金であるとし、清算的財産分与であっても課税の対象となる』として、課税される可能性がありますので、事前に税務相談を受けておくことをお勧めします。
当事務所のある兵庫県は課税しているようですので、必ず当局に事前に確認してください。
④財産分与による名義変更は「離婚後」に行う必要があります
財産分与は、離婚が成立して初めて効力が生じる制度です。
そのため、離婚前に「財産分与」を原因とする所有権移転登記を行うことはできません。離婚前に名義変更をしてしまうと 税務上は「贈与」扱いとなります。
※ 実務上、弁護士でもここを誤解して成立前に「先に登記だけしてしまいましょう」という方が見受けられますが、注意が必要です。
⑤譲渡する側には「譲渡所得税」が課税される場合があります
不動産の価値が、購入時よりも上昇している場合には、譲渡する側に譲渡所得税が課税される可能性があります。
課税譲渡所得の計算
課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
もっとも、
- 居住用不動産の場合
- 財産分与による譲渡である場合
には、
- 3,000万円特別控除
- 所有期間10年超なら軽減税率
が適用される可能性があります。
⑥登録免許税・固定資産税にも注意
登録免許税
贈与でも財産分与でも固定資産税評価額の2%
通常は取得者側が負担します。
固定資産税
毎年1月1日時点の所有者に課税
名義変更した年の固定資産税は、離婚協議で負担割合を定め、後日精算することもあります。
まとめ(重要)
離婚に伴う不動産の名義変更は、
✔ 贈与税
✔ 不動産取得税
✔ 譲渡所得税
✔ 登録免許税
✔ 固定資産税
といった複数の税金が関係し、譲渡のタイミングや方法によって結果が大きく異なります。
本記事は一般的な考え方を示したものであり、
✔ 不動産の評価額
✔ 婚姻期間
✔ 分与の内容・割合
✔ 当局の考え方
によって、税務上の結論が変わることも少なくありません。
実際に不動産の財産分与を行う際には、必ず事前に税理士、税務当局へ相談してください。
⑤将来財産・収入に関する問題
離婚に際し、「将来もらう予定の退職金まで財産分与の対象になるのか」という点は、非常によく問題となります。
結論:退職金も財産分与の対象になります
退職金は、在職期間中の労務提供の対価としての性質を有するため、原則として財産分与の対象となります。
既に受け取っている退職金の場合
離婚時に、すでに退職金を受領している場合には、婚姻期間に対応する部分は、当然に財産分与の対象となります。
婚姻前・別居後の勤務期間に対応する部分は、分与対象から除外して整理します。
まだ受け取っていない退職金(将来の退職金)の場合
受領前の退職金についても、一定の条件のもとで財産分与の対象となります。
実務では、
- 基準時(原則として別居時)において、
- その時点で自己都合退職したと仮定した場合の退職金見込額
を算定し、そのうち婚姻期間に相当する部分を分与対象とするのが一般的です。
つまり、将来もらう金額そのものではなく「別居時点で形成されていたと評価できる退職金部分」を対象にする、という整理です。
実務上の最大の問題点:支払時期
退職金は、実際に支払われるのが離婚後かなり先になることが多い財産です。
そのため、分与額が高額になりやすいにも関わらず、離婚時点では、支払う側に十分な手元資金がないといった理由から、「いつ、どのようにして支払うか」が実務上の大きな問題となります。
分与方法としては、
- 将来の退職金支給時に支払う方法
- 離婚時に他の財産と調整して清算する方法
など、事案に応じた工夫が必要になります。
1.の「将来の退職金支給時に支払う方法」は、退職時期が「近い将来」の場合に用いられることがあります。
退職金の算定資料はどのようにして集めるか
退職金の分与を検討するにあたっては、客観的な算定資料の有無が極めて重要です。
実務では、次のような方法が用いられます。
- 勤務先から「退職金見込額証明書」を取得する
- 就業規則・退職金規程に基づき、見込額を推定する
これらの資料をもとに、分与対象額を検討していくことになります。
⑥財産隠し・争いがあるケース
離婚の財産分与において、「相手には開示されていない財産がまだあるはずだ」と感じることは、決して珍しくありません。
しかし、その主張が裁判所で認められるかどうかは別問題です。
原則:財産の存在は当事者が主張・立証する必要があります
財産分与では、どのような財産が存在し、それが分与対象であるかについて、当事者自身が主張し、資料を提出しなければなりません。
裁判所が職権で「相手の財産を探してくれる」ことはありません。
よくあるが認められにくい主張
調停や訴訟でよく見られるのが、次のような主張です。
- 毎月の収入額と支出額を計算すると、
- これだけの差額が出るのだから無いはずがない
しかし、このような推測や仮定に基づく主張だけでは、裁判所はほとんど考慮しません。
「あるはずだ」「不自然だ」という推測的な指摘だけでは、財産の存在を認定することはできないからです。
裁判所が求めるのは客観性・具体性です
相手に隠し財産があると主張したい場合には、
「どのような種類の財産が」
「どこに」
「どの程度存在すると考えられるのか」
を、できる限り具体的に示す必要があります。
有効な主張・資料の例
次のような事情や資料がある場合、主張の説得力は高まります。
- 過去に存在していた預貯金口座の通帳・取引履歴
- 特定の金融機関を利用していたことを示す資料
- 保険会社・証券会社からの郵送物や通知
- 別居直前の不自然な資金移動
- 第三者名義口座への送金を示す記録
これらをもとに、「この財産が現在も存在している可能性が高い」と具体的に説明することが重要です。
推測だけの主張は逆効果です
証拠の裏付けがないまま、「財産を隠しているはずだ」という主張を繰り返すと、
- 手続の遅延を招いているとみられる
- 他の正当な主張まで軽視される
といった不利益を招くおそれもあります。
隠し財産の主張について
隠し財産の有無は、財産分与の結果を大きく左右する重要なポイントです。
何を、どこまで、どの段階で主張するかをよく検討して臨まなければなりません。当事務所では、
- 隠し財産の疑いがどこまで現実的かの初期判断
- 有効な証拠の整理
- 調停・訴訟を見据えた主張構成
まで含めたサポートを行っています。相手に申告されていない財産があるのではないかと感じた場合は、早めに専門家へご相談ください。
離婚の話し合いでは、慰謝料や財産分与が問題となりますが、支払う側(分与する側)が財産を隠そうとするケースもあります。
財産隠しを許してしまい、相手の財産の「額」や「所在」が分からなくなると、交渉や手続が不利になり、公平な解決が難しくなるおそれがあります。
よくある財産隠しの手法
具体的には、次のような行為が想定されます。
- 自分名義の預金を、相手に知られていない別の金融機関口座へ移す
- 預金を現金化して保管する
- 親族名義口座への送金など、資金の流れを分かりにくくする
疑いがある場合は、感情的に追及するよりも、早めに証拠化・方針決定を行うことが重要です。
事前の「保全」を検討する
財産隠しの可能性が高い場合、状況によっては、裁判所を通じて財産を動かしにくくする手続(保全)を検討します。
①預貯金など金銭を確保したい場合:仮差押え
財産分与として金銭の支払いを求める方針であれば、相手方の預貯金等について、仮差押命令の申立てを検討します。仮差押えにより、相手が当該財産を自由に処分しにくくなります。
ただし、仮差押えには原則として、一定額の担保(保証金)を立てる必要があります。
②不動産を守りたい場合:処分禁止の仮処分
相手名義の不動産を対象として争いがある場合には、処分禁止の仮処分を申し立て、名義移転や売却などの処分行為を抑止することを検討します。
この決定が出た後に相手が第三者へ名義移転したとしても、原則として、移転を受けた側は申立人に対し「自分が所有者だ」と対抗できなくなる(対抗要件を具備しても保全の効力が及ぶ)ため、実質的な保護になります。
もっとも、仮処分の場合も、通常、担保が必要です。
実務上の注意点(保全は強力だが最善とは限りません)
- これらの保全手続は、一般の方が単独で行うのは難しいため、通常は弁護士による対応が前提となります。
- 実務では、費用・担保負担・事案の見通し等の関係で、常に選択されるわけではありません(むしろきわめて例外的です)。
- 保全をかけることで、相手の感情を刺激し、紛争が激化することもあります。
そのため、相手の性格、財産状況、離婚全体の戦略を踏まえて、「やるべきか/やらないか」を慎重に判断する必要があります。
不利になる前に、早めの相談を
財産隠しが疑われる場面では、
- 何を証拠として押さえるか
- いつ、どの手続を選ぶか
- 保全をかけるべきか、交渉で進めるべきか
といった判断が結果を大きく左右します。
当事務所では、財産隠しの兆候がある場合に、証拠の整理、調査方針、保全の要否、調停・訴訟戦略まで一体で検討し、最適な進め方をご提案しています。
財産が動かされそうだと感じたら、できるだけ早い段階でご相談ください。
財産分与の調停や交渉では、当事者からさまざまな主張がなされます。
しかし、その中には感情的には理解できても、法的にはほとんど考慮されない主張も多くあります。
代表的なものは、次のようなケースです。
よくあるが認められにくい主張①
「相手が浪費したせいで財産が残っていない。だから自分が全部取得すべきだ」
この主張は、調停実務において採用されにくいのが実情です。その理由としては、
- 「浪費」といえるかどうかの客観的基準が不明確(生活水準・収入状況・価値観により判断が分かれる)
- 浪費行為の立証が極めて困難
- 夫婦が共同生活を営っていた以上、
- 浪費をやめさせる努力をどこまでしていたか
- 支出を容認・黙認していたのではないか
といった点が問題となり、一方的に責任を帰すことが難しいからです。
単に「使いすぎだった」という評価だけで、財産分与の割合を大きく変えることは、通常は認められません。
よくあるが認められにくい主張②
「相手が不貞行為をしたのだから、財産分与を受ける資格はない」
この点も、財産分与の場面では原則として考慮されません。理由は明確で、
財産分与は「夫婦共有財産の清算」を目的とする制度であり、不貞行為や有責性は、慰謝料の論点として別途判断されるからです。
そのため、相手に離婚原因があり、有責配偶者であったとしても、財産分与を受ける権利自体は原則として否定されません。
実務では、財産分与と慰謝料を混同した主張がなされることが少なくありません。しかし、
-
財産分与:共有財産の清算
-
慰謝料:違法・不法行為に対する損害賠償
というように、制度の目的が全く異なります。この区別を誤ると、
- 調停で主張が整理されない
- 「感情論ばかり」と評価される
- 本来通るべき主張まで弱くなる
といった不利益につながるおそれがあります。
⑦財産分与に応じない場合・手続の流れ
「一刻も早く離婚したいのに、相手が財産分与に応じない」
「財産を全く開示してくれず、話し合いが前に進まない」
このような状況は、実は調停・訴訟の現場では決して珍しくありません。
相手が任意の話し合いに応じない以上、個人同士の交渉で解決しようとするのは限界があります。
話し合いが進まない場合は調停手続に移行します
相手が
- 財産分与に応じない
- 財産内容を開示しない
- 話し合いそのものを拒否している
という場合には、速やかに家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることが現実的な対応となります。
調停手続に入ることで、第三者(調停委員)を介した話し合いが可能となり、手続の中で、財産の開示を正式に求めることができます
「時間稼ぎ」をされ続ける状態から脱するためにも、手続に乗せること自体が重要な意味を持ちます。
調停を申し立てた後は、次のような方法により、相手方の財産情報の把握を目指します。
- 調停の場で、財産目録の提出を求める
- 弁護士を通じて、弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)を行う
- 裁判所を通じて、調査嘱託を申し立て、金融機関等から情報を取得する
これらは、当事者本人だけでは行うことが難しく弁護士の関与が前提となる手続です。
「早く離婚したい」場合こそ、手続きを使うことが近道です
相手が財産分与に応じない状態を放置すると、
- いつまでも話が進まない
- 相手に主導権を握られる
- 精神的な負担が増す
といった状況に陥りがちです。
一方、自分が主導権をもって調停を申し立てることで、相手は「応じざるを得ない立場」に置かれ、結果として、解決が早まるケースも少なくありません。
早期相談が結果を左右します
財産分与に応じない相手への対応では、
- いつ調停に切り替えるか
- どの範囲まで財産開示を求めるか
- どの調査手段を使うか
といった初動の判断が極めて重要です。
当事務所では、
- 話し合い継続が可能かどうかの見極め
- 調停申立てのタイミング判断
- 財産調査を含めた戦略的な進め方
まで含めたサポートを行っています。「相手が応じない」「これ以上待てない」と感じたら、早めにご相談ください。
離婚協議・離婚調停の中で財産分与の話し合いを行い、合意が得られるまで離婚が成立しないことが一般的です。
しかし、早く離婚したいという理由から、財産分与の合意をせずに協議離婚を先に成立させることも可能です。離婚後に財産分与について話し合うことは可能です(但し、2年(法改正後は5年)の期間制限があることには注意)。
離婚後に財産分与の話し合いを行っても解決できない場合、財産分与調停申立を行います。
調停が不成立となれば、審判となります。家庭裁判所は、審判手続で財産分与の要否、分与の額及び方法等を定めます。
審判が金銭の支払い、物の引き渡し、登記義務の履行など給付を命じるものであれば、執行力ある債務名義と同一の効力があり、相手が任意に審判の内容を履行しない場合、強制執行が可能となります。
なお、調停で双方が合意し、合意した内容が調書に記載されると調停が成立します。成立した調停は、確定した審判と同一の効力を有します。
離婚と財産分与の関係
一般的には、離婚協議や離婚調停の中で財産分与の話し合いを行い、合意が成立して初めて離婚が成立するケースが多く見られます。
もっとも、必ずしも離婚と財産分与を同時に解決しなければならないわけではありません。
先に離婚を成立させることも可能です
「一日でも早く離婚したい」という事情から、財産分与については合意せず、先に協議離婚を成立させるという選択をすることも可能です。
この場合でも、離婚後に改めて財産分与について話し合うことは認められています。
ただし、財産分与の請求には期間制限があり、
- 旧法(現在):離婚から 2年以内
- 法改正後:離婚から 5年以内
に請求しなければならない点には注意が必要です。
離婚後に解決できない場合は「財産分与調停」へ
離婚後に当事者間で話し合いをしても、
- 合意に至らない
- 相手が話し合いに応じない
といった場合には、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てます。
調停では、調停委員を介して、
- 財産分与を行うかどうか
- 分与の額
- 分与の方法
について協議を行います。
調停が不成立となった場合は「審判」に移行します
財産分与調停が成立しない場合には、手続は審判に移行します。
審判手続は、話し合いの手続ではなく、家庭裁判所が職権で、
- 財産分与の要否
- 分与額
- 分与方法(支払・引渡し・登記など)
を定めます。
審判・調停の効力
審判で、
- 金銭の支払い
- 物の引渡し
- 登記義務の履行
などの給付義務が命じられた場合、その審判は、確定すれば、強制執行が可能な「執行力のある債務名義」と同一の効力を有します。
相手が審判内容を任意に履行しない場合には、強制執行(差押え等)を行うことが可能です。
また、調停で双方が合意し、その内容が調停調書に記載されて成立した場合、その調停調書は、確定した審判と同一の効力を有します。
どの段階で、どう進めるかが重要です
財産分与については、
- 離婚と同時に解決するべきか
- 先に離婚を成立させるべきか
- 調停・審判まで見据えて進めるべきか
といった判断によって、結果や負担が大きく変わることがあります。
当事務所では、
- 離婚を先行させるべきかどうかの判断
- 財産分与調停・審判の見通し
- 強制執行まで見据えた解決方針
を踏まえ、事案に応じた進め方をご提案しています。
訴訟では「附帯処分」として財産分与を請求します
離婚調停が不成立となり、離婚訴訟に移行した場合、財産分与は、離婚請求に付随する「附帯処分」として請求します。
離婚訴訟においては、
- 離婚の成否
- 親権・養育費
- 財産分与
などを同一の手続の中で判断することになります。
財産分与の請求は「相当額」とすることも多い
財産分与として金銭の支払いを求める場合、具体的な金額を記載するのが原則です。
しかし、訴訟提起の段階で正確な分与額を算定することは、通常困難です。
そのため、請求の趣旨には、「被告は、原告に対し、財産分与として相当額を支払え」といった形で記載しておき、相手から証拠の提出などを受けて検討し、あとから額を確定していくことも実務では行われています。
一方で、
- 特定の預貯金
- 不動産
- 自動車など
具体的な現物の分与を求める場合には、その内容や対象を特定して明確に記載する必要があります。
訴訟(および調停)における検討の基本的流れ
家庭裁判所の実務では、調停段階であっても訴訟段階であっても、財産分与については、概ね次の手順で検討が進められます。
- 基準時(原則として別居時)の確定
- 基準時現在における双方の財産の開示・把握
- 特有財産の有無の確認
- 分与対象財産の評価
- 2分の1ルールを前提とした分与額の算定
- 具体的な分与方法(支払方法・引渡し等)の決定
これらは、形式的に一つずつ進むというよりも、可能であれば同時並行的に検討されるのが実務の実情です。
訴訟段階では主張と証拠が重要になります
訴訟では、
- 財産の存在
- 評価額
- 特有財産性
について、具体的な主張と証拠に基づく立証が求められます(書面の提出の仕方も決まりがあります)。
調停のような柔軟な話し合いは期待しにくく、何をどの順番で主張し、どの証拠を提出するかが、結果に大きく影響します。
訴訟段階では、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。
訴訟を見据えた早期の準備が重要です
離婚訴訟での財産分与は、
- 手続が長期化しやすい
- 専門的な争点が多い
- 結果が生活に大きな影響を与える
という特徴があります。
当事務所では、
- 調停段階から訴訟を見据えた主張整理
- 財産分与に関する証拠収集・提出方針
- 訴訟終結後の強制執行まで含めた対応
を一体的にサポートしています。離婚訴訟で財産分与が争点となっている場合は、早めにご相談ください。
財産分与の結果は、交渉が始まる前の準備段階で、ほぼ方向性が決まるといっても過言ではありません。
とくに重要なのは、次の2点です。
- 相手方配偶者の財産を、漏れなく把握しておくこと
- 自分自身の特有財産を、証拠によって立証できるようにしておくこと
なぜこの2点が重要なのか
財産分与では、
- 相手方配偶者名義の財産が多ければ多いほど、請求できる財産分与額は大きくなり
- 自身の特有財産が多ければ多いほど、相手に分与しなければならない金額は小さくなります
つまり、「相手の財産をどこまで把握できるか」と「自分の財産をどこまで守れるか」が交渉力を左右します。
同居中だからこそできる「財産把握」
将来的に離婚を検討している場合、同居している間にしか確認できない情報が数多くあります。
可能であれば、次のような対応を検討しましょう。
- 相手方配偶者の収入資料(源泉徴収票・給与明細)の確認・コピー・撮影
- 預貯金・保険・証券会社等からの郵便物の確認
- 利用している金融機関・保険会社の名称の把握
※ 無断で持ち出す、違法な方法で取得することは避け、あくまで適法かつ現実的な範囲での情報整理が重要です。
見落とされやすい財産の代表例
財産分与で見落とされやすいものとして、次のような財産があります。
- 生命保険・学資保険・外貨建保険
- 財形貯蓄・小規模企業共済
- ネット銀行・ネット証券の口座残高
- 暗号資産(仮想通貨)
- 配偶者が経営する会社の株式・出資持分
「手元に資料がないから存在しない」と判断するのは危険です。
通帳・給与明細は「最低1年分」を確認したい
預貯金の動きや収入の実態、見落とし財産の有無を把握するため、
- 通帳
- インターネットバンキングの取引履歴
- 給与明細
については、少なくとも過去1年分を確認し、不自然な入出金や見落としがないかをチェックしておきましょう。
「手がかり」があれば、後に調査が可能です
残高や具体的な内容が分からなくても、
- 「どの銀行に口座があるか」
- 「どの保険会社と契約しているか」
といった手がかりさえ分かれば、調停・訴訟の中で、裁判所の調査嘱託などにより調査できる場合があります。
逆に、金融機関名すら分からない状態では、弁護士であっても調査は極めて困難です。
特有財産の立証は「時間との勝負」
特有財産を守るためには、証拠が不可欠です。
- 婚姻前の預金残高との紐づけができるか
- 贈与・相続を受けた際の資料(契約書、申告書、振込記録等)が残っているか
を早めに確認しましょう。
特に、婚姻期間が長いほど、資料の再取得は難しくなります。金融機関の取引履歴の保存期間は、一般に10年程度といわれており、時間が経つほど立証が困難になります。
重要な原則:特有財産の立証責任はあなたにあります
特有財産については、「特有財産であると主張する側が、立証責任を負う」
という原則があります。
証拠がない場合、相手が任意に認めない限り、その財産は夫婦共有財産と推定されてしまいます。
交渉が始まる前の準備が結果を左右します
財産分与の交渉は、「話し合いが始まってから考える」ものではありません。
- 何を把握しているか
- 何を証明できるか
で、結果は大きく変わります。
当事務所では、交渉前の情報整理、見落としやすい財産の洗い出し、特有財産の立証方針の検討まで含めてサポートしています。ご不安な方は早い段階でご相談ください。
⑧期限・税金・特殊な分与
財産分与は、いつまでも請求できる権利ではありません。
法律で定められた期間内に手続きを行わなければ、請求自体ができなくなります。
財産分与の調停・審判は、離婚が成立してから一定期間を経過すると、申し立てることができなくなります。
この期間は「除斥期間」と解されており、次のような特徴があります。
期間を過ぎると、権利そのものが消滅する
裁判外で請求(話し合い・内容証明の送付など)をしていても、期間は止まらない
そのため、「話し合いはしていた」「請求する意思は伝えていた」という事情があっても、期限を過ぎてしまえば、法的手段は取れなくなります。
離婚時に財産分与を先送りする場合の注意点
「とにかく早く離婚したい」という理由で、財産分与の話し合いを後回しにして協議離婚を成立させるケースも少なくありません。
しかし、この場合、請求期限を意識せずに放置してしまうと、取り返しがつかない結果になることがあります。
法改正による期間変更
令和6年(2024年)の法改正により、財産分与の請求期限は、従来の「2年」から「5年」へ延長されることとなりました。
改正法施行日以降に適用されるケースでは、離婚から5年以内が請求期限となります。
離婚に伴う財産分与では、「税金はかかるのか」という点について不安を抱かれる方が少なくありません。
財産分与によって財産を取得した場合、原則として贈与税は課税されません。
これは、財産分与が、夫婦が婚姻中に共同で形成した実質的共有財産を清算する行為にすぎないと考えられているためです。
例外①:分与額が「過当」と判断される場合
もっとも、財産分与であっても、
- 分与額が明らかに多すぎる
- 実質的に一方配偶者へ財産を移転する趣旨と評価される
といった場合には、過当と認められた部分について、贈与税が課税される可能性があります。
財産分与という名目であれば、どのような配分でも非課税になるわけではありません。
例外②:節税目的の離婚と判断される場合
また、形式上は離婚に伴う財産分与であっても、贈与税や相続税を免れる目的で離婚を手段として利用したと認められるような場合には、贈与税が課税されることがあります。
実質を重視して課税判断がなされる点には注意が必要です。
分与する側にも税金の問題があります(譲渡所得税)
財産分与で見落とされがちなのが、財産を「渡す側」への課税です。
財産分与として、
- 不動産
- 有価証券
- 高額な資産(金)
などを譲渡した場合には、譲渡所得税が課される可能性があります。
- 取得時の価額はいくらだったのか
- 現在の評価額はいくらか
- 差額(譲渡益)が生じているか
といった点を事前に検討せずに離婚を成立させてしまうと、離婚後に想定外の課税を受けることになりかねません。
税務面も含めた事前検討が不可欠です
財産分与では、分与の「内容」だけでなく、その「方法」や「税務上の影響」まで含めて検討することが重要です。
財産分与には、これまで述べてきた清算的財産分与のほかに、いわゆる「扶養的財産分与」と呼ばれる考え方があります。
実務上、離婚後の生活不安を理由に、この扶養的財産分与を求める主張がなされることがあります。
原則:扶養的財産分与は認められません
離婚が成立すると、夫婦間の相互扶養義務は終了します。
そのため、財産分与として離婚後の生活費を恒常的に支えることを予定する「扶養的財産分与」は、制度の趣旨からして原則として認められません。
財産分与はあくまで、婚姻期間中に形成された共有財産を清算する制度であり、離婚後の扶養を目的とするものではないからです。
例外的に認められるのは「極めて例外的な場合」に限られます
実務上、扶養的財産分与が認められるのは、これを認めなければ公平・信義に著しく反すると評価される、極めて限定的なケースです。
具体的には、次のような事情が重なった場合が典型例です。
- 一方配偶者が
- 高齢である
- 病気や障がいを有している
- 就労が著しく困難である
- 他方配偶者には、
- 今後も安定した高収入が見込まれる
といった事情が認められる場合です。
清算的財産分与がある場合は、扶養的分与は否定されがちです
もっとも、上記のような事情がある場合でも、一定額の清算的財産分与が認められるのであれば、その給付をもって最低限度の生活は維持できると評価されることが多く、追加で扶養的財産分与まで認められるケースは稀です。
単に、「離婚後の生活が不安である」「収入が少ない」といった理由だけでは、審判や判決で扶養的財産分与が認められる可能性は、ほとんどないと考えられます。
支払方法について
仮に扶養的財産分与が認められる場合には、原則として一括払いとされます。
もっとも、支払額が高額で一括払いが現実的でない場合には、例外的に一定期間の定期金払い(分割払い)が命じられることもあります。
扶養的財産分与に過度な期待を持たないことが大切です
扶養的財産分与は存在はするものの、実務では極めて限定的にしか認められない制度です。
清算的財産分与、婚姻費用、年金分割、生活再建のための制度などを総合的に組み合わせて考えることが現実的な対応といえます。
内縁とは何か
内縁とは、
「婚姻届は提出していないものの、当事者双方に夫婦として生活する意思があり、社会通念上、婚姻関係と同視できる共同生活を継続している男女関係」をいいます。
単なる同居や交際関係とは異なり、
- 生活費を分担している
- 夫婦同様の生活実態がある
といった事情が必要になります。
結論:内縁関係の解消でも財産分与は可能です
財産分与を定める民法768条は、形式的には法律上の婚姻関係にある夫婦を対象としています。
しかし、実務では、内縁関係の解消に際しても、同条が類推適用され、財産分与が認められています。
そのため、
- 内縁関係の期間中
- 両当事者の協力によって形成された財産
が存在する場合には、法律婚と同様に、財産分与を請求することが可能です。
財産分与の対象となるのは「協力して形成した財産」
内縁関係においても、
- 一方の収入だけで名義上取得した財産であっても
- 他方が家事・育児・生活面で協力していた
と評価できる場合には、実質的な共有財産として分与の対象となります。
相続との違いに注意してください
ここで注意すべきなのは、内縁関係と相続は全く別の問題である点です。
内縁関係が解消された場合には、財産分与が認められる余地がありますが、内縁配偶者には、法律上の相続権は認められていません。
この点を混同すると、重大な誤解につながります。
死亡に備えるには生前対策が不可欠です
内縁の相手が死亡した場合、
- 法定相続人にはならない
- 財産を当然に取得できない
というリスクがあります。
そのため、内縁関係にある場合には、
- 生前贈与
- 遺言による遺贈
- 保険の受取人指定
など、生前のうちに明確な対策を講じておくことが極めて重要です。
法律相談のお申込みはこちら
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日