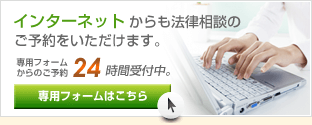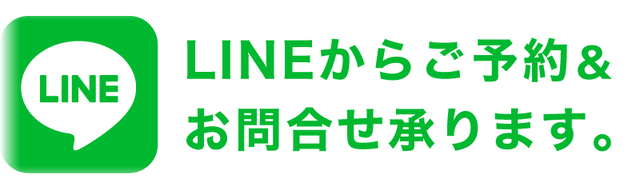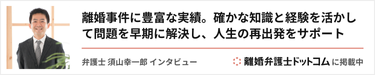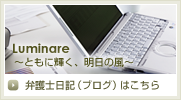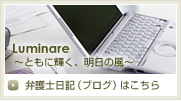弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。

突然、子どもと引き離されてしまった。別居をきっかけに、子どもを連れて行かれたまま会わせてもらえない。
「このままでは二度と子どもに会えなくなるのではないか」
「親権を失ってしまうのではないか」
そのような強い不安を抱えながら、このページをご覧になっている方もいらっしゃると思います。
子の監護者指定、子の引渡し、審判前の保全処分は、別居後に子どもを巡って深刻な対立が生じている場合に、家庭裁判所が関与し、子どもの生活と福祉を守るために用意された手続です。
もっとも、これらの手続は、「子どもを連れて行かれたから必ず認められる」「申し立てた方が常に有利になる」といった単純なものではありません。
家庭裁判所では、別居に至った経緯、これまでの監護状況、子どもの生活環境や心身への影響などを踏まえ、子どもにとって最も適切な状態は何かという観点から、慎重に判断がなされます。
そのため、子どもを連れて別居された側の方はもちろん、相手方からこれらの申立てを受けた場合であっても、状況に応じた適切な対応を早期に取ることが極めて重要です。
このページでは、子の監護者指定・子の引渡し・審判前の保全処分とは何か、どのような場合に問題となるのか、そして、弁護士に相談するタイミングについて、神戸の弁護士の立場から分かりやすく解説していきます。
子の監護者指定や子の引渡し、審判前の保全処分は、すべての別居や親子間トラブルで必要となるわけではありません。
しかし、別居後に次のような状況が生じている場合には、早期に裁判所の判断を求める必要が出てくることがあります。
- 別居後、子どもとまったく会わせてもらえない状態が続いている
- 子どもの生活環境が急激に変わっている
- 保育園や学校にも行っていない様子だ
- 時間の経過によって既成事実が積み重なりつつある
このような場合には、通常の調停や審判の結論を待っていては、子どもの生活や親子関係に重大な影響が生じるおそれがあります。
そこで問題となるのが、本案の審判に先立って、暫定的な判断を求める「審判前の保全処分」という手続です。
以下では、審判前の保全処分の仕組みや要件について、実務上のポイントを踏まえてご説明します。
別居後、相手方が一方的に子どもを連れて行き、会わせてもらえない状態が続いている場合、できるだけ早く子どもの引渡しを求める必要が生じることがあります。
このような場合に検討されるのが、家庭裁判所に対して申し立てる「審判前の保全処分」という手続です。
審判前の保全処分とは、子の監護者指定や子の引渡しといった本来の審判(本案)に先立ち、当面の間の取扱いについて、裁判所に暫定的な判断を求めるための制度です。
単に「子どもを返してほしい」という気持ちだけでは足りず、なぜ今すぐ裁判所の判断が必要なのかを、法的な観点から説明しなければなりません。
誰が申し立てることができるのか
この手続を申し立てることができるのは、原則として子どもの父母です。
理論上は祖父母も申立権者に含まれるとされていますが、実務上は、父または母のいずれかが申立人となるケースがほとんどです。
申立ての前提条件
審判前の保全処分を申し立てるためには、子の監護者指定や子の引渡しについて、すでに家庭裁判所で調停や審判が係属している必要があります。
そのため、多くの場合は、本案となる審判の申立てと同時に、審判前の保全処分を申し立てることになります。
裁判所に示すべきポイント
申立書には、「どのような仮の判断を求めるのか」「なぜそれが必要なのか」を具体的に記載します。
特に重要なのは次の2点です。
- 本来の審判で認められる可能性が高いこと
- 今すぐ判断してもらわなければならない事情があること
これらについて、客観的な資料を基に裁判所へ説明する必要があります。
保全処分が認められた場合の注意点
審判前の保全処分が認められた場合、直ちに子どもの引渡しを求めるための手続を取ることができます。
ただし、この手続には厳格な期限があり、決定を受け取ってから短期間のうちに対応を完了させる必要があります。
対応が遅れると、せっかくの決定を活かせなくなるおそれもあるため、迅速かつ慎重な対応が求められます。
弁護士への依頼について
審判前の保全処分は、高度に専門的な判断と迅速な対応が求められる手続です。
申立ての内容や対応方法を誤ると、かえって不利な状況を招くおそれもあります。
実務上は、弁護士に依頼せずにこの手続を適切に進めることは容易ではありません。
子どもを巡る問題は、時間の経過がそのまま結果に影響する分野です。
審判前の保全処分は、
「後から何とかすればよい」
「様子を見てから動けばよい」
という性質の手続ではありません。
対応の遅れや、初動での判断ミスによって、その後の調停・審判で不利な状況が固定してしまうことも少なくありません。
現在の状況が、
- そもそも審判前の保全処分の対象となるのか
- どのような主張や資料が必要になるのか
- 今、取るべき行動は何か
については、事案ごとの判断が不可欠です。
一人で判断せず、できるだけ早い段階で子の監護問題に精通した弁護士へご相談ください。
なぜ初動対応が重要なのか
子の監護者指定や子の引渡しをめぐる問題では、「どちらが正しいか」よりも、「これまでどのような状況が積み重なっているか」が重視される傾向があります。
別居後の対応を誤ると、実際の事情とは異なる形で「これが安定した生活環境である」と評価されてしまうおそれがあります。
特に注意が必要なのは、
- 子と会えていない期間が長くなる
- 監護実績が一方に固定される
- 不利な主張や事実関係が既成事実化する
といった点です。
これらは、後になって説明を尽くしても、簡単には覆すことができません。
そのため、感情的に行動してしまう前に、どの事実を、どのような形で整理し、どのタイミングで裁判所に示すべきかを、専門的な視点から検討することが重要になります。
子どもを連れて別居した側の事情や、相手方から申立てを受けた立場であっても、状況に応じた適切な主張や対応は異なります。
いずれの立場であっても、早い段階で法的な整理を行うことが、不要な不利益を避けるための重要なポイントとなります。
親権との関係についても知っておく必要があります
子の監護者指定や子の引渡しの問題は、将来の親権の判断と無関係ではありません。
もっとも、
「今回の手続で親権がすぐに決まる」
「引渡しが認められれば必ず親権が取れる」
といったものではなく、親権の判断は、別の視点と基準に基づいて行われます。
親権がどのような考え方で判断されるのかを理解しておくことは、現在の対応方針を誤らないためにも重要です。
親権の判断基準や考え方については、こちらの解説もあわせてご覧ください。
離婚調停や審判との関係
子の監護者指定や子の引渡しについては、離婚調停や離婚審判と並行して問題となることが少なくありません。
実際には、
- どの手続を先に進めるべきか
- 同時に進めた場合の影響
- 調停と審判の役割の違い
といった点を整理しないまま動いてしまい、結果的に不利な状況を招いてしまうケースも見受けられます。
離婚調停の基本的な流れや注意点を把握しておくことで、現在の対応をより冷静に判断することが可能になります。
離婚調停の進め方や注意点については、こちらで詳しく解説しています。
審判前の保全処分を申し立てるためには、「本案が認められる可能性が高いこと」を裁判所に示す必要があります。
これを「本案が認容される蓋然性を疎明する」といいます。
ここでいう「本案」とは、子の監護者指定や子の引渡しについて、最終的に判断される審判のことを指します。
つまり、将来行われる本案の審判において、申立人が子の監護者として相当であり、子の引渡しが認められる可能性が高いかどうかがまず検討されることになります。
裁判所が総合的に考慮する事情
本案でどのような判断がなされるかについては、一つの要素だけで決まるわけではありません。
裁判所は、次のような事情を総合的に考慮しながら、子どもにとって最も望ましい状態は何かを判断します。
・これまで、どちらの親が主に子どもを監護してきたか
・現在、どのような環境で子どもが生活しているか
・祖父母など、監護を補助する人の関与や監護能力
・子どもの年齢や、意思を確認できる場合はその内容
・子どもの心身の状態や健康上の配慮の必要性
・現在の生活環境にどの程度適応しているか
・子どもと、それぞれの親との関係性
・通学や通院(持病や治療の必要がある場合など)への影響
・現在の状況に至るまでの具体的な経過
これらの事情を踏まえ、本案の審判においてどのような結論になる可能性が高いかが判断されることになります。
実務上、特に重視されるポイント
実務上は、これらの事情の中でも、裁判所が特に注意深く確認していると考えられる点があります。
とりわけ、別居に至った経緯や、子を連れて移動した際の状況については、やむを得ない事情があったのか、一方的な行動と評価されるのかといった点が慎重に検討されます。
審判前の保全処分では、本案が認められる可能性が高いことに加えて、「保全の必要性」があることも示さなければなりません。
法律では、「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するために必要がある場合」に保全処分が認められるとされています(家事事件手続法157条1項3号)。
保全の必要性が認められやすいとされるケース
具体的には、次のような事情がある場合に保全の必要性が認められることがあります。
-
現在子を監護している親による虐待や、子の生活に重大な危険が及んでいると認められる場合
-
現在の生活環境が原因で、子どもが著しく情緒不安定になっている場合
-
別居後に一方の親のもとで生活していた子どもを、他方の親が実力行使によって連れ去ったと評価される場合
子に切迫した危険が迫っているとか、子の監護開始の経緯に悪質性がある場合などに、保全の必要性が肯定されやすい傾向があります。
保全の必要性が厳格に判断される理由
子の仮の引渡しを命じる保全処分が認められた場合、本案の結論を待たずに、直ちに子の引渡しを求める強制執行を行うことが可能となります。
しかし、強制執行は、子どもに大きな心理的・身体的負担を与える可能性が高い手続です。
その後、本案や即時抗告審で判断が変わるたびに、強制執行が繰り返されるような事態は、極力避けなければならないと考えられています。
このような理由から、実務上、保全の必要性については極めて慎重に判断されており、単に「主たる監護者の承諾なく子を連れて行った」という事情だけでは、保全処分が認められない可能性も高いといえます。
審判前の保全処分は、その性質上、非常に迅速な審理が行われることが特徴です。
申立書を提出すると、比較的早い時期に審判期日が指定され、双方が裁判所に出席した上で、裁判官による事実確認や争点整理が行われます。
調査官の関与について
この審理には、家庭裁判所調査官が関与することが通常です。
事件の内容に応じて、緊急性の有無や、調査の時期や方法について検討されます。
子どもの意思の確認
子どもが15歳以上の場合には、原則として、子どもの意思を聴取することとされています。
もっとも、15歳以上の場合は、子ども自身の意思によって居所が定まっていることも多く、実務上、必ずしも多いケースではありません。
申立て後に求められる対応
審判前の保全処分を申し立てると、短期間のうちに裁判所へ出向く必要が生じます。
調査官調査が行われる場合には、日程の調整や資料の準備などについて、柔軟かつ迅速な対応が求められます。
弁護士に依頼している場合には、これらの期日や審問に同席してもらうことができ、適切な主張や対応をその場で行うことが可能になります。
保全処分と本案の関係
裁判所は、保全処分と本案の判断が異なることによって、子どもが両親の間を行き来する事態を避けるべきだと考えています。
そのため、審判前の保全処分という名称ではあるものの、実際には保全処分として先行判断がなされず、本案の審判と同時に判断がなされるケースも少なくありません。
いずれにしても、審判前の保全処分は、子どもに与える影響を十分に考慮した上で、迅速を旨としながら、慎重に判断される手続であるといえます。
子の監護者指定や子の引渡しについては、最終的には「本案の審判」において判断がなされます。
本案審判とは、一時的・暫定的な判断である審判前の保全処分とは異なり、子の監護の在り方について、家庭裁判所が最終的な判断を下す手続です。
そのため、仮に審判前の保全処分が申し立てられている場合であっても、裁判所は、常に本案でどのような結論が相当かを見据えながら、審理を進めることになります。
保全処分と本案審判の関係
審判前の保全処分は、あくまで緊急的・暫定的な措置であり、本案の判断に優先するものではありません。
裁判所は、保全処分と本案の結論が食い違うことにより、子どもが短期間で生活環境を繰り返し変えられる事態をできる限り避けるべきであると考えています。
そのため、実務上は、審判前の保全処分として先に結論を出さず、本案の審判と同時に判断がなされることも少なくありません。
本案審判で裁判所が判断する視点
子の監護者指定・子の引渡しの本案審判では、裁判所は、子どもにとってどのような監護状況が最も望ましいかという観点から、総合的に判断を行います。
審判前の保全処分と同様、形式的な権利関係ではなく、子どもの生活実態や将来への影響が重視されます。
【本案で考慮される主な事情】
これまで、どちらの親が主として子どもを監護してきたか
現在の監護状況と、その安定性
子どもの年齢、意思(判断能力がある場合)
心身の健康状態、治療や特別な配慮の必要性
子どもと、それぞれの親との関係性
通学・通院を含む生活環境との適合性
別居に至った経緯や、子の移動がどのように行われたか
これらを踏まえ、将来にわたって子どもの生活と福祉が最も確保されるのはどの監護体制かが検討されます。
本案では「時間の経過」が大きく影響します
本案審判において特に注意が必要なのは、時間の経過が、そのまま評価に影響する点です。
別居後の監護状況が一定期間継続すると、それが「現に安定した生活環境」と評価される可能性があります。
その結果、現状を前提とした判断がなされるおそれもあります。
調査官調査の重要性
本案審判では、家庭裁判所調査官による調査が行われることが一般的です。
調査官は、子どもの生活状況や関係者の状況について調査を行い、その結果を裁判官に報告します。この調査結果は、裁判官の判断に大きな影響を与えることが少なくありません。
そのため、調査官調査への対応や説明の仕方は、本案審判において極めて重要な意味を持ちます。
本案審判は「やり直し」が難しい手続です
子の監護者指定や子の引渡しの本案審判では、一度示された判断が、その後の手続や親権判断に影響を及ぼすこともあります。
判断が不利であれば後の親権争いで逆転することも可能、という性質の手続ではありません。
そのため、まずそもそも、この類型の申立てを行うのか、申立て
を行ったとして、どの事実を、どのような形で裁判所に示すのか、どのタイミングで主張・立証を行うのかについて、早い段階から慎重な検討が求められます。
弁護士に相談すべき理由
本案審判では、前の保全処分と同様に、法的な評価と実務の運用を踏まえた対応が不可欠です。
特に、
・どの事実を重視すべきか
・どの点が不利に評価される可能性があるか
・保全処分との関係をどう整理するか
といった点については、事案ごとに検討が必要です。
子の監護者指定、子の引渡し、審判前の保全処分といった事件は、離婚事件の中でも特に専門性が高く、実務経験が求められる分野です。
実際にご相談を受けていると、「何人もの弁護士に相談したが、対応できないと言われた」「忙しいので引き受けられないと断られた」といったお声を耳にすることも少なくありません。
なぜ引き受けてもらえないことがあるのか
この類型の事件を受けてくれる弁護士を見つけにくい理由としては、いくつかの事情が挙げられます。
まず、審判前の保全処分は、通常の離婚調停や審判と異なり、極めて短期間での対応が求められます。
申立書の準備、疎明資料の整理、裁判所とのやり取りや期日対応などを、限られた時間の中で集中的に行う必要があります。
そのため、日常的に多くの案件を抱えている弁護士にとっては、時間的な制約から受任が難しい場合があります。
経験を有する弁護士が多くない理由
また、この分野は事件数そのものが多いとはいえず、弁護士であっても実際に経験する機会が限られています。
特に、審判前の保全処分まで含めて実際に申立てを行い、裁判所対応をした経験がある弁護士は、決して多くありません。
書籍や研修で制度の知識を得ることと、実際の事案で迅速に判断し、対応することとの間には、大きな差があります。
この手続では、裁判所がどの点を重視し、どのような資料や説明が必要とされるのかといった実務感覚が結果に影響することも少なくありません。
弁護士選びが結果に影響する分野です
このような事情から、子の監護をめぐる緊急性の高い事件では、弁護士選びそのものが、その後の手続や結果に大きく影響する可能性があります。
すべての弁護士が対応できる分野ではないからこそ、これまでに同種の事件を取り扱った経験があるか、迅速な対応が可能な体制が整っているかといった点を、事前に確認することが重要になります。
もちろん、どの弁護士に相談しても誠実に対応してもらえないということではありません。
ただ、この分野に限っては、一般的な離婚事件とは異なる視点や判断が必要となる場面が多く、経験の有無によって対応の差が生じやすいという側面があります。
なお、時間的余裕があれば受任することができても、多忙なため、ご相談の時点ではどうしても引き受けることができない、といった弁護士も多いのではないかと思われます。
この手続は親権争いの前哨戦に過ぎないという現実
子の監護者指定や子の引渡し、審判前の保全処分は、別居後の混乱した状況を整理するための重要な手続です。
しかし、実務上、この類型の事件は最終的な解決ではなく、後に行われる離婚調停や離婚訴訟における親権争いの「前段階」に位置付けられることがほとんどです。
最終的なゴールは、子どもの将来にわたる監護体制を定める「親権の帰属」にあります。
この類型での判断は、親権判断に影響することがあります
子の監護者指定や子の引渡しの審判は、形式的には親権を決める手続ではありません。
もっとも、この段階で示された裁判所の判断や評価が、その後の離婚調停・離婚訴訟における親権判断に影響を及ぼす可能性は否定できません。
例えば、
・どちらの親が子を安定的に監護していると評価されたか
・別居後の対応がどのように受け止められたか
・子の生活環境に問題があると認められたか否か
といった点は、親権判断においても同様に検討される要素です。
そのため、この類型の事件で不利な判断が示された場合、親権争いにおいても厳しい見通しとなる可能性があります。
だからこそ、戦い方の選択が重要になります
子の監護をめぐる問題に直面した際、「とにかく子の引渡しを求めたい」「今すぐ裁判所に動いてほしい」という気持ちになるのは自然なことです。
しかし、すべてのケースにおいて、審判前の保全処分や本案の申立てを行うことが最善の選択肢になるとは限りません。
親権獲得を最終目標とした場合の別の選択肢
事案によっては、弁護士費用や時間をかけて子の監護者指定・子の引渡しを争うよりも、
・離婚調停・離婚訴訟における親権争いに注力する
・別居後の監護実績を丁寧に積み重ねる
・調査官調査を見据えた対応を優先する
といった戦略を取る方が、結果として親権獲得の可能性を高める場合もあります。
特に、現時点での状況を客観的に見た場合、この類型の事件で勝つことが難しいと見込まれる場合には、無理に申立てを行うことが、かえって不利な評価を固定してしまうおそれもあります。
重要なのは「今勝つこと」ではなく、「最終的にどうするか」
子の監護をめぐる紛争では、一つ一つの手続が独立しているように見えても、実際にはすべてが連続しています。
短期的な結果を追うあまり、最終的な親権判断に不利な状況を作ってしまっては、本来の目的を達成することができません。
だからこそ、現在の状況だけで判断するのではなく、親権獲得を最終目標とした場合に、どの手続に、いつ、どの程度の力を注ぐべきかを、全体像の中で検討することが重要になります。
弁護士に相談する意義は「戦略」を考えることにあります
この類型の事件において、弁護士に相談する最大の意義は、単に手続を進めることではありません。
現在の状況を踏まえ、
・今、申し立てるべきかどうか
・この手続が親権争いにどのような影響を及ぼすか
・別の選択肢を取るべきか
といった点について、専門的な視点から戦略を検討することにあります。
ご相談の結果として、「現時点では申立てを行わない」「親権争いに向けた準備を優先する」という判断に至ることも、決して珍しくありません。
まとめ
子の監護者指定・子の引渡しは、親権争いに向けた重要な局面である一方で、それ自体が最終目的ではありません。
どの手続に、どのタイミングで注力すべきかは、事案ごとに大きく異なります。
現在の状況が、親権獲得という最終目標にとってどのような意味を持つのかについて、一度専門的な視点で整理してみることが重要です。
別居に際して子を連れて出た結果、配偶者から、子の監護者指定や子の引渡し、審判前の保全処分を申し立てられることがあります。
このような場合、
「子を連れて別居したこと自体が間違いだったのではないか」
「この申立てで、一気に不利になってしまうのではないか」
と強い不安を感じられる方も少なくありません。
もっとも、子を連れて別居したという事情だけで、直ちに違法であるとか、必ず不利な判断がなされるわけではありません。
裁判所がまず確認する点
裁判所は、申立てを受けた側についても、感情や形式ではなく、具体的な経過と子どもの状況を重視して判断します。
例えば、
・なぜ別居の際に子を連れて出る必要があったのか
・別居前、実際にどのような形で子を監護していたのか
・別居後、子どもの生活や心身に問題が生じていないか
・現在の監護状況が、子どもにとって安定しているか
といった点が、個別に検討されます。
そのため、「連れて出た側である」という一点のみで、結論が決まることはありません。
申立てを受けた立場で特に注意すべきこと
一方で、申立てを受けた側である場合には、初動の対応を誤ると、その後の手続に不利な影響が及ぶ可能性があります。
具体的には、
・申立ての趣旨や理由を正確に理解しないまま対応してしまう
・感情的な反論に終始してしまう
・調査官調査の位置づけを軽く考えてしまう
といった対応は、裁判所に対する説明として十分でないと評価されかねません。
また、現状を正当化することに意識が向きすぎると、「子どもにとってどうか」という本来の判断軸から主張がずれてしまうこともあります。
本案・親権判断への影響を見据える必要性
子の監護者指定や子の引渡しは、形式上は親権を決める手続ではありません。
しかし、この段階での裁判所の評価や、別居後の監護状況の整理のされ方が、後の離婚調停や離婚訴訟における親権判断に影響を及ぼす可能性があることは否定できません。
申立てを受けた側であっても、
「今回は防御できればよい」
「ひとまず現状を維持できればよい」
と考えるだけでは十分ではなく、最終的な親権争いを見据えた対応が求められる場面があります。
専門的な整理が特に重要となる立場です
子を連れて別居した側が申立てを受けた場合には、「不利ではない」と一般論で片付けることも、「もう勝てない」と悲観することも、いずれも適切ではありません。
現在の状況が、裁判所にどのように評価され得るのか、本案や親権争いにどのようにつながっていくのかを、早い段階で専門的に整理することが重要です。
子の監護者指定や子の引渡し(保全・本案)は、対応の遅れや初動の判断が、その後の手続や結論に大きな影響を与える分野です。
限られた時間の中で、法令が定める要件を踏まえつつ、実務の運用や裁判所の判断傾向を考慮した主張を行い、適切な資料を整理・提出していく必要があります。
また、家庭裁判所調査官による調査への対応も、結果を左右する重要なポイントとなります。
当事務所では、子を現在監護している側の立場、子どもを連れて別居された側の立場、いずれについても代理人として対応してきた経験があります。
それぞれの立場に固有の注意点やリスクを踏まえたうえで、事案の状況に応じた最適な対応を行うことを重視しています。
なお、本類型の事件は、短期間で集中的な対応が必要となるため、当事務所の受任状況によっては、すぐにお引き受けすることができない場合があります。
その場合であっても、現在の状況を整理した上で、取るべき対応についてのご説明や、今後の見通しに関する助言は可能ですので、まずは一度ご相談ください。
|
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 子の監護者指定・子の引き渡し(本案) | 330,000円 | 330,000円 |
| 子の監護者指定・子の引き渡し(保全) | 330,000円 | 330,000円 |
※消費税込
※保全、本案の両方のご依頼が必要になることがほとんどです。
※申立人側のご依頼、相手方側のご依頼のいずれもお受けしております。
法律相談のお申込みはこちら
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日