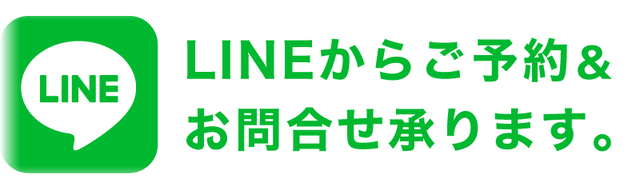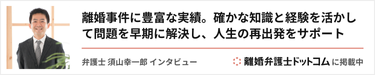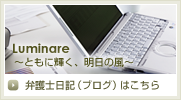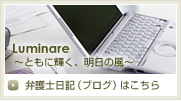弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
遺留分の基礎知識
遺留分は、相続人に最低限確保されている相続分ですが、実際の算定は複雑で難易度が高くなることが多いのが実情です。
弁護士に依頼して対応するにしても、以下を読んで最低限の基礎知識は身に着けておくとよいでしょう。
遺留分権利者全体に残されるべき遺留分の割合については以下のとおりです。
①相続人が配偶者及び子→被相続人の財産の2分の1
②相続人が子のみ→被相続人の財産のの2分の1
③相続人が配偶者のみ→被相続人の財産の2分の1
④相続人が配偶者及び直系尊属→被相続人の財産の2分の1
⑤相続人が直系尊属のみ→被相続人の財産のの3分の1
【具体例(相続人が配偶者及び子一人の場合)】
それぞれの法定相続分は、配偶者:2分の1 子:2分の1
遺留分は被相続人の財産の2分の1ですから、
配偶者の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
子 の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1 となります。
このような場合に、被相続人が、全ての財産を第三者に遺贈するとしたような場合、配偶者及び子は、相続財産の4分の1の範囲で当該第三者に対し、遺留分減殺請求権を行使することができることになります。
遺留分額の算定の基礎となる財産
=被相続人が相続開始時に有していた財産(遺贈財産を含む)の価額
+相続人に対する贈与の価額(相続開始前10年以内にしたもの)
+第三者に対する贈与の額(相続開始前1年以内にしたもの)
-相続債務の額
贈与を算入するのは、これを加算しないと、被相続人が死亡直前に財産の大半を贈与していたような場合に、遺留分制度の目的が達成できないからです。
相続開始前1年以内の贈与は、遺留分算定の基礎財産に加えます。
但し、当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りつつ行った贈与は、1年前より過去にされたものであっても遺留分算定の基礎財産に算入します。
「損害を加えることを知って」とは、遺留分を侵害する認識があればよく、加害意図は不要です。
相続人に対する贈与は、特別受益としての贈与(相続人が結婚や養子縁組のため又は生計の資本として贈与を受けた場合等)に該当し、かつ相続開始前の10年以内にされたものは遺留分算定の基礎財産に加えます。
また、持戻し免除の意思表示がある場合でも算入します。
被相続人が、特別受益に当たる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入されるものと解される(最判平成24年1月26日)。
保険金の受取人の変更は、民法1031条に定める遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるということもできない(最判平成14年11月5日)とされており、加算しません。
控除する債務は、借金などの私法上の債務のほか、税金・罰金などの公法上の債務を含みます。
保証債務は、主たる債務者が無資力で求償権の行使による填補の実効性がない場合に限り、被相続人の財産から控除すれば足りるとする下級審裁判例があります(東京高判平成8年11月7日)。
以下のようなケースの場合、遺留分算定の基礎となる財産は幾らになるでしょうか。
【ケース例】
被相続人(甲)が死亡。相続人は3人の子(A、B、C)。甲は、全財産をAに相続させる旨の遺言を作成していた。
甲の相続財産は、預貯金3400万円、株式(相続開始時の時価1200万円、現在の時価2000万円)。事業債務として600万円を負担していた。
その他、甲は、死亡する7年前にBに生計の資として200万円を生前贈与していた他、死亡する3年前に愛人Xに100万円を生前贈与していた。
遺留分額の算定の基礎となる財産
=被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産の価額-相続債務の全額
預貯金3400万円+株式1200万円+Bに対する生前贈与200万円-債務600万円=4200万円
4200万円が遺留分算定の基礎となる財産となります(株式は相続開始時の評価で計算、愛人への贈与は1年以内の贈与ではないので加算しない)。
遺留分額
=4200万円×1/2(遺留分割合)×1/3(法定相続分)=700万円
Bの遺留分侵害額
=遺留分額700万円-(取得財産0円-相続債務200万円(法定相続分))-特別受益200万円-遺贈0円
=700万円
Cの遺留分侵害額
=遺留分額700万円-(取得財産0円-相続債務200万円(法定相続分))-特別受益0円-遺贈0円
=900万円
※ 遺留分権利者が特別受益財産を得ている場合にはその価額を控除し、相続によって得た財産がある場合にはその価額を控除し、負担すべき相続債務がある場合はその額を加算します(最高裁平成8年11月26日)。
※ 但し、相続債務については、以下の例外(最高裁)がありますので、計算にあたっては注意する必要があります。
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ、これに応じた場合も、履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず、相続債務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである(最高裁平成21年3月24日)。
遺留分侵害額請求権は、形成権と言われており、意思表示をしないと発生しません。意思表示によって行使します。
必ず訴えを起こさなければならないということはありませんし、具体的に金額を示して意思表示する必要もありません。
通常は、遺贈などを受けた者に対し、配達証明付きの内容証明郵便を送付する方法で行います。
遺留分侵害額請求を行った後、遺贈などを受けた者と協議を行い、解決を図ります。協議が調わない場合は、調停や訴訟を提起して解決することになります。
遺留分をめぐる紛争は、被相続人の相続に関する紛争であり、「家庭に関する事件」として家庭裁判所の調停を行うことができ(家事法244条)、調停を行うことができる事件については、調停前置主義により、訴えを提起する前に、原則として、まず家庭裁判所の調停を経なければなりません(家事法257条)。
もっとも、いきなり裁判を提起した場合、必ずしも、調停に戻されるとは限りません。
調停をせずに訴訟提起した場合、「裁判所は職権で、事件を家事調停に付さなければならない。」とされていますが(家事法257条2項本文)、「ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。」(同但書)とされているからです。
調停に付しても、話し合いで解決できる見込みが低い場合、結局、当事者としては裁判を提起せざるを得ないことになり、時間も費用も無駄になります。そのため、早期解決を望む場合に、裁判をいきなり提起した方がよい場合があります。
実務的には、調停で解決できる見込みが無い場合は、その旨の上申書を添付して、いきなり訴訟を提起することも多いのではないかと思われます。
遺留分侵害額請求調停は、遺留分を侵害する相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所へ調停申立を行います。
手数料は、1件につき収入印紙1200円です。
連絡用の郵便切手代(各裁判所に問い合わせ)が併せて必要です。
申立書は、戸籍関係書類、遺産関係資料、遺言書(又は遺言書の検認調書謄本)、遺留分侵害額請求権を行使したことを疎明する資料等を添付して提出します。
申立書には、侵害額請求権を行使した年月日、方法等を記載します。
遺留分侵害額請求調停は、他の家事調停と特別に異なることはありませんが、法的知識を必要とする場合が多く、代理人弁護士が就いている場合が多いように思われます。
遺留分減殺請求調停が不成立となってしまうと、訴訟を提起するかどうかを検討することになります。
遺産分割調停は、不成立により終了すると、審判手続に自動移行しますが、遺留分侵害額請求調停は審判手続に移行しません。改めて訴訟提起を行う必要があります。
注意すべきなのは、裁判所の管轄です。
調停は、家庭裁判所が管轄裁判所でしたが、遺留分侵害額請求訴訟は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所又は簡易裁判所が管轄裁判所となります。
どこの地方裁判所(又は簡易裁判所)に訴訟提起するかについては、相続開始時の被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所のほか、被告の住所地を管轄する地方裁判所、不動産に関する訴えにつき不動産の所在地を管轄する地方裁判所、金銭債権について義務履行地(債権者)の所在地を管轄する地方裁判所とに認められています。
また、手数料は、調停にように一律ではなく、請求の内容や額によって変わってきます。弁護士に依頼した方が良いでしょう。
遺留分侵害額請求権の行使がいつまでも認められるとすると、相続関係がいつまでたっても確定しないことになり不都合であることから、遺留分減殺請求権には期限が定められています(民法1048条)。
具体的には、
①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(消滅時効)
②相続が開始した時から10年間(除斥期間)
が経過したときは、権利行使が出来なくなります。
減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時」とは遺留分権利者が単に被相続人の財産の贈与又は遺贈があったことを知るだけでは足りず、贈与や遺贈が遺留分を侵害することを知ることが必要とされています。
遺留分侵害額請求それ自体は、もちろん弁護士に依頼しなくても自分でも可能です。
確かに、遺言書に「財産全部を○○に相続させる」などと書かれていることも多く、自身の遺留分が侵害されていること自体は、比較的容易に分かるケースもあります。
しかし、通常、自身で請求を行っても、相手方(侵害者)がすんなり侵害事実を認めて、請求通りの支払いを行ってくるということは滅多にありませんし、そもそも自己の遺留分がいったい幾らなのかを正確に計算するのは難しいのが実情です。
請求自体は簡単でも、遺留分制度は、複雑かつ難解で、実際に基礎となる財産を算定し、具体的な請求を行って解決するには、法律の条文だけでなく、判例などの実務の知識が必要です。
遺留分に関する交渉は、決裂した場合の調停・訴訟負担、最終的に共有物分割まで視野にいれて交渉しなければなりませんので、時間的・経済的損得なども勘案した交渉を一般の方が行うのは難しい分野です。
また、遺留分についての争いは、親族間の感情的対立や紛争が背景になっていることが多く、専門家が介入することで、感情的な対立はひとまず棚上げし、権利の内容や遺留分制度に関する知識を提供することで、早期解決が図れるケースも多いといえます。
遺留分は、相続放棄と異なり、被相続人の生前に放棄することも可能です。
従って、相続人廃除のほか、遺留分の事前放棄と遺言を組み合わせることにより、財産を相続させない方法もあります。
但し、遺留分を放棄するためには、遺留分を持つ相続人が、家庭裁判所に対し、遺留分を放棄する手続を行い、家庭裁判所の許可を得る必要があります。つまり、相続させない相続人の協力が必要になります。遺留分を持つ相続人が、親子間での何らかの事情により、「相続しなくてもよい」と言っているような場合に利用できることになります。
申立ては、被相続人の住居地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
遺留分の放棄が認められても、相続権が無くなる訳ではありませんので、必ず遺言でその全財産を、遺留分放棄をした相続人以外の者に相続させたり、遺贈しておかなければなりません。
なお、相続人の一人が遺留分の放棄をしたとしても、他の相続人の遺留分が増えるものではありません。相続放棄があった場合には、他の相続人の相続人が増える場合がありますが、遺留分の放棄は、遺言者が自由に処分できる割合が増えるだけです。
また、遺留分の放棄が認められても、相続放棄をしたことにはなりません。遺留分を放棄した人も、相続が開始すると相続人となります。従って、遺留分の放棄をしたとしても、被相続人に債務がある場合には、債務を法定相続分に従って承継します。遺留分の放棄と相続放棄は別ですので注意しましょう。
プラン | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
交渉・調停 | 30万円 | 得られた経済的利益の10% (但し、最低額:30万円) |
- 1上記着手金と報酬には別途消費税がかかります。
- 2相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、内容証明郵便の起案・発送、調停申立書の作成、調停代理を含みます。
- 3経済的利益とは、協議、調停または審判で決定した依頼者が相続する財産(不動産については固定資産評価額とします)の合計額を意味します。争いが無かった額を含みます。
- 4遺留分減殺請求を受けている場合の報酬金は、請求されている金額から減額した金額の10%となります。
- 530万円を報酬金の最低額とさせて頂きます。
- 6同一の被相続人についての、複数の方のご依頼の場合、お二人目からの着手金は10万円となります。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日