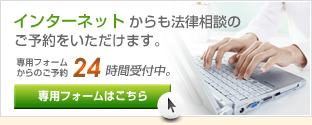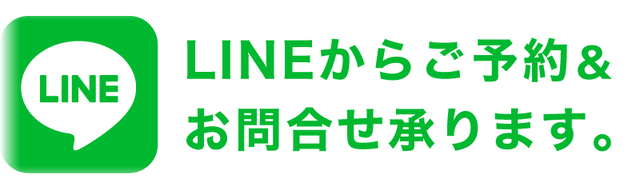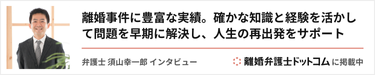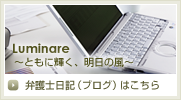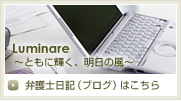兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
初めて離婚調停に出席する方へアドバイス

初めて離婚調停に臨まれる方はとても緊張され、ご不安なことと存じます。調停委員をつとめる立場から注意点などをご紹介いたします。
- 離婚調停とはどのような手続?
- 離婚調停をするタイミング
- 離婚調停の流れ
- 離婚調停の準備(申立書作成まで)
- 離婚調停を弁護士に同席してもらうメリット
- 調停申立書の作成-1 申立書の記載事項
- 調停申立書の作成-2 記載の正確性
- 調停申立書の作成-3 住所の表示をどうするか
- 調停申立書の作成-4 婚姻費用分担調停の検討
- 申立書提出後、第1回調停期日が決まるまで
- 第1回調停期日の指定
- 第1回調停期日の呼び出し
- 相手が調停に来ない(無断欠席)場合、調停はどうなるか
- 離婚調停を申し立てられた方へ(呼出状が届いた方)
- 離婚調停に出席する際の服装
- 離婚調停に出席する際の持ち物
- 離婚調停への親・親族の同行
- 乳幼児の同行
- 裁判所の場所・交通手段の確認
- 離婚調停に臨む際に気をつけておくべきこと
- 離婚調停を成立させる際の注意点
- 離婚調停が不成立になった場合にとるべき対応と流れ
- 離婚調停の調停委員ってどんな人?
- DV被害者の方が離婚調停を起こしたい場合
- 離婚調停の管轄について(自庁処理)
- 離婚調停の際の資料の提出(非開示希望など)
- 離婚調停の取下げ
離婚調停は、どのタイミングで起こすのが良いでしょうか。
通常、夫婦の一方が、もうこれ以上夫婦としてはやっていけない、離婚したいと考えた際、相手に離婚したいと意思を伝え、協議を始めることになると思われます。
子の親権をどうするか、養育費はいつまで幾ら支払うか、面会交流をどのように行うか、財産分与・慰謝料はどうするか、今後の住まいはどうするかといったことを決め、自分たちで離婚協議書を作成したり、公証人に離婚公正証書の作成を依頼したりします。
「これらを自分たちだけでは決められない」と判断したときが、調停を申し立てるタイミングです。
「決められない」理由は様々ですが、
- そもそも相手が話し合いに応じない
- 希望条件を伝えても相手から返事が無い
- 協議のたびに双方が感情的になって話し合いにならない
- 相手が協議の度に言うこと(希望条件)が変わる
- 相手に暴言・暴力の傾向がある
- 条件(養育費の額・財産分与・住居をどうするか・慰謝料)が合わない
- 法外な養育費・慰謝料を要求されている
- どちらも親権を譲らない
- 相手が子どもに毎日会いたいと主張するが非現実的
- 相手が浮気を認めない
- 子が成人するまで離婚しないと言われている
- 自分のこれまでの態度を反省し、改善するから離婚しない
以上のような場合、協議を続けても合意に至ることは難しく、速やかな離婚を求めるなら、離婚調停を申し立てるべきです。
離婚協議も離婚調停も、話し合いという意味では同じです。
しかし、調停は、それまでの自分たちだけでの話し合いと異なり、調停委員及び裁判官で構成される調停委員会という中立な第三者が間に入って話し合いを行います。
場所も、裁判所で一定期間ごとに期日が開かれ、話し合います。
調停委員から、今後の手続きの流れや一般的な解決方法が示され、期日ごとに段階を踏んで進められますので、法外な要求や、主張の変遷(話し合いの度に主張が変わること)は認められにくくなり、解決につながりやすくなります。
1 相手方の住居地を管轄する裁判所に申し立て
すぐに離婚したくても、いきなり離婚裁判を起こすことは原則としてできません(調停前置主義)。
調停を始めるには、必ず裁判所に対する「申立て」が必要です。
「申立て」という言葉自体、一般人の方には馴染みのないものかもしれませんが、要は、裁判所に調停の申請をする手続とご理解下さい。
離婚調停は、相手方配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てを行い、その裁判所で調停が行われるのが通常です。合意で裁判所を定めることが出来るケースは多くなく、通常は相手の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
したがって、別居し、遠方の実家に帰った場合など(例えば結婚して神戸で暮らしていたが、別居して東京に帰ったような場合)には、調停への出席が負担になる可能性が高いことは頭に入れておきましょう。
調停の「申立て」は、申立書を作成し、必要な添付書類と併せて裁判所に提出して行います。
申立書に記入すべき事柄、書類は、事件の類型によって異なります。弁護士に依頼をすると、この申立書の作成・提出から行ってくれますが、自分で作成して申し立てることも可能です。
※「事件」という言葉も、一般人の方にはニュースで話題になるような刑事事件や出来事をイメージされる方が多いかもしれませんが、調停や裁判など、裁判所が取り扱う案件のことを、「事件」と呼び、案件ごとに「事件番号」で管理されます。
各調停の申立書の書式は裁判所に準備されていますので、実際に裁判所に出向いてもらってくることも出来ますし、裁判所によっては、ホームページからダウンロード出来るようにしているところもあります。

2 期日の呼び出し
離婚調停を申し立てると、裁判所から双方に対し、調停を行う日(第1回調停期日)の連絡・呼び出しが行われます。
申し立てを行う際、どうしても都合の悪い日や曜日などがあるのであれば、申立書に事前に記載しておけば、通常、その日は除外した日が指定されます。

3 調停委員会が調停を進行
調停は、原則として、裁判官(または「家事調停官」という非常勤裁判官)1名と男女の調停委員2名の計3名で構成される調停委員会が行います。
裁判官は、同じ時刻に複数の調停事件を並行して担当しているため、調停に同席することは少なく、方針などについて、事前に打合せ(「評議」といいます)をした上で、実際の調停は、調停委員に任せるかたちで進められます(調停委員は期日の途中で裁判官に評議に行って方針を確認することがあるほか、期日終了後には調停委員から裁判官に期日の結果が報告されます)。
実際には、調停の当事者が裁判官と直接話をするのは、調停が成立する場面(又は不成立により終了する場面)だけであることがほとんどです。

4 裁判所に到着してからの流れ
毎回の期日は、双方とも同じ日に呼び出しが行われますが、時刻を20分~30分程度ずらして呼び出し、待合室も申立人と相手方で別にされており、出来るだけ顔を合わせることが無いような配慮がなされています。
呼び出された期日に裁判所に出向くと、まずは調停受付に行って、裁判所職員に出頭した旨を告げましょう。
職員から、待合室を案内されます。
待合室で待機していると、調停委員が呼びに来ます。通常は、申立人と相手方が交互に調停室に入って調停委員と話をします。
当事者が同じ部屋に入って調停を進める(同席調停)ことは、通常はありません。
夫婦間での暴行のおそれがある場合、精神的負担が大きい場合(PTSDなど)には、調停室が2室指定されて当事者はそこで待機し、調停委員が調停室間を移動するケースもあります。

5 毎回の調停の流れ
各回の調停は、概ね2時間で、30分程度を目安に交代して調停室で話をします。
2往復程度となることが多いです(申立人→相手方→申立人→相手方)。
もっとも、厳密に30分と決まっている訳ではなく、あくまでも目安であり、話の内容によっては一方が長くなってしまう場合もあります。
自分の番が短く、相手の番が長い場合、どうしても自分が不利益に扱われていないか、調停委員が相手の主張ばかりを聞いているのではないかと不安に思いがちですが、調停委員は中立ですので、どちらか一方に肩入れして話を聞くということはありません。
必要があってのことですので、不安に思う必要はありません。
もっとも、毎回相手の番が長く、自分の待ち時間が長いことが気になる場合には、率直に調停委員に理由を聞いてみるとよいです。
調停委員からその理由の説明が受けられると思われます。
調停は非公開で行われますので、傍聴人は勿論いません。調停室でのやりとりの録音は禁止されていますので注意しましょう。

6 期日・調停の終了
その後は、おおよそ1か月~2か月ごとに調停期日が開かれ、話し合いを続けていきます。
期日終了時に次回期日の調整(当事者双方及び調停委員が出席可能な日を調整します)を行います。
最終的に、合意が出来れば調停成立、合意が出来なければ調停不成立(調停委員は、単に「不成立」「打ち切り」「不調」という場合があります)となります。
事情によっては取下げにより終了する場合もあります。
調停が成立する場合には、当事者が合意で定めた内容が調書に記録されます。
調停調書は判決と同じ効力を持ちますので、内容によっては強制執行が可能となります。
離婚をする場合には、調停が成立した時点で離婚の効力が発生します(協議離婚は離婚届が受理された際に離婚の効力が発生しますが、調停離婚は調停成立時に効力が発生し、離婚届の提出は役所への報告的意味合いでの届け出になります)。
調停不成立の場合には、その旨が調停委員から示されて調停は終了します。特に何かをしなければならないということはありません。
この場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起するかを検討することになります。

7 調停の期間
離婚調停は、どのくらいの期間行われますか、というのはよくお受けする質問ですが、これに関しては、ケースバイケースとなります。
1回で成立して終了する場合もあれば、1年以上調停が継続しているケースも珍しくありません。
特に、親権・面会交流が争点になっているケースは、子の調査が必要となることも多く、長期化しがちです。
離婚調停の申立書を作成するにあたって、確認・収集・検討をしておかなければならない事項には以下のようなものが挙げられます。

1 管轄裁判所はどこか
管轄裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
自分が平日の昼間に出席出来るか、弁護士に依頼する場合、その出廷費用にも影響してきますので、管轄裁判所の確認は必ず必要です。

2 必要書類・証拠は収集できているか
戸籍事項証明書(戸籍謄本)、源泉徴収票、登記事項証明書(登記簿謄本)等、基本的な資料は収集しておく必要があります。申立書に添付して提出します。
年金分割を求める場合には、「年金分割のための情報通知書」の入手も必要です。
請求内容に応じた印紙を貼らなければなりませんので、印紙代が幾らになるのかの確認も必要です。

3 自分の意思・希望条件は明確になっているか
法律相談を受けていると、ここがはっきりしていない方が結構沢山いらっしゃいます。
明確になっていないという場合には、法律相談を受けるなどして自身の未来像をきちんと描いておく必要があります。
親権・養育費・財産分与・慰謝料・面会交流・年金分割などが検討対象になります。

4 (別居していない場合)別居の準備・方法・時期
離婚が成立すると、基本的には相手と別居し、自活していかなければなりません。具体的なスケジュールをある程度決めておく必要があります。

5 離婚後の生活設計は出来ているか
今後の収入の見通し、児童扶養手当の見込み額、扶養手当の減少等、離婚に伴い経済面に変化が出てきます。
実家に帰るのか、保育園の送迎は出来るのか、就労形態を見直すのか等々検討しておく必要があります。

6 相手から毎月の生活費が確保できているか(婚姻費用分担請求調停を同時に起こすかどうか。
別居しても、離婚が成立するまでは、夫婦間の扶助義務があり、相手から生活費(婚姻費用)を支払ってもらえるのが原則です。
生活費が支払われていない場合、早急に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることが大切です。
実務では、不払いが長期間継続していても、相手から遡って支払ってもらえるのは、請求時(調停申立て時)とされることが多いからです。

7 弁護士に依頼して、調停期日に同行してもらうか
自分で調停を乗り切れる自信があるか、弁護士費用を工面できるのか、後悔しないか、といった検討が必要です。

8 弁護士に依頼しない場合、申立書書式の入手は出来ているか
申立書書式(ひながた)は、裁判所ホームページからダウンロードしたり、家庭裁判所に実際に赴いて入手することが出来ます。
内容がきちんと書かれていれば、必ず裁判所の書式で申し立てなければならないということはありません。
裁判所によっては、調停申立書のほかに、添付書類の提出を求めている場合があります。
神戸家裁の場合、事情説明書、子についての事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書、非開示申出書等です。
申立てを行う前に一度裁判所に問い合わせをされることをお勧めします。
弁護士に依頼する場合には、弁護士が全てを作成してくれます。
(参考)神戸家庭裁判所の調停申立書 書式ダウンロードページ
裁判所所定の書式は、専門家ではなく、一般の方でも無理なく申し立てられるように設計されています。
申立書に記載する内容はそれほど多くありません。
30分もあれば十分完成させられる内容です。
離婚を求めるのかどうか、親権者をどちらにすることを希望するのか、慰謝料、財産分与を希望するか、といったの項目について、チェックをしたり、数字を記入するなどして作成していきます。
「申立ての理由の項目」では、同居・別居の時期や申立ての動機を記入します。
「申立ての動機」には、あらかじめ「性格があわない」「異性関係」「暴力をふるう」「酒を飲みすぎる」「性的不調和」「浪費する」等の項目が記載されており、あてはまる番号に〇、最も重要と思うものに◎を付けます。
申立ての動機を詳しく書きたい場合は、別紙をつけて説明することも出来ます。
ただ、申立書は相手方にも送付されます。したがって、申立書にどこまで記載するのかは慎重に検討する必要があります。
調停は、あくまでも合意により解決を目指す場であり、相手を非難したり、屈服させる場ではありません。
相手方に対する非難を並べ立てたり、事実と異なる事柄を書いたりすると、相手の感情を不必要に害し、調停に出席してくれなかったり、合意の可能性が低くなってしまいます。
私個人の意見としては、必要最低限の事柄だけを記入しておくのが良いと思います。
養育費、財産分与、慰謝料を請求したい場合も、とりあえずは「相当額」と記載しておき、具体的な額については調停が始まった後、相手から提示された資料等を確認した後に、調停委員を通じて相手に伝えてもらうのが良いように思います。
一方、事情説明書や進行に関する照会書等、申立書以外の書類は、相手方に送付されませんので、これらの書面で少し詳しめに事情を説明することが出来ます。
もっとも、これらの書類は、相手方が裁判所に対し、閲覧の請求をした場合には、裁判官の判断を経て開示される可能性がありますので、これらの書類についても、記載内容については細心の注意を払う必要があります。
調停委員をしている私の経験からすると、弁護士であっても離婚事件に不慣れな弁護士は訴状のような自己の主張をただ言いたい放題書いた調停申立書を裁判所に送付していることが多いように感じています。
調停は、訴訟と異なり、裁判官に自分の主張を理解してもらい、説得する場ではありません。
あくまでも、合意を目指して相手方と話し合う場であり、相手にも感情があるということを忘れずに書面を作成することが大切だと考えます。
それが結局、調停委員を味方につけ、相手方も冷静に事案に対処することが可能となり、早期解決に繋がることが多いのです。
申立書には自分の住所を記載する欄があります。
通常は現住所(住民票上の住所)を記載しますが、相手方からDVを受けていたり、家に押しかけてきて嫌がらせをされる恐れがあるような場合は、必ずしも現住所を記載する必要はありません。
現住所の非開示の上申書を提出するという手段もありますが、相手方も知っている同居時の住所を記載することも可能です。
一度、事情を説明して、担当書記官に相談してみてもよいかもしれません。
最終的に調停がまとまり、調停調書が作成される際に、担当書記官が調書に記載する住所をどうするかについて確認します。
そこで、住所の記載をどうするかについて最終的に判断することも出来ます。
離婚調停を申し立てる際には、併せて婚姻費用分担調停を申し立てるか否かを必ず検討するようにしましょう。
生活費の送金を受けていない場合又は裁判所算定表による金額が支払われていない場合、私は必ず同時に調停申立てを行うことをお勧めしています。
相手が離婚に応じない又は条件を争う態度を示している場合には、離婚が成立するまで長期化する場合があります。
その間の生活費を確保することは、じっくり腰を落ち着けて離婚の話し合いをするためにとても重要です。
また、婚姻費用は未払い分について遡って支払いを受けることが出来ますが、実務的には未払い分をすべて遡って支払ってもらえるとは限らず、通常は調停を申立てた月以降の分しか認められていません。
このため、場合によっては、離婚調停に先行して、婚姻費用分担調停だけでも先に起こしておくことをお勧めしています。
後に離婚調停を申し立てた場合、調停は別々に進行するのではなく、併合されて同じ時間帯に並行して行われます。
婚姻費用の額と養育費の額では、配偶者の生活費を含む分、婚姻費用の額の方が高くなります。
子がいない場合、離婚すれば婚姻費用の支払義務は消滅します。
このため、出来る限りお金を払いたくない配偶者は、早めに離婚に応じた方が経済的には得策となり、相手が離婚に応じたり、条件を譲歩する動機になりやすいですので、この意味でも申立てを積極的に検討すべきです。
離婚調停と婚姻費用分担調停の両方が申し立てられている場合、通常、日々の生活費を確保するという観点から、調停委員会は婚姻費用分担調停の方を先行して調停を進めることが多くなります。
離婚の話し合いが後回しにされてしまう可能性も無くはありませんので、調停委員には、離婚調停と同時並行で進めてもらえるよう、きちんと意思表明をするようにしましょう。
弁護士を付けた場合、慣れた弁護士であれば、このあたりは適切に対処するものと思われます。
裁判所は、離婚調停の申立書を受け付けると、各事件について「事件番号」を割り振ります。
以後、裁判所では当事者名と事件番号によって事件管理が行われます。
離婚調停の場合、令和〇年(家イ)第〇〇号という事件番号となります。
事件名は通常は、「夫婦関係調整調停事件」となります。
事件番号は、裁判所ごとに毎年1月から受け付け順に振られていきます。
弁護士が電話で書記官に連絡事項を伝える場合などは、「令和〇年(家イ)第〇〇号の件でお電話を差し上げました。ご担当の書記官をお願いします」などと伝えます。
裁判所では所内LANで事件を管理をしていますので、すぐに把握が可能です。
調停事件は、調停担当の裁判官に割り振られます。
複数の裁判官が担当している裁判所では機械的に事件が割り振られ、一人しかいない裁判所では、当該裁判官が担当することになります。
家事調停官(本職は弁護士の非常勤裁判官)が担当する場合もあります。
その後、担当する調停委員が決まります。男性・女性各1名が担当します。
調停委員は、裁判所ごとに民間人から任命されています。弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門職のほか、会社の元役員、大学講師、元裁判所職員等様々な方が任命されています。
担当する調停委員の割り振りは、予想される事件の内容や、調停委員が既に任命されている事件数などで決定しているようです。過去に当該当事者の調停事件を担当したことがある場合、事案をよく知っていますので、同じ調停委員が任命されることが多いようです。
担当裁判官が決まると、当事者、担当調停委員の予定と調停室の空き状況を踏まえて、第1回調停期日が指定されます。
弁護士が代理人として調停申立を行っている場合、予め電話等で弁護士(及び申立人本人)の予定を尋ねた上で調整が行われます。
弁護士に依頼している場合、自分が出席できない日は必ず弁護士に伝えておくようにしましょう。
弁護士に依頼せず、本人が申し立てている場合でも、裁判所によっては調整をしてくれますので、仕事の都合等でどうしても出席が難しい曜日などが決まっている場合には、調停申立書の添付書類にその旨を記載しておけば、通常は配慮がしてもらえるのではないかと思われます。
2回目以降の調停期日は、出席した調停期日で次回期日を調整しますので、必ずスケジュール帳を持参するようにしましょう。
1度決まった期日に出席できないということになると、相手方はもちろん、関係者全員に迷惑が掛かることになりますので、期日に出席できるかどうかは慎重に判断してください。
なお、調停期日が開かれる曜日は、担当裁判官によって決まっています(A裁判官は、毎週月曜と木曜など)。
したがって、2回目以降が何曜日に開催されるかは、調停委員に尋ねれば通常教えてもらえると思われます。
第1回調停期日が決まると、申立人と相手方それぞれに呼出状が送付されます。
呼出状には、日時と場所、事件番号、事件名、担当書記官等が記載されています。
呼出状は普通郵便で送付されます(訴訟の場合は、特別送達という特別な送達方法ですが、調停は普通郵便です)。
相手方に送付される呼出状には、申し立てられた調停事件に対する意向等を確認する文書が同封されていますので、事前に返送するようにしましょう。
事前に返送しておきますと、調停委員会は、第1回調停期日前に、双方の意向や関係者が置かれている状況等を事前に確認してから調停に臨むことができますので、1回目の調停期日が有意義になりやすいです。
なお、調停申し立てを弁護士に依頼している場合には、裁判所から当該弁護士に電話連絡があり、申立人本人には呼出状は送付されません。期日がいつに指定されたのかは、依頼した弁護士から連絡を受けるようにして下さい。
調停は、双方が家庭裁判所に出席し、話し合いにより自主的に解決を図る制度ですから、双方が出席することが前提です。
初回期日は、相手方の都合を確認せずに指定されることが多く、相手方から裁判所に欠席の連絡が事前にあれば、申立人のみの聴き取りを行って次回(第2回)期日を指定するか、第1回期日を変更することが一般的です。
無断欠席の場合、調停委員会は、相手方に対し、出席するよう働きかけを行ったり、裁判所調査官が直接連絡をとって、出頭を勧告することもあります。
それでも当事者が出席しない場合は、話し合いが出来ないため、残念ながら、申立人の意向を確認後、調停は不成立として終打ち切られるか、取下げを勧告されます。
それでも離婚を実現したい場合には、次の段階として、後述する離婚裁判を提起する必要があります。
明確な離婚原因がある(例えば相手方の不貞を立証できる証拠を保有している等)場合は、調停に固執せず、調停を早めに打ち切ってもらい、速やかに訴訟提起することを検討することになります。
裁判は話し合いの場ではありませんので、被告が欠席しても、裁判所は、原告の主張と提出された証拠に基づき、判決を出します。
逆に、明確な離婚原因が無く、訴訟を提起しても離婚の認容判決が得られる可能性が低い場合は、しばらく訴訟提起せず、一定の別居期間を置いてから再度離婚を試みるか、訴訟提起を行って、訴訟手続の中で和解離婚を目指していくことになります。
なお、裁判所から呼出を受けた当事者が正当な事由なく出頭しないときは、5万円以下の過料が課される旨の規定があります。現実に課されることは多くありませんが、相手がこの規定を知らない場合には、この規定を伝えて出席を促してみましょう。
離婚調停の呼出状は、何の前触れもなく、突然郵便で届きます。
調停では、調停を申し立てた方を「申立人」、調停を申し立てれれた側を「相手方」と便宜上呼びます。
調停を申し立てられると気分を害される方もいらっしゃいますが、あくまでも裁判所で調停委員を通じて話し合いましょうということですので、自分にとってもメリットがある場合もあります。
感情的になっても仕方がありませんので、冷静に対応するようにしましょう。
呼出状には、第1回調停期日の日時、事件番号、担当書記官、連絡先電話番号等が記載されているはずです。
まずは、第1回調停期日に出席可能かどうかをチェックし、スケジュール調停を行いましょう。
どうしても出席が難しい場合は、出来るだけ速やかに呼出状に書かれた裁判所に連絡するようにしてください。
また、照会書等が同封されていると思われますが、回答期限までに提出するようにしましょう。
回答書に記載したことは、その後の調停や訴訟で前提とされますので、慎重に対応することが重要です。
不安があれば、回答書を提出する前に、弁護士に依頼て対応してもらうということも大切です。
1 自分が提出した資料・相手方が提出した資料
離婚調停の申立書、事情説明書、主張書面、証拠資料(源泉徴収票、給与明細、不動産登記事項証明書等)など、自分が裁判所に提出した書類は必ずコピーを取っておき、ファイルに綴じて持参してください。
調停期日の際に、これまでの主張を確認したり、記載内容について調停委員から確認を求められる場合があります。
相手方が提出した書類も同様です。全てをファイリングしておきましょう。
なお、全てを透明のクリアーファイルに入れておられる方もいらっしゃいますが、確認しにくいのでパンチで穴を開け、2穴ファイルに古い資料から順に綴じていかれることをお勧めします(もっとも、原本はその性質によっては穴を開けずに保管しておきましょう)。

2 裁判所からの呼出状・事件番号が書かれた出頭カード
呼出状には事件名・事件番号や担当書記官が記載されています。
裁判所に出頭した際に、これらを見せるとスムーズな案内が受けられます。

3 身分証明書
初回期日に本人確認のために、身分証明書の提示が求められるのが通常です。
免許証を提示すると、調停委員は、申立書の記載内容と照らし合わせて確認します。

4 ノート、メモ帳、筆記用具
緊張して忘れてしまったときのために、自分の検討してきた主張内容、希望条件、相手方に確認したい事項等を書いたメモを持参することもお勧めです。
調停期日では、メモを見ながら話しても構いません。
また、期日において、調停委員から伝えられた相手方の主張や調停委員から出された課題・宿題をメモする必要がありますので、ノート、メモ帳は持参された方が良いでしょう。

5 スケジュール帳、シフト表
その日の調停期日が終了する際、次回期日の調整が行われます。
当事者の両方と調停委員2名の全員が出席可能な日を調整しますので、スケジュール帳やシフト表、スマホでスケジュールを管理している場合はスマホを忘れずに持参してください。
スケジュール不明のまま適当に期日を決めると、出席できないことになった場合、期日が無駄になり、相手方・調停委員に迷惑が掛かります。
もっとも、期日が決まった後、急病や予測不能な出張等が入り、期日への出席が不可能になった場合、速やかに裁判所に連絡し、相談してください。

6 認め印
調停期日において、裁判所に書類(受領書、取り下げ書等)を提出する必要が生じる場合があります。
その際、押印が求められることがありますので、認め印を持参しているとその場で対応できます。

7 自分の預金通帳
相手から金銭を振り込んでもらう内容の調停(養育費、財産分与、慰謝料等)が成立しそうな場合、調停調書に自分の振込先口座を記載してもらいたい場合には、預金通帳の原本か、通帳の裏表紙の写し(金融機関、支店、種別、口座番号、名義が記載されているもの)を期日に持参しておくとよいでしょう。
調停成立時にこれらが分からない場合、速やかに裁判所にFAX等の連絡をしなければなりません(離婚調停は成立後10日以内に届け出をしなければならない関係上、裁判所も調書の作成を急ぎますので、何日も待ってくれません。当日か遅くとも翌日には連絡の必要があるでしょう)。
単に、「**が指定する口座に振り込みの方法で支払う」と調書に記載してもらうことも出来ますが、その場合、相手に振り込みを希望する口座を連絡する必要があります。「振込先が分からなかったから振り込まなかった」というような言い訳をされたくないなら、調書に明示してもらっておく方が安心です。

8 時間つぶしの道具
調停は、自分と相手が交互に呼ばれますが、相手が調停室に入っている間、待合室でじっと何もせずに待っているのは苦痛です(いつ呼ばれるか分かりませんので、外を散歩する等は出来ません)。
調停内容によっては1時間以上待たされることも珍しくありません。
本や雑誌などを持参しておくと良いかもしれません。
調停室には、原則として調停の当事者本人しか入室することが出来ません。
親御さんが「本人が事情を上手に話せないから同席したい」「重大な関係があるから同席したい」といった希望を述べる方が時折いらっしゃいますが、通常は待合室でお待ちください、と調停委員から言われることになります。
調停は、自分自身の事を話し合う手続です。
当事者本人の意思・意見・考えが大事ですので、よく考えて臨んでください。
調停委員は、当事者本人が自分の意思を発言しているのか、親の意向に従って発言しているに過ぎないのかは分かります。
私の経験上、親であれ第三者が本人の意思決定に関与することは、調整を難しくすることが多いという印象です。
もっとも、裁判所に出向くというのは誰しも緊張するものですし、相手方と同じ建物に入るということですから心理的負担も大きいかもしれません。
そのような場合に、裁判所の建物まで同行してもらうということは、本人を安心させ、勇気づけるために有用です。
本人の意思を尊重しつつ、相談相手になる程度であれば同行も良いかもしれません。
調停期日を重ね、お互いに合意が出来た場合には、離婚調停が成立します。
それまで調停期日には同席していなかった書記官が部屋に入り、裁判官がやってきて、合意内容を読み上げます。
事前に調停委員から調停条項の概要の説明を受けられることが多いと思われますが、そうでない場合もありますので、裁判官が読み上げる内容はよく確認するようにしてください。
了承するかどうかは、その場で、口頭で求められます。
署名、押印は必要ありません。
裁判官が読み上げた内容につき、双方が了承すると、調停成立となり、書記官が調停調書を作成します。
最後の裁判官の読み上げの段階でも、やはり嫌だと言うことももちろん可能です。疑問点を質問することも出来ます。
ですので、最後まで気を抜かないようにしましょう。
【離婚届の提出について】
協議離婚は、離婚届を提出し、受理されたときに離婚の効力が発生しますが、調停離婚の場合は、調停が成立し、調書が作成されたときに離婚の効力が発生します。
役所への離婚届の提出は単に「報告的届出」にすぎません。
調停離婚であっても、裁判所から役所に離婚の連絡がされる訳ではありません。
離婚届の提出が必要です。
調停離婚の場合、通常、調停調書の第1項に、「申立人と相手方は、本日、調停離婚する。」と記載されます。
このような記載がなされると、離婚届を提出できるのは原則として、申立人になります。離婚調停を申し立てたのが夫なら夫、妻が申し立てたなら妻となります。
しかし、婚姻の際、妻側が氏を変えて夫の戸籍に入っていた場合、離婚の際に戸籍から出ていくのは妻であり、妻は、婚姻前の元の戸籍に戻るのか、新しい戸籍をつくるのかを届出用紙に記載しなければなりません。
また、氏(苗字)は、離婚により元に戻るのが原則ですが、3か月以内に届け出をすれば、婚姻中の氏を使い続けることが出来ます。
離婚届と同時に婚姻時の氏を続けて使用する旨の届出をすれば、元の氏の戸籍は作られませんが、同時に届出をしなかった場合、一旦元の氏の戸籍が作られ、後で婚姻中の氏を使用する旨の届出をした際に、改めて新しい戸籍が作られることになり、煩雑になります。
以上から、協議離婚にしても、調停離婚にしても、離婚届を提出するのは、婚姻時に氏を変更していることが多い妻側にしておくことが便宜にかないます。
このため、離婚調停において、夫側が申立人である場合、裁判所は、「申立人と相手方は,本日、相手方の申し出により、調停離婚をする。」という調停調書を作成します。
このように書いておくと、妻側が離婚届を提出することが出来るようになるからです。
これを見て、夫から求められて渋々離婚に応じることにした妻から「私は離婚など望んでいない!!」と思われるかもしれませんが、あくまでも便宜上のものですので、気になさる必要は全くありません。
どうしても嫌であれば、「相手方の申し出により」は外しても構いません。
ただ、上述のとおり、後で色々不便が生じますことを覚悟のうえ希望してください。
離婚届は、調停成立後、10日以内に役所に提出しなければなりません。
本籍地で届出をする場合には、戸籍謄本は不要ですが、本籍地以外で届出をする場合は、自身の戸籍謄本が必要になります。
本籍地以外で離婚届を提出する予定である場合、戸籍謄本を取り寄せるのに時間がかかりますので、離婚が成立しそうな場合には、予め取り寄せておくことをお勧めします。
法務省 離婚届ページ
調停期日で話し合いを続けた結果、調停成立の見込みが無いと判断されると、離婚調停は不成立として終了します。
調停は、話し合いにより当事者間の紛争を解決することを目的とする制度です。
したがって、今後いくら期日を重ねても両者の対立が激しくて溝が埋まりそうにない場合や、一方が調停に出席せず話し合いすら難しいような場合には、成立の見込みがないため、打ち切られるのです。
離婚調停が不成立により終了すると、特に自動的に訴訟に移行するというようなこともありません。
次回期日も指定されません。
不成立になること自体は、「何も決まらなかった」という結果が生じただけで、双方に不利益はありません。
積極的に離婚したい側が訴訟を提起するか、少し別居期間を置いてから再度離婚を試みるかといったことを検討することになります。
「調停委員ってどんな人?」
「普段は何をしている人?」
調停委員って謎の存在ですよね。
「出来る事なら自分の味方になってもらいたい」
多くの方がそう思っていると思います。
もし味方に付けたいなら、まずは「相手を知ること」です。
離婚調停の場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門職が選任されることは多くなく、一般委員が選任されることが一般的です。
一般委員には、元裁判所職員、会社を定年退職された方、元会社役員、元教師等様々な方がいらっしゃいます。
原則として40歳から70歳までの方が任命されています。
非常勤ですので、毎日裁判所に通っているわけではなく、原則として担当事件の期日の日に仕事をします。
(ちなみに、私も調停委員に任命されています。)
当事者の一方が、DV被害を受けたと主張している離婚調停は、家庭裁判所も、当事者が裁判所庁内で対面するなどのトラブルが生じないよう、呼出時間や退庁時間をずらしたり(待ち伏せされないよう、先に被害者に退庁して頂く)、調停室の階を分けたりして、特別の対応をしています(通常のケースは待合室を分け、呼び出し時刻を多少ずらすのみ)。
したがって、DV被害者で、裁判所で万一加害配偶者と出会ったらどうしようなどという恐怖感がある場合には、裁判所に対し、その旨を事前に伝え、相談するようにしましょう。
裁判所も出来る限りの対応はしてくれるのではないかと思います。
もし可能であれば、DV被害者の方については、裁判所にもきちんと説明し、調停期日に安心して臨むため、弁護士に依頼されることをお勧めします。
離婚調停の管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所とされています。
通常はなかなか相手と裁判所の合意は出来ませんから、通常は相手方の住所地を管轄する裁判所に赴かなければなりません。
最近は、弁護士が代理人に就いている場合は、電話での調停が実施されることもあります。裁判所によってはWEBによる調停も始まっています。
相手方の住所地の家庭裁判所に赴くことが困難な場合や申立人の住所地の家庭裁判所で調停を行うことが適切といえるような場合には、自庁処理の上申書を添付して相手方の住所地を管轄する裁判所とは異なる裁判所(多くは申立人の住所地を管轄する家庭裁判所でしょう)に調停申立を行う場合があります。
上申書を添付して申立てを行っても必ず認められる訳ではありませんが、認められなくても原則通りの管轄権のある裁判所に移送されるだけですので、特別な事情があるような場合はチャレンジしてみても良いと考えます。
もっとも、自庁処理の上申書は単に希望を述べるだけでなく、その理由を説得的に記載する必要がありますので、弁護士によく相談しましょう。
相手方の住所地(例えば大阪家裁)で調停が始まった後(例えば婚姻費用分担調停)、相手方が申立人(例えば神戸に居住)に対して離婚調停を申し立てる場合、相手方は神戸家裁に申し立てる必要があるのでしょうか。
この場合、類似の調停事件を別々の裁判所で行うのは不経済であり負担も大きいことから、離婚調停は大阪家裁に関連事件として申し立て、裁判所は、後から申し立てられた離婚事件の相手方の意向を確認し(通常は同じ裁判所で行ってもらいたいことから承諾する)、大阪家裁で自庁処理により両事件が同時に行われることが一般的です。
但し、最終的な判断は裁判所の判断となることは留意が必要です。
離婚調停の際には、様々な資料の提出が必要となります。
例えば源泉徴収票や給与明細書の写し、不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し、診断書等が典型例です。
調停で資料を提出する際には、裁判所に提出するものと同じものを相手方にも交付することを求められます。
これは、前提となる資料を共有していないと話し合いを進めるのが難しいからです。
したがって、自分から裁判所に提出する資料に、相手には秘密にしておきたい情報(例えば住所や勤務先など)が書かれている場合は、必ずマスキングして提出するようにしましょう。
ただ、マスキングして提出すると、裁判所も内容を確認出来ません。
裁判所には読んでもらいたいが、相手には見せたくないといった情報が記載されている資料については、相手に開示しないよう非開示の上申書を添付して提出するなどの対応が必要になります。
取り扱いは、裁判所によって異なる場合がありますので、相手に見せたくない情報が記載されている資料の提出を検討する場合には、事前に方法について裁判所と相談しておくことが重要です。
非開示の手続きを取っておくと、相手方が閲覧や謄写(コピー)の申請をした際に裁判官が許可するかどうかの判断材料とされます(最終的には裁判官の判断になり、必ず不許可となるとは限りませんが、非開示の希望が尊重されることが多いと思われます)。
なお、弁護士に依頼している場合は、弁護士が非開示情報について適切に対応してくれるはずです。
離婚調停を申し立てた後、申立人は、いつでも調停を取り下げることができます。
具体的な理由を述べる必要もありません。
相手方の同意は不要です。
調停を取り下げる事情は様々でしょうが、離婚意思が無くなった場合や協議離婚する場合、相手方が出席しない場合等が考えられます。
調停を取り下げた場合、調停を前置したものとして離婚訴訟を提起できるかについては、調停期日が開かれて実質的な話し合いが行われていた場合は調停を前置したものと評価される可能性が高いといえます。
逆に、第1回期日が開かれる前に取り下げた場合などは、実質的な話し合いが行われていませんので、調停前置の要件を満たさないと考えられます。
法律相談のお申込みはこちら
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚サービス案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 家族信託
- 成年後見制度
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日