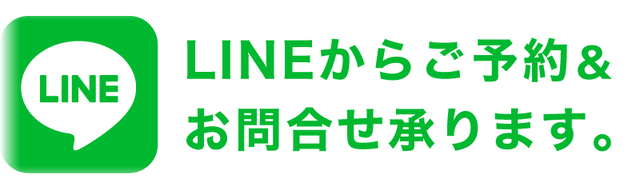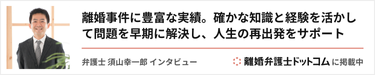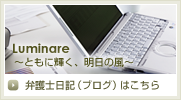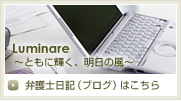弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
神戸の弁護士が離婚時の年金分割について解説します
離婚時の年金分割とは、公的年金のうち、厚生年金、共済年金につき、保険料納付実績(保険料納付記録)を分割する制度です。
婚姻中に夫婦の一方(例えば夫)が納付した保険料の一定割合を、分割を受ける者(例えば妻)が納付したものとして記録を付け替え、分割を受けた者(妻)が受給を開始する際、分割を受けた納付実績を考慮した年金を受給する権利が発生します。
国民年金や、厚生年金基金・国民年金基金等は分割の対象となりません。
年金分割の種類(合意分割)
【合意分割】
夫婦の双方が年金分割及びその分割割合について合意していれば、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大1/2として分割出来るという制度です。
合意が出来ない場合には、夫婦の一方が裁判所に申立をして、裁判所で按分の割合を決定することも出来ます(年金分割の調停や審判)。
【合意分割の手続】
①当事者間の協議による場合
当事者間の話し合いによって合意分割を行うためには、当事者間で決定した按分割合を定めた書面を作成する必要があります。
具体的には、合意の内容を定めた公正証書の謄本、公証人の認証を受けた書面等が必要となります。
当事者間の話し合いによる場合でも、書類の作成等、専門的な知識を要する作業が必要となりますので、弁護士等に相談されることをお勧め致します。
②当事者間の話し合いでは決まらない場合
当事者間の話し合いでは合意できない場合には、一方の当事者が家庭裁判所に申立をして、その割合を定めることができます。
家庭裁判所における手続に際しては、一度、弁護士に相談されることが望ましいといえます。
③標準報酬改定請求
①又は②により、分割割合が定まった場合、夫婦であった者の一方は、標準報酬改定の手続を行います。
実際には、所定の請求書に必要事項を記載し、請求する側の現住所を担当する年金事務所を通して社会保険庁に提出することになります。
なお、標準報酬改定請求は原則として、離婚等をした日の翌日から2年以内に行う必要があります。
年金分割の種類(3号分割)
【3号分割の制度とは】
平成20年4月以降に配偶者の一方が第3号被保険者であった期間について、他方配偶者の保険料納付実績の1/2を自動的に分割できる制度です。
合意分割とは異なり、夫婦間の合意の必要はなく、請求すれば、当然に1/2の割合で分割されることになります。
【3号分割の手続】
3号分割の場合、当事者間の合意は不要となりますので、当事者の一方が、他方の合意がなくとも標準報酬改定請求を行うことが可能です。
請求は、合意分割の場合と同様に、原則として離婚等の翌日から数えて2年以内に請求を行う必要があります。
合意分割と3号分割の関係
平成20年4月1日以降に関しては、合意分割と3号分割が併存することになります。
【3号分割の分割請求を行った場合】
3号分割の請求のみがなされた場合には、対象となる平成20年4月1日以降の期間についてのみ年金分割が行われることになります。
【平成20年3月31日以前の対象期間を含めて合意分割の請求を行った場合】
この場合には、合意分割の請求と同時に3号分割の請求もあったものとされます。
したがって、平成20年4月1日以後の特定期間につき3号分割が行われ、平成20年3月31日以前の期間については合意分割が行われることになります。
よくある勘違い‐1 夫の年金全部が対象になる
離婚時年金分割において、実際に分割するのは、夫が会社員なら厚生年金、公務員や私立学校の教職員なら共済年金の報酬比例部分のみです。
「3階建て」の日本の年金制度において、2階部分のみで、国民年金や厚生年金基金(但し代行部分は分割対象)などの企業年金は対象外です。
したがって、ずっと自営業の場合、そもそも2階部分がありませんので、分割する対象となる年金が無いことになります。
また、対象期間は、結婚してから離婚するまで(別居期間含む)です。従って、婚姻期間が長ければ、分割額は増えますので、メリットが大きいのは「熟年離婚」ということになります。
「年金分割のための情報通知書」を年金事務所又は共済組合に請求し、該当期間の夫婦の標準報酬総額を計算し、額の多い方が少ない方へ分割します。
割合は夫婦で話し合って決めますが、上限は50%です。
合意ができなければ、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることになります。
なお、ほとんどのケースで分割割合が50%となっています。
よくある勘違い‐2 専業主婦なら必ず2分の1
専業主婦であれば、かならず夫の年金は無条件で半分もらえると誤解されている方がまだまだ多いようです。
確かに、専業主婦(第3号被保険者)が求めれば、夫婦の合意がなくても年金分割が受けられる「3号分割」制度があります。
しかし、この制度が適用されるのは、2008年(平成20年)4月以降、離婚するまでの間の標準報酬総額に限定されています。
したがって、2008年4月以前に婚姻し、2008年4月までの間の部分について分割を受けたい場合には、合意分割制度に基づいて、夫婦で話し合って分割の割合を決める必要があります。
よくある勘違い‐3 分割したら自動的に受け取れる
分割した年金を受け取るには、離婚した翌日から2年以内に年金事務所等へ手続をしなければなりません。
当たり前の話ですが、せっかく話し合って案分割合の合意をしても、手続をしなければ変更されませんのでご注意ください。
また、分割するのは保険料の納付記録であって、実際の年金額ではありません。
年金は、分割された保険料納付記録を前提に、受給資格期間を満たしたうえで、生年月日と性別によって定められている受給開始年齢に達しないと受け取ることは出来ません。
よくある勘違い‐4 女性は必ず増える
年金分割は、「女性は常にもらう側(増える側)
」と考えがちですが、そうとも限りません。
夫婦の一方から他方へ、多い方から少ない方へ分割するのが基本ですので、妻の方が夫より納付実績が多ければ妻の年金を夫へ付け替えるというケースもありえます。
また、例えば夫はずっと自営業で国民年金、妻はずっと会社勤めを続けていたとすると、2階部分を持たない夫には分割する年金はありませんが、妻には厚生年金がありますので、夫が求めれば、妻の年金が分割されることになります。
よくある勘違い‐5 再婚や死亡でもらえなくなる
夫から分割された年金の納付記録について、夫が亡くなったり、自分が再婚しても、受け取る年金に影響はありません。
これは、年金の受給開始前であっても、開始後であっても同じです。
遺族年金は、再婚すると受給権が無くなりますが、年金分割と混同しないようにしましょう。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日