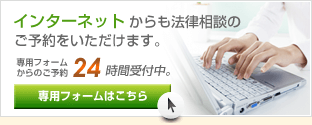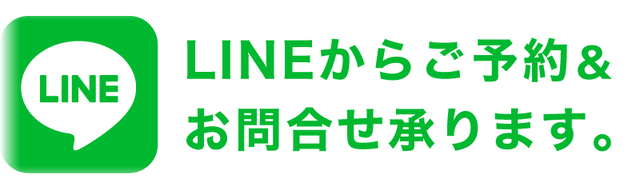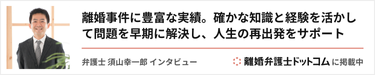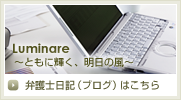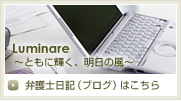弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
別居中の生活費(婚姻費用)でお悩みの方へ|神戸の弁護士が解説
婚姻費用の基礎知識
別居後の生活費について、
「そもそも婚姻費用を請求できるのか」
「いくらぐらいが妥当なのか」と悩まれて、このページをご覧になっている方も多いのではないでしょうか。
婚姻費用は、夫婦である以上、法律上当然に認められた権利であり義務です。
話し合いが難しい場合でも、調停などの適切な手続きを取ることで、請求・調整が可能です。
このページでは、婚姻費用の基本から、実務で特に問題になりやすいケースまでを、神戸で家事事件を多く扱ってきた弁護士の視点で分かりやすく解説します。
1 婚姻費用の基本的な考え方
2 婚姻費用を請求・調整する手続き
3 婚姻費用の支払いが問題になるケース
4 収入・生活状況別の婚姻費用の考え方
5 婚姻費用と他の制度との関係
6 特殊なケース
1 婚姻費用の基本的な考え方
夫婦は婚姻すると、原則として同居し、協力して共同生活を営むことが予定されています。この夫婦の生活を維持するために必要となる費用を、法律上「婚姻費用」といいます。
夫婦には、互いに協力して扶養する義務があり(民法752条)、それぞれの収入や生活状況に応じて、婚姻費用を分担しなければなりません。これを「婚姻費用分担義務」といいます。
この婚姻費用分担義務は、単に最低限の生活を支えるという「生活扶助義務」にとどまりません。「自分と同程度の生活水準を相手にも保持させる義務(生活保持義務)」であるとされています。
そのため、夫婦のいずれか一方の収入が高い場合には、収入の多い側が、収入の少ない側に対して金銭(婚姻費用)を支払う必要が生じます(民法760条)。
また、子どもがいる場合には、子の生活費や養育費も婚姻費用に含まれます。
婚姻費用に含まれる主な費用としては、衣食住の費用、医療費、交際費、娯楽費、子どもの養育費や教育費などが挙げられます。
婚姻費用の具体的な金額については、最高裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が、実務上の目安として広く用いられています。家庭裁判所の調停や審判でも、原則としてこの算定表を基準に婚姻費用額が判断されます。
【算定表の基本的な見方】
算定表は、子の人数や年齢に応じて複数用意されています。ご自身のケースに該当する表を選んだうえで、次の手順で確認します。
- 義務者(支払う側)の年収を縦軸から選ぶ
- 権利者(受け取る側)の年収を横軸から選ぶ
- 縦軸と横軸の交わる部分が、標準的な婚姻費用の月額の目安となります。
【算定表がどこまで考慮されるのか】
家庭裁判所の実務では、婚姻費用は算定表を基準に算出するのが原則とされており、個別の事情は、算定表が示す幅の中で調整されるにとどまるのが一般的です。
算定表の幅を超えた金額が認められるのは、算定表をそのまま用いると著しく不公平となるような特段の事情がある場合に限られます。
代表的な例としては、算定表が「子が公立学校に通学していること」を前提としているため、私立学校の学費や高額な教育費がかかっている場合などが挙げられます。
【算定表がそのまま使えないケースもあります】
算定表は、
- 子を権利者(請求する側)が監護している
- 他に扶養すべき家族がいない
という前提を置いて作成されています。
そのため、
- 義務者(支払う側)が子を監護している場合
- 義務者に前婚の子がいて扶養義務を負っている場合
などには、算定表をそのまま当てはめることができず、個別の計算が必要となります。
このようなケースでは判断が専門的になるため、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
婚姻費用は、いつの分から支払う義務が生じるのかが重要なポイントになります。
この「いつから支払うか」を、婚姻費用の始期といいます。
実務上は、婚姻費用を請求する意思を明確に示した時点を始期とするのが一般的です。
具体的には、次のいずれかの時点が始期とされることが多くあります。
- 婚姻費用の支払いを求める内容証明郵便を相手方に送付した時
- 婚姻費用分担請求調停を申し立てた時
この考え方は「請求時説」と呼ばれ、家庭裁判所の実務でも広く採用されています。
そのため、生活費の支払いが止まってしまった場合には、できるだけ早く正式な方法で請求の意思を示すことが重要です。対応が遅れると、遡って婚姻費用を受け取ることができない可能性があります。
なお、離婚調停を申し立てただけでは、婚姻費用を請求したことにはなりません。
婚姻費用を求める場合には、離婚調停と併せて、婚姻費用分担請求調停を別途申し立てる必要があります。
やってはいけないこと(重要)
口頭やLINEだけで曖昧に請求すること
「生活費を払ってほしい」と口頭やLINEで伝えていても、それだけでは法的に請求したとは評価されない場合があります。
特に、後から
「請求されていない」
「一時的なお願いだと思っていた」
などと争われると、不利になることがあります。
婚姻費用を請求する際は、
- 内容証明郵便
- 婚姻費用分担請求調停の申立て
など、記録に残る方法で請求の意思を明確にすることが重要です。
婚姻費用は、いつまで支払う必要があるのかという点も重要なポイントです。
婚姻費用分担義務の終期は、原則として、当事者が離婚に至るまで、または別居状態が解消されるまでとされています。
そのため、離婚が成立した場合には、離婚成立日の属する月をもって、婚姻費用の支払義務は終了します。
また、別居を解消し、再び同居した場合にも、婚姻費用の支払義務は原則として終了します。
実務上、婚姻費用分担調停が成立すると、調停調書には次のような内容が記載されることが一般的です。
相手方は、申立人に対し、婚姻費用として、
令和〇年〇月分から、当事者が離婚または別居状態の解消に至るまで、
月額〇万円を、毎月末日限り、申立人指定の銀行口座に支払う。
このように、婚姻費用は将来にわたって自動的に継続するものではなく、離婚または別居解消という事情が生じた時点で終了することになります。
2 婚姻費用を請求・調整する手続き
別居中であるにもかかわらず、夫が生活費を支払ってくれない場合でも、婚姻費用は話し合いによって決めるのが原則です。
まずは、婚姻費用の額や支払方法について当事者間で協議します。
しかし、話し合いがまとまらない場合や、そもそも協議ができない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることになります。
調停で合意が成立すると、その内容は調停調書に記載されます。
この調停調書は、確定した審判と同じ効力を持ち、支払いがなされない場合には強制執行を行うことも可能です(家事事件手続法268条1項)。
金額の合意が出来ないなどの理由で調停が不成立となった場合には、手続は審判に移行し、家庭裁判所が婚姻費用の額や支払方法を判断します。
また、調停が成立するまでに時間がかかり、生活に困窮するおそれがある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、婚姻費用の支払いについて仮の処分(保全処分)を命じてもらえる場合があります。
婚姻費用分担調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担調停申立書を提出して申し立てます。
婚姻費用は、夫婦双方の収入状況をもとに算定されるため、収入に関する資料の提出が必須となります。
【主な収入資料】
一般的には、以下のような資料を提出します。
- 源泉徴収票(直近年度分)
- 所得証明書
- 確定申告書の写し(自営業等の場合)
なお、所得証明書は、請求した年度の前年の所得が記載される点に注意が必要です。(例:令和6年度の所得証明書には、令和5年分の所得が記載されます)
【事情に応じて必要となる資料】
個別の事情がある場合には、以下の資料を追加で提出します。
- 子どもが私立学校に通学している場合:学費や教育費を示す資料
- 転職直後で前年の年収が実情と合わない場合:現職の労働条件通知書、直近数か月分(目安として3か月分程度)の給与明細
- 育児休業中・失業中の場合:育児休業給付金決定通知書、雇用保険受給資格者証 など
なお、申立てを受けた側(相手方)についても、同様に収入資料の提出が求められます。
提出資料に不備があると、調停が円滑に進まなかったり、実態を反映しない金額で話が進んでしまうこともあります。ご不安な場合は、弁護士に相談のうえ準備されることをおすすめします。
婚姻費用分担調停を検討している方は、
▶ 離婚調停の流れと注意点 を併せてお読みください
婚姻費用分担調停を申し立てると、家庭裁判所から、当事者双方に対して収入資料の提出を求める連絡が行われます。
しかし、特に義務者(支払う側)が弁護士を付けていない場合などには、収入資料の提出を拒んだり、提出を先延ばしにするケースも少なくありません。
【同一世帯の場合の対応】
まだ双方が住民票を移しておらず、形式上同一世帯となっている場合には、役所で相手方の所得証明書を取得できる可能性があります。この点は、状況に応じて役所で確認してみるとよいでしょう。
【調査嘱託による収入調査】
調停手続では、家庭裁判所に対し、調査嘱託の申立てを行うことが可能です。
調査嘱託が認められると、裁判所から相手方の勤務先に対して、収入資料の提出を求める照会が行われます。勤務先に裁判所から連絡が入ることを避けたいと考え、この段階で任意に収入資料を提出するケースも少なくありません。
なお、調査嘱託の申立ては専門的な対応が必要となるため、弁護士に依頼している場合には、通常は弁護士が対応します。
【収入が明らかにならない場合】
それでも相手方の収入が明らかにならない場合には、調停で合意が成立することは通常は難しく、手続は審判へ移行することになります。
審判では、賃金センサスなどの統計資料等を参考にして、家庭裁判所が相手方の収入を推計したうえで婚姻費用額を判断することもあります。
相手方が収入資料を提出しない場合でも、対応の選択肢はありますので、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
婚姻費用の金額を、調停や公正証書によって定めた場合でも、その後に事情が変わったからといって、婚姻費用が自動的に終了したり、金額が変更されたりすることはありません。
たとえば、
- 収入が増減した
- 失業・転職・病気などがあった
- 子どもの進学や養育状況が変わった
といった事情が生じても、何もしなければ、従前どおりの金額の支払義務が続くのが原則です。
当事者間で話し合いにより合意できる場合は、その内容に応じて変更することが可能ですが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して、婚姻費用の「増額」または「減額」を求める調停を申し立てる必要があります。
事情変更があるにもかかわらず手続きを取らないままにすると、不合理な金額の支払い・受領が続いてしまうおそれがあります。
状況に変化が生じた場合には、早めに専門家へ相談し、変更の可否や適切な対応方法を確認することをおすすめします。
3 婚姻費用の支払いが問題になるケース
「これまで生活費をもらっていなかった分を、後からまとめて請求できるのか」
婚姻費用について、この点を気にされる方は非常に多くいらっしゃいます。
結論から言うと、婚姻費用を過去にさかのぼって請求できるケースは限定的です。
家庭裁判所の実務では、婚姻費用の始期は、
- 婚姻費用分担請求調停を申し立てた時
- 婚姻費用の支払いを求める内容証明郵便を送付した時
とされるのが一般的であり、これ以前の期間についての請求は、原則として認められません。
このため、「長期間生活費を受け取っていなかった」という事情があっても、正式な請求をしていなかった期間分については、原則として婚姻費用を請求することはできないのが実情です。
重要なのは「早めに動くこと」
婚姻費用は、「困ってから請求する」よりも、「困り始めたらすぐ請求する」ことが重要です。対応が遅れるほど、受け取れる婚姻費用の期間は短くなってしまいます。
生活費の支払いが止まった、又は十分に支払われていない場合には、できるだけ早く内容証明郵便を送付するか、婚姻費用分担請求調停を申し立てることを検討しましょう。
ご自身のケースで過去分の請求が可能かどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。判断に迷われる場合には、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
「配偶者が勝手に家を出て行ったのに、なぜ生活費を支払わなければならないのか」
「配偶者の不貞が原因で別居しているのに、婚姻費用を払うのは納得できない」
このようなご相談を受けることは少なくありません。
しかし、配偶者が一方的に別居したように見える場合であっても、法律上の婚姻関係が継続している限り、原則として婚姻費用の支払義務は否定されません。
婚姻費用分担請求が否定されるのは、例外的な場合に限られます。
具体的には、婚姻費用を請求する側に不貞行為があり、その状態で支払いを認めることが信義則に反すると評価される場合です。
なお、請求する側に不貞行為があり、子を連れて別居している場合には、配偶者本人分の婚姻費用は否定されても、子の分については認められるのが一般的です。
もっとも、不貞行為の有無については、当事者間で争いになることが少なくありません。
家庭裁判所の実務では、婚姻費用は当面の生活費であることから、迅速な判断が重視され、不貞行為の有無について詳細な審理は通常行われません。
そのため、婚姻費用分担請求が信義則違反であると主張する場合には、
- 相手方が不貞行為を認めている
- 不貞行為を容易に認定できる客観的な証拠が存在する
といった事情が必要になります。
不貞行為の影響がどの程度婚姻費用に反映されるかは、事案ごとの判断となるため、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
別居中の妻から、「とても支払えない」と感じるような高額の婚姻費用を請求されることがあります。
このような場合、どのように対応すべきかについて、法律相談でよくご質問を受けます。
結論からいえば、一切支払わずに放置することは避けるべきです。
婚姻費用は、調停や審判で額が確定した際、これまでの未払分をまとめて支払う扱いとなるのが一般的であり、何も支払わずにいると、未払額がそのまま積み上がってしまいます。
そのため、請求額が不当に高いと感じる場合でも、ご自身の収入や生活状況から見て適正と考えられる金額を、暫定的に支払っておくことが実務上は望ましい対応と考えられます。
もっとも、適正な金額の判断は容易ではありません。誤った額を支払うと、後の調停で不利に評価されるおそれもあるため、事前に弁護士へ相談したうえで金額を判断することをおすすめします。
そのうえで、婚姻費用について争いがある場合には、相手方が婚姻費用分担調停を申し立て、家庭裁判所で適正な金額が判断されることになります。
これまで、配偶者の求めに応じて婚姻費用を支払い続けてきたものの、結果的に算定表の額より大幅に高額の支払いをしてきている、という方も少なくありません。
このような場合、支払い過多となっていた部分について返還を求めることができるのでしょうか。
この点について、実務上は、婚姻費用の「過払い」があったとしても、後から精算されるケースは多くありません。
婚姻費用は日々の生活費として支出・消費される性質のものであるため、特段の取り決めがないまま支払われていた場合には、「任意に履行されたもの」「すでに生活費として消費されたもの」と評価され、返還や清算の対象とはならないとされることが一般的です。
もっとも、当初から「最終的に清算する」という合意したうえで、暫定的に多めの金額を支払っていたような場合であれば後日精算が認められる余地はあります。
別居に際して、配偶者が預貯金などの財産を多く持ち出して行った場合、「その財産を生活費に充てればよく、あらためて婚姻費用を支払う必要はないのではないか」と感じられる方も少なくありません。
しかし、配偶者が別居時に持ち出した財産の取扱いは、原則として婚姻費用の問題ではなく、財産分与の場面で整理されるものと考えられています。
そのため、(不満が生じがちですが)配偶者の持ち出しがあったという事情だけで、婚姻費用の支払義務は当然に免れません。
もっとも、例外的に、
- 配偶者が持ち出した財産の金額や内容が明確であり
- その財産を配偶者が生活費として使用することについて、本人も同意している
といった事情がある場合には、その持ち出し額の範囲で、婚姻費用はすでに支払われたものとして評価される余地があります。
別居前・別居直後に講じておきたい予防策
そもそも、別居時の財産持ち出しを防ぐためには、次のような実務的対応が有効です。
- 家計を全面的に配偶者任せにしない
- 配偶者が口座から自由に払い出しが出来ないように管理方法を見直す
- 共同管理口座に過剰な残高を置かない
- クレジットカードの利用停止や利用枠の制限を行う
最終的な整理の場面について
財産の持ち出しが適法か違法かにかかわらず、最終的には、持ち出された財産は財産分与の中で清算されることになります。
突然、管理していた資産が無断で移動されれば、強い不安や憤りを感じるのは当然のことです。
しかし、冷静に状況を整理し、全体像を見据えて対応することが、結果としてより良い解決につながる場合が多いと言えるでしょう。
「後で清算すればよいのであれば、最終的な判断が出るまで婚姻費用を支払わないという選択もあり得るのではないか」と考えられる方もいらっしゃいます。
しかし、最終判断が出るまで婚姻費用を支払わないという対応には、一定のリスクが伴います。
まず、別居期間中に生活費の支払いが行われない状態が続くと、配偶者の生活基盤に直接的な影響を及ぼすことになり、その結果、離婚条件や財産分与などをめぐる話し合いが感情的にこじれ、交渉そのものが難航する可能性があります。
婚姻費用の判断そのものへの影響
さらに注意すべき点として、配偶者が生活費に不足が生じているにも関わらず、婚姻費用の支払いを一切行わない姿勢は、裁判所や配偶者から「任意の履行や柔軟な調整が期待できない」と受け取られる可能性があります。
その結果として、
- 婚姻費用の負担額が高めに判断される
- 支払方法について分割や猶予が認められにくくなる
といったように、最終的な判断内容に不利な影響が及ぶ可能性も考えられます。
暫定的な支払いをしておくことをお勧めします
後で清算する際に、既払いの婚姻費用は充当されますので損失にはなりません。
したがって、最低でも自身が妥当と考える金額を「暫定払い」であることを明示して支払っておくことをお勧めします。
4 収入・生活状況別の婚姻費用の考え方
婚姻費用の算定に用いられる算定表は、義務者の年収について、給与所得者は年収2,000万円まで、自営業者は年収1,567万円までを上限として作成されています。
そのため、義務者の年収がこれらの金額を超える場合には、算定表をそのまま当てはめることができません。
このような高額所得事案では、家庭裁判所の実務においても、一律の算定方法が確立されているわけではなく、事案ごとに判断されるのが実情です。
- 最高裁の標準算定方式で算出される最高額(算定表の上限額)とする見解
- 基礎収入の係数を修正して計算すべきとする見解
- 同居中の生活レベル、現在の生活レベル等を考慮して算出する見解
などがありますが、私の経験では、3の見解を元に「同居中の生活水準」「従前の生活費の負担状況」「高額な支出の有無や内容」など、一切の事情を総合的に考慮して裁判官の裁量で婚姻費用が算定されることが多いように感じます。
相手方の所得が高額な場合には、離婚時の財産分与額も高額になる可能性が高いことから、婚姻費用の算定方法や主張内容が、その後の手続にも影響を及ぼすことがあります。
そのため、このようなケースでは、早い段階から弁護士に依頼し、事案に即した適切な主張・立証を行うことが重要です。
配偶者の収入が年金のみである場合でも、双方が受給している年金額をそれぞれの収入として、婚姻費用を算定します。
年金は、性質上は給与に代わる収入であるため、婚姻費用の算定にあたっては、原則として給与所得者に準じた方法で扱われます。
もっとも、年金受給者は通常、実際に就労していないため、給与所得者に当然含まれる職業費(通勤費や業務関連支出など)は発生しません。
そのため、実務では、最高裁の標準算定方式に基づき、職業費を控除せずに基礎収入を算定する取り扱いが一般的です。
このように、年金収入をどのように評価するかは算定方式や前提条件の理解が必要となり、事案によっては算定結果に大きな影響が出ることもあります。
年金のみの収入で婚姻費用が問題となっている場合には、一度、弁護士に相談し、具体的な見通しを確認されることをおすすめします。
婚姻費用の分担について、「相手がすでに生活保護を受けているのだから、婚姻費用を支払う必要はないのではないか」というご相談を受けることがあります。
しかし、権利者が生活保護を受給していることだけを理由に、婚姻費用の分担義務が否定されたり、当然に減額されるわけではありません。
生活保護法は、まず本人がその収入や資産、能力を最大限活用して生活することを前提とし、そのうえで、配偶者や親族による扶助・扶養が優先される(親族扶養優先の原則)
と定めています。
つまり、婚姻関係にある配偶者による扶養(婚姻費用の分担)が第一次的に行われ、それでもなお生活が成り立たない場合に、はじめて生活保護が補完的に支給されるという位置づけになります。
そのため、婚姻費用の分担において、「相手が生活保護を受給しているから」という理由だけで、分担義務そのものを免れたり、当然に支払額を減額することはできません。
婚姻費用は、原則として直近年度の実際の収入額を基準に算定されます。
そのため、調停や協議の場で、「近い将来、収入が下がる見込みがある」として、婚姻費用を低くすべきだと主張されることがあります。
しかし、家庭裁判所の実務では、将来の減収に関する主張の多くが、業績の悪化や残業代の減少見込みなど、不確実な予測にとどまるとして、婚姻費用の算定に反映されることはほとんどありません。
婚姻費用は、あくまで現時点での収入状況を基準に判断されるのが原則です。
もっとも、婚姻費用の額が定まった後に、失業、病気、会社都合による大幅な減収など、当初は予測できなかった事情変更が生じた場合には、改めて婚姻費用の増額又は減額について話し合い、必要に応じて調停を申し立てることになります。
将来の収入変動が不安な場合でも、現時点ではどのように評価されるのか、事情変更が生じた場合にどのような対応が可能かについて、事前に専門家へ相談しておくことをおすすめします。
5 婚姻費用と他の制度との関係
児童手当は、「児童を監護し、かつ生計を同じくしている父または母のうち、児童の生計を維持する程度の高い者」に対して支給される制度です。
そのため、夫婦が同居している間は、収入の高い側の配偶者(多くの場合は父)が受給者となっているケースが一般的です。
【別居した場合の児童手当の扱い】
配偶者の一方が、子どもを監護して別居した場合には、婚姻費用の義務者(支払う側)は、児童を監護していないことになります。この場合、義務者は児童手当の受給要件を満たさなくなります。
したがって、別居後は速やかに、児童手当の受給者変更手続きを行う必要があります。具体的な手続き方法は自治体によって異なるため、早めに市区町村の窓口で相談することをおすすめします。
【切り替え前に支給された児童手当について】
別居後、児童手当の切り替えが行われる前に、義務者側に児童手当が支給されていた場合には、婚姻費用を請求する際に、未支給分として返還を求めることが可能です。
【婚姻費用との違いに注意】
児童手当は、「次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する」という政策目的に基づき支給される制度です。
そのため、夫婦間の扶助義務に基づく婚姻費用分担義務とは別の制度であり、両者を混同しないことが重要です。
なお、婚姻費用の算定にあたって、児童手当は収入として加算されません。
別居後、婚姻費用の支払義務者が住宅ローンを返済している自宅に、権利者(受け取る側)が引き続き居住している場合、「住宅ローンの支払額は、婚姻費用から控除されるべきではないか」というご相談を多く受けます。
しかし、住宅ローンの支払いは、原則として婚姻費用の算定にはそのまま反映されません。住宅ローンは本来、義務者自身の債務の返済であり、支払いには義務者の資産形成という側面もあるため、実務では、住宅ローンの全額を婚姻費用から控除する取扱いは採られていません。
もっとも、義務者が住宅ローンを支払っている不動産に、権利者が無償で居住している場合には、権利者は義務者の負担によって住居費の支出を免れていることになります。
そのため、家庭裁判所の実務では、算定表の標準的な婚姻費用に含まれている住居関係費相当額を控除する方法により、一定の調整を行うのが一般的です。
なお、この控除額は、住宅ローンの全額ではなく、ごく一部にとどまる点に注意が必要です。
標準算定方式による婚姻費用を支払いながら、自宅の住宅ローンを負担し、さらに自身の住居費も支払わなければならない場合、支払義務者(多くは別居により自宅を出た側)にとって、経済的な負担が大きくなるケースも少なくありません。
このような事情がある場合には、離婚を早期に実現することにより経済的負担を減らすことを検討することも必要となる場合があります。
婚姻費用は、原則として夫婦双方の収入額を基礎に算定されます。
そのため、現在専業主婦(主夫)であり、実際に収入がない場合には、収入は0円として算定されるのが原則です。
もっとも、家庭裁判所の実務では、「現在は無収入であっても、就労が可能と考えられる場合」には、一定の潜在的な稼働能力があるとして、一定の収入を認定することがあります。
具体的には、特段の制約がない場合、パート就労程度の収入が可能であるとして、年収約120万円前後を総収入として認定されるケースが見られます。
一方で、
- 権利者に障害がある場合
- 子どもが乳幼児であり、育児に専念せざるを得ない場合(目安として3歳以下)
などには、無収入とする取扱いもやむを得ないと判断されることもあります。
専業主婦の収入認定は、個別の事情によって結論が大きく異なるため、ご自身の状況でどのように評価されるかについては、専門家に確認することをおすすめします。
6 特殊なケース
婚姻費用の分担義務は、法律上の婚姻関係にある夫婦に限られるものではありません。
実務上は、実質的に夫婦同様の生活を営んでいる「内縁関係」にある場合にも、婚姻費用に準じた生活費の分担を請求できると考えられています。
もっとも、内縁関係であれば当然に請求が認められるわけではなく、
- 同居して家計を共通にしていたか
- 社会的に夫婦として認識されていたか
- 生活費を相互に分担する意思があったか
といった事情を総合的に考慮して、婚姻に準ずる実体があったかどうかが判断されます。
このような実体が認められる場合には生活費の分担請求が認められる可能性があります。
内縁関係にあたるかどうか、また、どの程度まで請求できるかは、事案ごとの事情によって大きく異なります。
請求を検討されている場合や、逆に請求を受けて困っている場合には、早めに弁護士に相談し、見通しを確認することが重要です。
法律相談のお申込みはこちら
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日