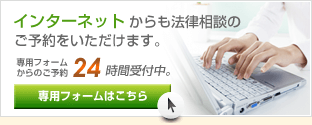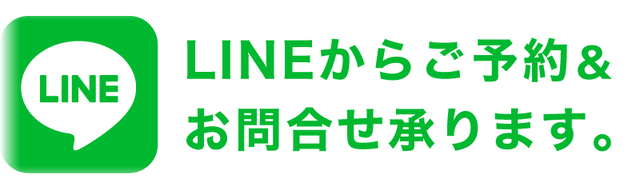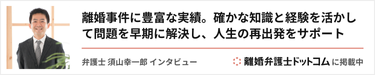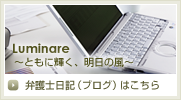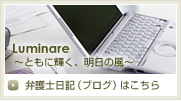弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
預金の引き出し・使い込み(使途不明金問題)
相続人の一人が故人の預金を使い込んでいた!
相続が開始し、遺産分割手続を進めるに際しては、被相続人名義の預貯金口座を確認するのが通常です。
その際、被相続人の生前に多額の引出行為がなされていることがあり、それを誰が引き出したのか、何に使ったのかが問題となることがあります。
特に、被相続人が長期にわたって寝たきり状態にあり、自分で引き出しに行くことが出来るような健康状態で無かったような場合や、引き出した額に見合う使途が想定出来ないような場合、被相続人の預金を管理していた相続人等が、自己のために費消したのではないかと疑念を持たれることになります。
当該相続人が、使途を示した資料を残していたり、説得的な説明が出来れば、他の相続人の疑問も解消するのでしょうが、そうでない場合には、感情的にも対立し、遺産分割協議が進まなくなります。
やむなく遺産分割調停を起こしても、使途不明金問題は調停では解決することが出来ないことから、調停の取り下げを勧告されたり、調停不成立となって審判移行してしまうこともあります。
審判手続においても、使途不明金問題は解決することが出来ませんので、別途民事訴訟(一般的には不当利得返還請求訴訟又は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)により解決しなければなりません。
被相続人が死亡する前に使い込みが行われた場合
相続人による預金の引き出し行為が、被相続人の意思に基づいて行われていたのであれば、それは贈与となりますので、遺産分割にあたっては、引き出した相続人の特別受益の有無が問題となります。「被相続人のために使った」という言い分が反論として主張される場合があります。
一方、預金の引き出し行為が、被相続人の意思に基づかないものであった場合には、被相続人は、預金を引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有していたことになりますので、各相続人は、これらの請求権を法定相続分に従って相続することになります。したがって、各相続人は、預金を引き出した相続人に対し、自己の相続分にあたる金額の返還を求めることが出来ます。
被相続人の意思に基づくものであったか否かは、明確に分からないことも多く、この点で紛争となることが多いのが実情です。
「被相続人のために使った」という主張が出た場合、被相続人が当該金額を使う必要と理由が証拠に基づき、合理的に説明出来るのかがポイントとなります。
遺産分割にあたって、この問題が生じた際に、預金を引き出した者が無断で払い出したことを認める場合には、払い戻しを受けた者が払戻金額相当の現金を保管・所持しているものとして処理することは可能です。
合意形成が出来ない場合には、訴訟又は特別受益の争いとなります。
被相続人が死亡した後に使い込みが行われた場合
被相続人の預金は、過去の判例(最判昭29.4.8)によると、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて当然に分割され、各自に帰属するとされていましたが、平成28年12月19日、最高裁は、銀行預金も遺産分割の対象となると判断を変更しました。
従って、今後は、相続人全員の合意が無い限り、銀行は個別の相続人からの払い戻し請求に応じることは無いものと考えられます。
仮に、銀行に被相続人の死亡を知られる前に、相続人の1人が、自分の法定相続分を超えて預金の引き出しを行った場合は、当該引き出し行為は他の相続人に対する不法行為又は不当利得となり、他の相続人は、預金の引き出しを行った相続人に対し、返還を請求することができます。
使い込みされた後に返還を求める方法
預金の引き出し・使い込みが発覚した場合、通常は、まず遺産分割協議の中で争われます。
遺産分割協議の中で、相続人が自ら使い込みを認め、使い込みの額を加算して協議により解決できればそれでよいのですが、相続人間で協議がまとまらない場合には、遺産分割調停ではなく、預金の引き出し行為について、民事訴訟等により返還を求めることになります。
返還を求めるためには、次のような資料が必要です。
預金の引き出し・使い込み行為は、相続・遺産分割問題の中で表面化してくることが多いと思われますが、厳密には、相続とは異なる問題となることが多く、引き出した相続人が使い込みを認めなければ、遺産分割では解決できず、裁判所も家庭裁判所ではなく、地方裁判所(又は簡易裁判所)で民事訴訟等で争わなければなりません。
遺産分割と並行して民事訴訟を行うのは、時間面・手続面・費用面のいずれも負担となります。
このため、和解により解決した方が望ましい場合も考えられます。
どのような方針で臨むのが良いかは、手持ちの資料等によりケースバイケースとなりますので、弁護士へのご相談をお勧めします。
よくあるケース
母の預金を母の死後、弟が勝手に払い戻して使い込んでいる
お母さまの預金は、相続人間で遺産分割を行い、原則として法定相続分により分配されるべきものです。使い込んだ預金の法定相続分について、弟に対し、不当利得返還請求訴訟又は不法行為に基づく返還請求訴訟を提起して返還を受けます。
認知症であった父の預金を、父の死亡前に勝手に払い戻して使い込んでいた
お父様の預金を勝手に使い込む行為は不法行為にあたります。使い込んだ預金の法定相続分について、弟に対し、不法行為に基づく返還請求訴訟を提起して返還を受けます。
父の死後、収益物件の賃料を弟が独り占めしている
被相続人の死亡後に発生する賃料収入は、死亡時には存在しなかったものですので、厳密には遺産ではありません。
しかしながら、通常は、収益を生み出す物件の遺産分割と併せて、協議により解決します。
協議により解決が出来ない場合には、弟に対し、不当利得返還請求訴訟を提起して解決を図ります。
使い込み金の返還請求代理サポート
法律相談のお申込みはこちら
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日