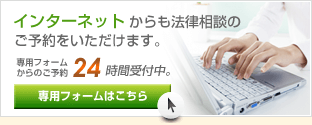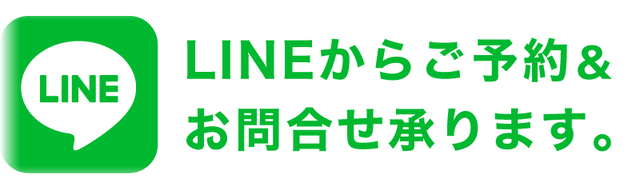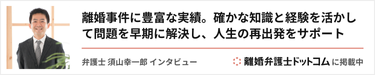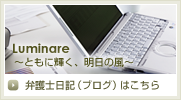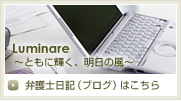兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
相続放棄でよくお受けするご質問
警察から「○○さん(父の名前)のご親族の方ですか」と電話がありました。聞くと、父は自宅で亡くなっていたそうです。
私は、昔両親が離婚した際、親権者となった母と暮らすことになり、父とは疎遠になり、20年以上どこで何をしているかも全く知りませんでした。今更関わり合いになりたくありません。相続放棄をしたいです。
相続放棄は可能ですが、注意点があります。
相続放棄は、相続開始を知ったとき(通常は被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に手続をしなければなりません(民法915条1項、938条)。
今回の電話で被相続人の死亡を知ったことになりますので、原則として警察の電話を受けた日から3か月以内に相続放棄の手続きを取れば、受理されます。
最後の住所地が分からなくても、弁護士に依頼すれば調査してもらえますし、ご自身で戸籍附票を取り寄せるなどして調べることも可能です。
もっとも、一度相続放棄をしてしまいますと、初めから相続人ではなかったことになり、相続権を失います。原則として取り消したり、撤回はできません。
後から、亡くなったお父様に相当額の遺産(預金や不動産など)があったことが分かった場合、後悔することにもなりかねません。
したがって、亡くなられたお父様の財産関係について3か月をかけて調査してから相続放棄をすることも選択肢としてあり得ます。
3か月では足りない場合は、「熟慮期間の伸長」の手続きをとれば、調査期間の延長も可能です。
「プラスの財産があっても、もう20年以上も関係が無かった以上、たとえプラスの財産があったとしても後悔しない。むしろとにかく関わりたくない」という場合には、直ちに相続放棄の手続きを取ると良いでしょう。
先日、聞いたこともない役所の福祉課から連絡文が届きました。内容は、母が亡くなったということ、遺骨の引き取り、滞納していた税金があるので連絡が欲しいというものでした。
母とは折り合いが悪く、長年にわたって疎遠であり、どこでどのような生活をしていたかも知りませんでした。
しかし、折り合いが悪かったとはいえ、親の遺骨を受け取らないというのは忍びなく、連絡して受け取ろうと思っています。
ただ、滞納していた税金がかなりあるとのことで、相続放棄を考えていますが、遺骨を受け取っても大丈夫でしょうか。
遺骨を受け取っても相続放棄は可能ですが、注意点があります。
遺骨は、「相続財産」ではなく、「祭祀財産」と考えられており、遺骨を引き取っても相続放棄は可能です。位牌や仏壇も同様です。
税金を滞納していたとなると、負債超過の可能性も高いものと思われます。
ただ、相談例1と同様、一度相続放棄をしてしまいますと、初めから相続人ではなかったことになり、相続権を失います。取り消すことができませんので、亡くなられたお母様の財産関係について3か月をかけて調査してから相続放棄をすることも選択肢としてあり得ます。
「プラスの財産があっても、もう20年以上も関係が無かった以上、たとえプラスの財産があったとしても後悔しない。むしろとにかく関わりたくない」という場合には、直ちに相続放棄の手続きを取ると良いでしょう。
先日、聞いたこともない役所の建設管理課から通知書が届きました。内容は、添付されている写真の建物が老朽化しており危険な状態にあること、通行人が事故に遭う危険があることから確認して対応をお願いしたい、通知書は建物所有者の共同相続人全員に送付している、というものでした。
しかし、私は記載されていた建物所有者と面識がなく、相続関係があるかどうかも分かりません。
おそらく建物所有者の方は、相当昔に亡くなられたものと思われますが、相続放棄して対応を免れることは出来ますか?
相続放棄は可能です。但し、被相続人が死亡して相続開始してから3か月以上経過していることが通常ですので、適切な対応が必要です。
通知を放置すると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
また、建物が建っている土地の固定資産税が安くなる「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が高くなる可能性もあります。
行政が「行政代執行」を行った場合、その費用を請求される可能性もあります。
相続放棄を検討している方は早急に専門家の相談を受けましょう。
近年、老朽化した空き家が社会問題化しています。
平成27年に空き家等対策特別措置法が施行され、行政は、空き家を適切に管理していない所有者に対し、助言・指導・勧告を行うことが出来るようになりました。
今回届いた通知書は、上記経緯から送付されたものと思われます。
相続放棄をした場合、その相続については、初めから相続人とならなかったとみなされます(民939条)。
相続放棄をした者が相続財産の管理をしている場合には、速やかに他の相続人等に引き継がなければなりません。
他の相続人等に引き継ぐまでは、相続財産の管理者が不在とならないよう、自己の財産と同様の注意をもって管理を継続しなければなりません(民940条1項)。つまり管理義務を負い続けます。
相続財産の管理を引き継ぐことが出来ない、または全員が相続放棄をして相続人不存在となったような場合には、そのまま管理を継続していくか、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行い、相続財産管理人に管理を引き継ぐことを検討することになります。
相続放棄が家庭裁判所に受理されたからと言って、必ずしも空き家を放ったらかしには出来ないということに注意が必要です。
民法改正(令和5年4月施行)
従前までは上記のような説明が行われてきましたが、相続放棄をした場合の管理義務について、令和5年4月1日施行の改正民法では以下の規定に改正され、管理義務者が明確化されることになりました。
改正民法940条1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
上記の改正により、空き家を現に占有していない方が相続放棄を行った場合、管理(保存)義務を負わないこととなり、改正により負担が軽くなったといえます。
ご相談のケースでは、全く見ず知らずの方の建物の話であり、占有もしていませんので、義務を負いません。
相続放棄の手続きを行っておいた方が無難と思われます。
ただ、相続放棄を行った場合、空き家の管理義務や借金・滞納税金等のマイナスの財産を相続することは無くなりますが、プラスの財産があった場合、それも相続できなくなりますので注意が必要です。
また、ご質問のような通知書が届いたケースは、被相続人が死亡してから3か月以上経過しているため、相続放棄申述書に適切な内容の上申書を付ける必要があるほか、そもそも相続を繰り返して相続人が多数になっていることが通常で、相続人調査が困難であることが多いようです。
したがって、最初から専門家に依頼して相続人調査と上申書の作成を行ってもらうことをお勧めします。
先日父が病院で亡くなりました。3か月ほど入院し、入院費と治療費などの支払が残っており、先日請求書が届きました。
父は多額の連帯保証をしていたため、相続放棄をすることを考えているのですが、入院費を支払ってしまっても大丈夫でしょうか。
相続放棄を考えているなら、支払いを行わない方が無難です。
債務の弁済については、こちらの「既に支払ってしまった場合の相続放棄」にご説明しておりますとおり、単純承認とされてしまうリスクがあります。
「故人の生前の入院費だから故人の預貯金から支出しても大丈夫」と思いがちですが、入院費も他の負債と同様に被相続人の負債にすぎません。
しかし、生前、故人が医師や看護師さんにお世話になった病院に、入院費を支払わないというのは道義的にしのびないというお考えの方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、故人の財産からではなく、ご自身の財産から支払うようにしましょう。
既に入院費を支払ってしまったという場合でも、その額や諸般の事情で相続放棄が認められるケースもございますので、一度ご相談にお越し頂ければ、ケースごとの助言をさせて頂けます。
法律相談のお申込みはこちら
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚サービス案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 家族信託
- 成年後見制度
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日