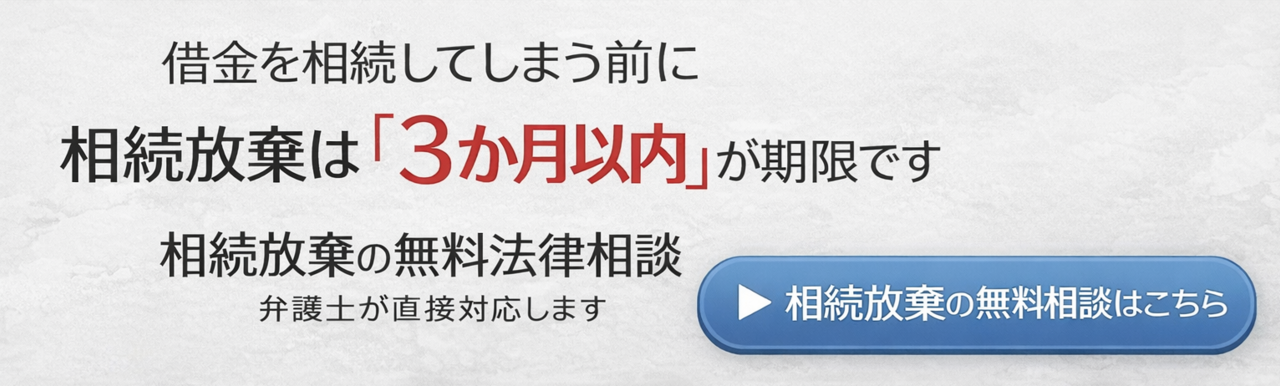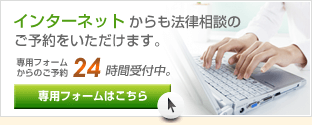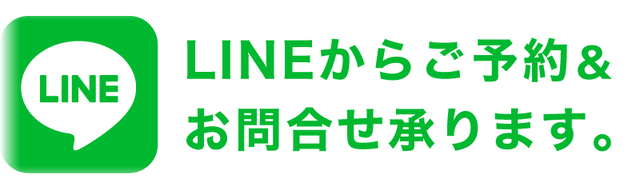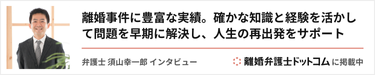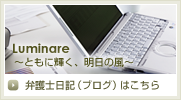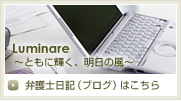弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
相続放棄は専門用語や手続きが多く、初めての方には分かりにくい手続きです。
- 「期限に間に合うか不安…」
- 「どこまで調べればいいのか分からない…」
- 「家族に負担を残したくない…」
そんな方のために、このページでは相続放棄の基礎知識を丁寧に整理しました。
不安な点や判断に迷う部分があれば、ページ内の解説とあわせて、一度専門家にご相談ください。
1.相続放棄の基本に関する質問
- 相続放棄とは何ですか?
- 相続放棄をすると、どのような影響がありますか?
- 相続放棄をするかどうかを判断するためのポイント
- 相続放棄と「相続の辞退」の違いは何ですか?
- 相続放棄は、どこで手続きを行いますか?
- 相続放棄は、一部の財産だけ行うことはできますか?
- 相続放棄が出来なくなる単純承認とは?
- よくある誤解-これは「処分行為」になる?ならない?
- 既に支払ってしまった場合でも相続放棄はできますか?
- 相続放棄と「相続分の無いことの証明書」の違いは何ですか?
- 相続放棄をすると官報に掲載されますか?
- 相続放棄は戸籍や住民票に記載されますか?
- 生前(被相続人が生きている間)に相続放棄はできますか?
- 被相続人が連帯保証人だった場合、相続放棄はできますか?
- 相続放棄をしても、お墓・お仏壇は承継できますか?
- (相談例:1)故人と長年疎遠だった場合の相続放棄
- (相談例:2)役所から滞納税金・遺骨の引取りの連絡が来ました
2.相続放棄の手続に関する質問
3.相続放棄の期限に関する質問
4.相続放棄と他の相続人との関係に関する質問
5.相続放棄と負債・財産に関する質問
6.相続放棄の取り消し・無効に関する質問
7.相続放棄をした後に関する質問
8.相続放棄と税金に関する質問
9.相続放棄と関連する制度
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、プラスの財産・マイナスの財産を含めて一切引き継がない ための制度です。
通常、人が亡くなると、その人が持っていた すべての権利と義務 は相続人に引き継がれます。
これは預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
- 借金
- ローン
- 連帯保証債務
といった マイナスの財産も例外ではありません。
そのため、被相続人が多額の借金を残したまま亡くなった場合、何も手続きをしなければ、相続人がその返済義務を負うことになります。
しかし、このような結果は相続人にとってあまりに過酷です。
そこで、民法は 相続人を守るための制度として「相続放棄」 を認めています。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続について 「最初から相続人ではなかったもの」と法律上みなされます。
その結果、
- 借金や連帯保証債務を負うことはありません。
- 債権者から返済を求められることもありません
- 遺産分割協議に参加する必要もなくなります
ただし、プラスの財産も一切相続できなくなる 点には注意が必要です。
「借金があるかもしれない」「相続していいのか判断がつかない」
このような場合は、早めに相続放棄を検討することが極めて重要です。
相続財産の内容を確認する
まずは、被相続人の相続財産を把握することが重要です。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産がないかを確認しましょう。
特に、被相続人との関係が希薄だった場合には、知らない借金が後から発覚するリスクもあります。
将来のリスクを避ける目的で、相続放棄を選択される方も少なくありません。
相続放棄が出来る期限を確認する
相続放棄は、「相続の開始を知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
期限直前では手続きが間に合わないこともあるため、早めに検討・行動することが大切
です。
弁護士に依頼する場合には、期限の1か月前までを目安にご相談いただくことをおすすめします。
他の相続人への影響を考える
自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
法律上、相続放棄をしたことを次順位の相続人に通知する義務はありませんが、状況によっては事前に話し合いをしておく方が円滑な場合もあります。
全員が相続放棄をするのか、一部の相続人が相続するのかを判断する必要が生じることもあります。
当事務所では、次順位・次々順位の方の相続放棄についても、まとめてご相談・ご依頼いただくことが可能です(申述は、法定の順位に従って順次行います)。
相続放棄をした場合のデメリットも理解する
相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金・不動産・有価証券・車両などのプラスの財産も一切相続できなくなります。
また、相続放棄をしても、遺骨や仏壇などの祭祀財産については、別途対応を検討する必要が生じる場合があります。
さらに、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることを検討しなければならないケースもあります。
自分で進めるか、専門家に依頼するかを判断する
相続放棄の判断や、戸籍の収集、裁判所への申述書作成が難しいと感じた場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、必要資料の収集から申述書の作成、裁判所とのやり取りまで一貫して任せることができ、手続きをスムーズに進められます。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行うことで、法律上「最初から相続人ではなかった」と扱われる制度です。
相続放棄が認められると、借金などの負債(マイナスの財産)を含め、一切の相続をしないことになります。
一方で、「相続の辞退」という言葉は法律上の制度ではありません。
単に「相続しません」と意思表示をするにすぎず、それだけでは相続人としての地位を失うことはできません。
そのため、相続放棄の手続きをしていない場合には、たとえ相続を辞退したつもりであっても、借金などの負債は相続してしまう点に注意が必要です。
また、プラスの財産についても、実際に取得しないためには遺産分割協議を行うか、相続分の放棄や譲渡などの手続きを別途行う必要があります。
相続放棄を検討している場合でも、一定の行為をしてしまうと、法律上「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
単純承認とは、被相続人の財産や負債をすべて相続することを意味し、いったん成立すると、後から相続放棄をすることはできません。
①相続財産の「処分行為」をしてしまった場合
相続人が、相続財産の全部または一部を「処分」した場合には、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。
相続放棄を考えている場合には、相続財産の取り扱いには特に注意が必要です。
処分行為に該当する代表例
- 被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更
- 被相続人名義の不動産の売却や名義変更
- 相続財産を換金して使用すること
処分行為に該当しないと考えられる例(例外)
- 社会通念上相当な範囲での葬儀費用の支出
- 預金を引き出したものの、費消せずに保管している場合
②判断が分かれやすい行為(要注意)
- 賃貸住宅の解約、名義変更
- 携帯電話や公共料金の解約、
- 遺品整理、車の処分、
- 入院費用や税金の支払い、
- 形見分け
などについては、ケースごとに判断が分かれるため注意が必要です。
これらは、
- 「処分行為」にあたるのか
- 問題のない「保存行為」にとどまるのか
という点で評価が分かれます。
③判断のポイント
判断のポイントは、主に次の2点です。
- 財産の価値を変動・消滅させる行為か(処分行為か)
- 客観的な経済的価値のある財産かどうか
具体例
- 倒壊しそうな塀の補修 → 保存行為
- 建物全体の解体や売却 → 処分行為となる可能性が高い
- 写真やアルバムなど経済的価値のない遺品の形見分け → 問題になりにくい
- 高額な腕時計や指輪など → 処分行為と判断される可能性あり
④相続財産の隠匿・消費
相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、私的に消費した場合には、単純承認とみなされることがあります。
この場合、債権者などから相続放棄の無効を主張されるおそれがあります。
⑤迷った場合の重要な注意点
被相続人の財産について、何らかの処理をしようと考えている場合には、実行する前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。
一度行ってしまった行為は、後から取り消すことができません。
相続放棄を検討している方から、特に質問の多い行為を整理しました。
※最終的な判断は個別事情によります。
×処分行為と判断される可能性が高い例(要注意)
- 被相続人名義の預貯金を引き出して生活費などに使った
- 預貯金を解約し、自分の口座に移した
- 不動産や車を売却した、名義を変更した
- 貴金属・腕時計などを換金した
- 財産の一部を自分のものとして使った
これらは、「財産の価値を消滅・移転させる行為」として、単純承認とみなされるおそれがあります。
〇処分行為に当たらないと考えられることが多い例
- 社会通念上相当な範囲での葬儀費用の支出
- 預貯金を一時的に引き出したが、使わずに保管している
- 倒壊防止など最低限の補修を行った
- 公共料金や携帯電話を解約した
- 写真やアルバムなど経済的価値のない遺品の整理
財産価値を維持するための「保存行為」にとどまる場合は、処分行為と評価されないことがあります。
△判断が分かれやすい行為(特に注意)
- 賃貸住宅の解約や原状回復、名義変更
- 車の廃車や引渡し
- 入院費や税金の支払い
- 形見分け
- 遺品の中に価値のあるものが混在している場合
判断の基本ルール(覚えておくべきポイント)
- 財産の価値を減らしたり、移転させていないか
- 客観的な経済的価値のある財産かどうか
迷った場合の重要な注意点
相続放棄を検討している段階で、被相続人の財産について何らかの対応が必要な場合には、必ず行動する前に弁護士へご相談ください。
一度行ってしまった行為は、後から取り消すことができません。
被相続人が負っていた借金や滞納税金を相続人が支払った場合、それが「処分行為」に当たり、相続放棄ができなくなるのかは、実務上よく問題となります。
自分の財産で支払った場合
相続人が、自分自身の財産(自己資金)で被相続人の債務を弁済した場合には、一般に「保存行為」に当たり、相続財産の処分には該当しないと解されています。
実際に、福岡高等裁判所は、「期限の到来した被相続人の債務について、相続人が自己資金で弁済する行為は、相続財産の処分行為には当たらない」と判断しています(福岡高決・平成10年12月22日)。
被相続人の財産から支払った場合
一方、被相続人の預貯金など、相続財産から債務や税金を支払った場合には、その行為自体が「相続財産の処分」と評価され、単純承認とみなされてしまう可能性があります。
リスクを避けるたけの実務上の注意点
相続放棄を検討している状況で支払いが必要な場合には、被相続人の財産ではなく、必ず自己資金から支払うようにし、自分の口座から支払ったことが分かる資料(振込明細など)を残しておくことが重要です。
すでに相続財産から支払ってしまった場合
すでに相続財産から債務や税金を支払ってしまった場合でも、その債務の性質や金額、支払いの必要性などによっては、保存行為と評価され、相続放棄が認められる余地が残ることもあります。
具体的な事情によって判断が分かれるため、「もう相続放棄はできない」と決めつけず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けており、その金額が法定相続分を上回っている方がいある場合、相続手続の一環として「相続分の無いことの証明書」を作成することがあります。
例えば、相続人が2名の場合、そのうち1名が「相続分の無いことの証明書」(実印の押印と印鑑証明書の添付)を提出することで、もう一方の相続人が単独で相続登記を行うことが可能になります。
ただし、「相続分の無いことの証明書」を作成したからといって、その相続人が「相続放棄」をしたことにはなりません。この点を誤解されている方は少なくありませんので注意が必要です。
「相続分の無いことの証明書」は、あくまで登記などの手続きを進めるための書類にすぎず、相続人としての地位を失うものではありません。
そのため、被相続人に借金や保証債務などの負債があった場合でも、この証明書を作成しただけでは、負債の支払義務を免れることはできません。
負債を含めた相続を一切引き継がないためには、家庭裁判所で正式に「相続放棄」の手続きを行う必要があります。
相続放棄は、被相続人が亡くなった後にのみ行うことができる手続です。相続開始前、つまり被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
たとえ被相続人が多額の借金を抱えており、将来、相続放棄をすることが確実な状況であっても、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行えるのは、相続が開始した後に限られます。
よく混同される制度:「遺留分の放棄」との違い
相続放棄と似た制度として「遺留分の放棄」がありますが、この2つは全く異なる制度です。
遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得ることで、被相続人の生前に行うことができます。
ただし、放棄できるのは「遺留分」に限られ、相続人としての地位そのものを失うわけではありません。
遺留分の放棄が利用される典型例としては、例えば、被相続人が遺言によって長男に事業を承継させる予定である場合に、他の相続人へ生前贈与を行ったうえで、あらかじめ遺留分の放棄手続きをしてもらうことで、相続開始後の紛争を予防するといったケースが考えられます
被相続人が、第三者の借金について連帯保証人になっていた場合でも、相続放棄をすれば、その連帯保証債務を相続することはありません。
連帯保証債務も、借金と同様に相続財産の一部であるため、相続放棄によって一切引き継がないことになります。
しかし、被相続人が誰かの保証人になっていても、それを家族に知らせていないこともあり、相続開始後、長期間が経過したのち、突如債権者から督促が来たことで保証債務の存在が発覚することがあります。
このような場合には、保証債務の存在を知った時(督促状を受け取った時)から3か月以内であれば、相続放棄の申述が受理される可能性があります。
裁判所の審理も慎重になりますので、このような場合には、弁護士にご相談・ご依頼なさることをお勧めします。
一方、相続人自身が、被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合には、相続放棄をしても、自身の連帯保証債務は残ります。
相続開始後に保証債務が発覚した場合
被相続人が連帯保証人になっていたことを、家族が知らないまま相続が開始し、長期間経過した後に、突然債権者から督促が届くことで保証債務の存在が判明するケースも少なくありません。
このような場合には、保証債務の存在を知った時点(通常は督促状を受け取った時)から3か月以内であれば、相続放棄の申述が受理される可能性があります。
ただし、通常のケースよりも裁判所が慎重に判断する傾向があるため、このような事情がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
【注意】相続人自身が連帯保証人になっている場合
一方で、相続人自身が、被相続人の借金について連帯保証人になっていた場合には、相続放棄をしても、その連帯保証債務は免れません。
これは、保証人としての義務が、相続とは別に、相続人本人の責任として発生しているためです。
警察から「○○さん(父の名前)のご親族の方ですか」と電話がありました。聞くと、父は自宅で亡くなっていたそうです。
私は、昔両親が離婚した際、親権者となった母と暮らすことになり、父とは疎遠になり、20年以上どこで何をしているかも全く知りませんでした。今更関わり合いになりたくありません。相続放棄をしたいです。
相続放棄は可能ですが、注意点があります。
相続放棄は、相続開始を知ったとき(通常は被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に手続をしなければなりません(民法915条1項、938条)。
今回の電話で被相続人の死亡を知ったことになりますので、原則として警察の電話を受けた日から3か月以内に相続放棄の手続きを取れば、受理されます。
最後の住所地が分からなくても、弁護士に依頼すれば調査してもらえますし、ご自身で戸籍附票を取り寄せるなどして調べることも可能です。
もっとも、一度相続放棄をしてしまいますと、初めから相続人ではなかったことになり、相続権を失います。原則として取り消したり、撤回はできません。
後から、亡くなったお父様に相当額の遺産(預金や不動産など)があったことが分かった場合、後悔することにもなりかねません。
したがって、亡くなられたお父様の財産関係について3か月をかけて調査してから相続放棄をすることも選択肢としてあり得ます。
3か月では足りない場合は、「熟慮期間の伸長」の手続きをとれば、調査期間の延長も可能です。
「プラスの財産があっても、もう20年以上も関係が無かった以上、たとえプラスの財産があったとしても後悔しない。むしろとにかく関わりたくない」という場合には、直ちに相続放棄の手続きを取ると良いでしょう。
先日、聞いたこともない役所の福祉課から連絡文が届きました。内容は、母が亡くなったということ、遺骨の引き取り、滞納していた税金があるので連絡が欲しいというものでした。
母とは折り合いが悪く、長年にわたって疎遠であり、どこでどのような生活をしていたかも知りませんでした。
しかし、折り合いが悪かったとはいえ、親の遺骨を受け取らないというのは忍びなく、連絡して受け取ろうと思っています。
ただ、滞納していた税金がかなりあるとのことで、相続放棄を考えていますが、遺骨を受け取っても大丈夫でしょうか。
遺骨を受け取っても相続放棄は可能ですが、注意点があります。
遺骨は、「相続財産」ではなく、「祭祀財産」と考えられており、遺骨を引き取っても相続放棄は可能です。位牌や仏壇も同様です。
税金を滞納していたとなると、負債超過の可能性も高いものと思われます。
ただ、相談例1と同様、一度相続放棄をしてしまいますと、初めから相続人ではなかったことになり、相続権を失います。取り消すことができませんので、亡くなられたお母様の財産関係について3か月をかけて調査してから相続放棄をすることも選択肢としてあり得ます。
「プラスの財産があっても、もう20年以上も関係が無かった以上、たとえプラスの財産があったとしても後悔しない。むしろとにかく関わりたくない」という場合には、直ちに相続放棄の手続きを取ると良いでしょう。
相続放棄を自分で行う場合には、次のような実費がかかります。
- 戸籍謄本や住民票などの取得費用
- 家庭裁判所に提出する申述書に貼付する収入印紙(800円)
- 裁判所からの連絡用の郵便切手(800円程度)
このほかに高額な費用がかかることはなく、実費は数千円程度に収まるのが一般的です。
一方、弁護士に依頼する場合には、上記の実費に加えて弁護士費用が必要となります。
弁護士費用は事務所によって異なりますが、相続放棄1名あたり、おおむね5万円〜15万円程度が目安ではないかと考えられます。
費用を比較する際の注意点(補足)
費用だけでなく、
- 取り扱い件数
- 戸籍収集や書類作成をどこまで任せられるか
- 期限が迫っている場合の対応
- 万一、不受理となった場合の取り扱い
といった点も含めて確認することが大切です。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったとき(通常は被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
相続放棄に必要となる書類は、概要、次のとおりです。
一般的に必要となる書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所に備え付けの様式があり、裁判所のウェブサイトからダウンロードも可能です)
- 相続放棄をする方(相続人)の戸籍謄本
- 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本
- 収入印紙(申述人1名につき800円)
- 予納郵便切手(裁判所により異なりますが、800円分程度を求められることが多い)
【注意】実際には「追加書類」が必要になることも少なくありません。
上記はあくまで基本的な書類であり、相続人の立場や被相続人との関係によって、追加の戸籍や資料の提出を求められることがあります。
特に、次のような場合には、必要書類の判断や収集が複雑になりがちです。
- 代襲相続が発生している場合
- 相続開始から時間(3か月以上)が経過している場合
- 相続人の数が多い場合
- 被相続人との関係が複雑な場合
弁護士に相続放棄を依頼した場合には、必要書類の判断から戸籍の収集、申述書の作成、裁判所とのやり取りまで、一連の手続きを任せることができます。
期限が迫っている場合や、書類不備によるやり直しを避けたい場合には、弁護士への依頼が有効かもしれません。
①相続開始と期限の確認(熟慮期間)
相続放棄は、相続の開始を知ったとき(通常は被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内に行う必要があります。
この3か月は、相続放棄をするかどうかを判断するための期間(熟慮期間)です。
②必要書類の準備
相続放棄をするためには、相続放棄申述書や戸籍謄本などの必要書類を準備します。
相続関係によっては、追加書類が必要になることもあります。
③家庭裁判所へ申述書を提出
必要書類をそろえ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
④裁判所からの照会・確認(ある場合)
書類提出後、家庭裁判所から照会書が郵送されたり、事情確認のために呼び出されることがあります。
照会書では、
- 相続を知った時期
- 債務の内容を知った時期
- 相続財産を処分していないか
- 本当に相続放棄の意思があるか
といった点について、簡単な質問がされるのが一般的です。
照会書が届いた場合には、指定された期限内に回答書を提出する必要があります。
⑤相続放棄の受理
裁判所が内容を確認し、問題がなければ、相続放棄が正式に受理されます。
申述書の提出から、おおむね1か月程度で受理通知書が届くのが一般的です
期限内に判断できない場合・期限を過ぎた場合
熟慮期間内に判断ができない場合には、家庭裁判所に申立てを行い、熟慮期間を延長してもらうことができます(期間伸長の申立て)。
また、被相続人の死亡から3か月を経過していても、事情によっては相続放棄が認められることがあります。
期限を過ぎたからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
弁護士に相談するタイミング
当事務所に依頼される方は、圧倒的に①の期間内で、相続開始2週間~1か月程度の方が多いです。
- 期限が迫っている場合
- 被相続人の借金や保証債務が後から発覚した場合
- 書類の準備や裁判所対応に不安がある場合
このような場合には、早めに弁護士へ相談することで、手続上のリスクを減らすことができます。
相続放棄は、一定の要件を満たしていない場合、家庭裁判所に受理されないことがあります。
代表的なケースは、次のとおりです。
①相続財産を処分してしまった場合(単純承認)
相続財産の全部または一部を処分してしまうと、法律上「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
例えば、
- 預貯金を引き出して使った
- 不動産や車を売却した
- 価値のある遺品を換金した
といった行為は、処分行為と判断される可能性があります。
②相続放棄の期限(3か月)を過ぎている場合
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎた場合、原則として相続放棄は認められません。
ただし、借金や保証債務の存在を後から初めて知った場合など、事情によっては例外的に認められることもあります。
③相続放棄の意思が明確でない場合
家庭裁判所は、本当に相続放棄をする意思があるかどうかを確認します。
照会書への回答内容が不十分であったり、説明があいまいな場合には、相続放棄が受理されないことがあります。
④照会書、電話照会や呼び出しに適切に対応しなかった場合
家庭裁判所から照会書が送られたり、事情確認のために呼び出されることがあります。
これに対応しなかったり、期限内に回答をしなかった場合には、相続放棄が受理されないことがあります。
⑤書類の不備が補正されない場合
書類に不備があっても、通常は補正の機会が与えられますが、指示された補正が行われない場合には、相続放棄が受理されないことがあります。
自分は無理だとあきらめる前に
相続放棄が認められるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれることがあります。
「もう無理だ」と自己判断せず、一度は弁護士に相談することで、例外的に認められる可能性が見つかることもあります。
相続放棄の手続きには、実印の押印や印鑑証明書の添付は必要ありません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行う手続であり、印鑑証明書を提出する場面はありません。
「印鑑証明書を送ってほしい」と言われた場合の注意点
法律相談の際、「相続放棄をしておくから」と言われて、他の相続人から印鑑証明書の提出を求められた、という相談を受けることがあります。
しかし、相続放棄のために印鑑証明書を提出する必要はありません。
このような場合には、印鑑証明書が何の手続に使われるのかを、必ず確認することが大切です。
相続放棄ではない手続の可能性
印鑑証明書が必要になる手続としては、次のようなものがあります。
- 相続分の譲渡
- 遺産分割協議書の作成
これらはいずれも、家庭裁判所で行う相続放棄とは別の手続です。
注意すべきポイント(重要)
「相続分の譲渡」や遺産分割をしても、借金などの負債については、相続分に応じて原則として引き継ぐことになります。
負債を含めた相続を一切引き継がないためには、家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きを行う必要があります。
【ご相談例】
夫が亡くなり、妻である私と子どもが相続人です。子どもは未成年ですが、相続放棄はどのようにすればよいですか?
原則:親権者が代理して相続放棄を行う
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が未成年者の法定代理人として、相続放棄の手続きを行うのが原則です。
注意:利益相反となるケースがあります
ただし、親権者と未成年者が同時に相続人となる場合には、注意が必要です。
例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続人となった場合に、妻が子を代理して相続放棄をすると、子は最初から相続人でなかったことになります。
その結果、妻の相続分が増えることになり、親権者(妻)と未成年者(子)の利益が対立する「利益相反」の関係にあたる場合があります。
このような利益相反がある場合には、原則として、未成年者について家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
例外:特別代理人が不要なケース
もっとも、次のような場合には、利益相反にはあたらず、親権者が法定代理人として未成年者の相続放棄を行うことができるとされています。
- 親権者が先に自ら相続放棄をした後、未成年者の代理として放棄する場合
- 親権者自身の相続放棄と、未成年者の相続放棄を同時に行う場合
未成年者の熟慮期間(3か月)の起算点
未成年者が相続放棄をする場合の熟慮期間(3か月)は、未成年者本人ではなく、親権者が未成年者のために「相続の開始を知った時」から起算されます。
注意点(重要)
親権者だけが相続放棄をし、未成年者の相続放棄を忘れてしまうと、未成年者が被相続人の借金を相続してしまいます。
必ず、未成年者についても相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄については、事前に相続財産や負債の内容を詳しく調べていなくても、ご相談いただくことが可能です。
- 「相続放棄をすべきかどうか迷っている」
- 「自分の状況で相続放棄が認められるのか不安」
といった段階でのご相談も、もちろんお受けしています。
ご相談の中では、相続放棄が家庭裁判所に受理される可能性についての見通しや、相続放棄をすると決めた場合に注意すべき点について、具体的な助言を行います。
最終的に相続放棄をするかどうかの判断は、ご本人にしていただくことになりますが、判断に必要な情報は分かりやすくお伝えします。
弁護士費用については、ご依頼の前に必ず明確にご説明し、当事務所では、ホームページに記載の料金体系に基づいてご案内しています。費用を明示しないまま手続きを進めることはありませんので、安心してご相談ください。
複数の相続人がいる場合には、まとめてご依頼いただくことも可能です。その際には、内容に応じて費用の調整を行うこともあります。
相続放棄をご依頼いただいた場合には、戸籍等の必要書類の収集から、申述書の作成、裁判所とのやり取りまで、相続放棄に関する手続きを一貫して代行します。
相続放棄ができる期間は、民法上「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められています。
この3か月の期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。
熟慮期間の進み方(重要な前提)
相続人が複数いる場合でも、熟慮期間は一斉に進行するわけではありません。
熟慮期間は、相続人一人ひとりについて、それぞれ別々に進行します。
原則:多くの場合は「死亡を知った時」から
多くのケースでは、被相続人が亡くなったことを知った時点で、熟慮期間が開始します。
例外①:死亡や債務を後から知った場合
被相続人と疎遠であった場合や、長年連絡が取れていなかった場合などには、被相続人の死亡そのものを知らないことがあります。
この場合、被相続人の死亡や借金の存在を債権者や自治体からの督促状によって初めて知ることも少なくありません。
このようなときは、死亡の事実や債務の存在を知った時点から熟慮期間が開始します。
ただし、客観的には死亡から3か月以上経過しているため、相続放棄をする際には、「いつ、どのように知ったのか」を裁判所に対して具体的に説明する必要があります。
※ 督促状や消印のある封筒などは、必ず保管しておきましょう。
例外②:後順位相続人の場合(直系尊属・兄弟姉妹など)
直系尊属(父母・祖父母)や兄弟姉妹は、子がいない場合などに初めて相続人となる後順位の相続人です。
そのため、被相続人が亡くなった事実を知っただけでは、ただちに自分が相続人になったと認識しないこともあります。
【先順位相続人がいないと知っていた場合】
この場合には、被相続人の死亡を知った時点で、熟慮期間が開始します。
【先順位相続人がいると思っていた場合】
先順位の相続人が存在し、その人が相続放棄をするまでは、後順位相続人は相続人になりません。
このため、先順位相続人が相続放棄をしたことを知った時から、熟慮期間が開始します。
※先順位相続人には、後順位相続人に対し、相続放棄を通知する義務はありません。
「3か月を過ぎたら絶対に無理」ではありません
相続財産が全く存在しないと信じていたなど、特別な事情がある場合には、例外的に熟慮期間の起算点が後ろにずれることがあります。
最高裁判所も、相続財産が存在しないと信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の存在を認識した時点から熟慮期間が開始すると判断しています。
また、一部の財産は認識していたものの、後になって予想外の多額の負債が判明した場合など、個別事情によって判断が分かれるケースもあります。
このような場合は、専門家への相談が重要です。
熟慮期間の起算点について裁判所に説明が必要な場合には、事情説明書や上申書の内容が重要になります。
このようなケースでは、弁護士に依頼し、事情に即した説明書面を作成することが、相続放棄を認めてもらうために有効です。
相続人は、原則として、相続の開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続を承認するか、相続放棄をするかを判断しなければなりません。
もっとも、一定の事情がある場合には、家庭裁判所に申立てを行うことで、この熟慮期間を延長してもらうことができます。これを「熟慮期間の伸長」といいます。
熟慮期間が認められやすいケース
次のような事情がある場合には、3か月以内に判断することが困難として、熟慮期間の延長が検討されます。
- 相続財産の内容が複雑な場合
- 相続財産が外国など遠隔地にある場合
- 被相続人との関係が疎遠で、情報収集に時間がかかる場合
- 相続人が海外に居住している場合
申立の方法と注意点
熟慮期間の伸長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てを行います。
重要なのは、この申立てを「熟慮期間内」に行う必要がある点です。期限を過ぎてから申立てをすることはできません。
熟慮期間を延長するかどうかは、家庭裁判所が、相続人ごと・事案ごとに、すべての事情を考慮して判断します。そのため、申立てをすれば、必ず延長が認められるわけではありません。
延長される期間の目安
実務上は、3か月程度の延長が認められることが多いとされています。
事案によっては、再度の延長が認められる場合もあります。
期限が迫っている場合の対応
熟慮期間の満了が迫っている場合には、早めに弁護士へ相談することが重要です。
事情を整理したうえで適切に申立てを行うことで、判断のための時間を確保できる可能性があります。
相続の開始を知ってから3か月以内に、相続放棄や限定承認の手続きをしないまま期限が経過すると、法律上「単純承認」をしたものとみなされます。
単純承認とみなされた場合には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含めて、すべてを相続することになります。
いったん単純承認とみなされると、原則として、後から相続放棄をすることはできません。
「何もしていないだけだから大丈夫」「まだ手続きをしていないだけ」と思っているうちに期限が過ぎると、意図せず借金まで相続してしまうおそれがあります。
もっとも、借金の存在を後から初めて知った場合など、特別な事情があるときには、期限経過後であっても、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、このような場合には、裁判所に対して事情を具体的に説明する必要がありますので、早めに専門家へ相談することが重要です。
相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
多くの場合、この起算点は被相続人が亡くなったことを知った時ですが、必ずしも「死亡日」から一律に数えるわけではありません。
3か月を過ぎてから負債が判明した場合
被相続人には財産も借金もないと思っていたため、相続放棄の手続きをしないまま過ごしていたところ、死亡から長期間が経過した後になって、金融機関や役所から突然請求書や通知が届き、多額の借金や滞納税金があることを初めて知る、というケースは少なくありません。
このような場合でも、必ずしも「手遅れ」となるわけではありません。
最高裁が示した考え方(重要)
最高裁判所は、相続人が被相続人について「財産も債務も全く存在しないと信じており、そのように信じることに相当な理由がある場合」には、例外的に、相続放棄の3か月の期間は、相続人が相続財産や債務の存在を知った時、または通常これを知り得た時から起算するのが相当である、と判断しています。
つまり、被相続人の死亡から3か月以上経過していても、一定の場合には、相続放棄が認められる余地があります。
実務上のポイント
もっとも、形式的には死亡から3か月を過ぎているため、相続放棄が受理されるかどうかは、
- 「いつ、何をきっかけに相続人になったと知ったのか」
- 「なぜそれまで知らなかったのか」
といった点を、家庭裁判所にどのように説明できるかに大きく左右されます。
この事情説明の内容は、依頼する専門家の知識・経験によって結果に大きな差が出る分野です。
自分で手続きをする際の注意点
死亡から3か月経過後の相続放棄については、一度、家庭裁判所に却下されてしまうと、同じ内容でやり直すことはできません。
「とりあえず自分でやってみて、ダメだったら専門家に依頼する」という方法は取れない点に注意が必要です。
当事務所で多い相談例
当事務所がご相談を受けるケースの多くは、被相続人の死亡から3か月以上、場合によっては数年経過した後に、
- 税金の滞納に関する通知
- 空き家の相続人であるとの連絡
- 賃借人の孤独死に関する文書
などが突然届き、初めて自分が相続人であったことを知った、というものです。
このような場合でも、事情を整理し、裁判所に適切な説明を行うことで、相続放棄が受理されるケースは少なくありません。
あきらめる前に、一度専門家へ相談されることをおすすめします。
相続放棄は、相続人全員で行わなければならないものではありません。
遺産分割協議とは異なり、相続放棄は、相続人それぞれが自分の判断で個別に行うことができます。
例えば、相続人が長男・次男・長女の3人である場合に、
- 長男と長女は相続放棄をしたい
- 次男は相続したい
という場合でも、長男と長女は相続放棄をすることが可能です。
この場合、次男は単独で相続人となり、相続手続きを進めることになります。
相続手続はどう進めるのか
他の相続人が相続放棄をした場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
相続した相続人は、相続放棄をした人の「相続放棄受理証明書」を用いて、不動産の相続登記や預貯金の手続きを行います。
注意点
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、相続放棄をした人の相続分は消滅し、残った相続人の相続分が増えることになります。
他の相続人が相続放棄をしているかどうか分からない場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に照会することで、相続放棄の有無を確認することができます。
家庭裁判所に照会すると、分かること
家庭裁判所に照会を行うと、相続放棄の申述がされている場合には、事件番号や受理年月日などが回答されます。
一方、相続放棄の申述がされていない場合には、「該当する申述は見当たらない」といった形で回答されます。
照会ができる人(限定されています)
相続放棄の有無を照会できるのは、次のいずれかに該当する方に限られます。
- 相続人
- 被相続人に対する利害関係人(債権者など)
照会が問題となりやすい典型例
特に多いのは、兄弟姉妹などの後順位相続人が、「被相続人の子や孫など、先順位の相続人が相続放棄をしたかどうか」を確認したいケースです。
この場合、先順位相続人が相続放棄をしなければ、後順位相続人は相続人となりません。
照会先と費用
照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
照会手数料はかからず、無料で行うことができます。
照会に必要な書類は?
照会に必要な書類は、裁判所によって多少異なることがありますが、一般的には次のようなものが求められます。
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人および照会者の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(照会者と被相続人との関係が分かるもの)
- 照会者の住民票(本籍地の記載があるもの)
- 相続関係図
- 手続代理委任状(弁護士に依頼する場合)
必要書類の詳細は、事前に家庭裁判所へ確認することをおすすめします。
被相続人の子が相続放棄をした場合でも、その子の子ども(被相続人の孫)が、借金などを代襲相続することはありません。
相続放棄をした人は、法律上「最初から相続人ではなかったもの」と扱われます。
そのため、相続放棄をした子がいる場合には、代襲相続そのものが発生せず、孫が相続人となることもありません。
孫が相続放棄をする必要はある?
被相続人の子が相続放棄をしている場合には、孫は相続人ではありませんので、孫が相続放棄の手続きをする必要はありません。
相続人は誰に移るのか
被相続人の子が相続放棄をした場合には、たとえ孫が存在していても、相続人の地位は次の順位へ移っていきます。
「相続放棄をすると、代わりに子どもが借金を負うのでは?」と心配される方もいますが、相続放棄によって、借金が自動的に孫へ移ることはありません。
①遺品・書類を確認する
まずは、被相続人の遺品の中に、借金や債務に関係する書類がないかを確認します。
- 契約書、請求書、督促状
- クレジットカード
- 消費者金融会社のカード
- 支払いに関するメモ
これらが見つかれば、借入先や債務の概要を把握する手がかりになります。
②預金通帳・口座の動きを確認する(重要)
被相続人の預金通帳や口座の入出金履歴の確認は必須です。
定期的な引き落としや振替えがある場合には、ローン、クレジット、家賃、保証料などの支払いが行われていた可能性があります。
預金残高が不足すると、金融機関や債権者から請求書や督促状が届くことがあります。
郵便物はこまめに確認し、見落とさないよう注意しましょう。
③死亡後の引き落とし・振替えに関する注意点
被相続人の死亡後に、自動的に口座から引き落としや振替えが行われていたとしても、それだけで直ちに単純承認にあたるわけではありません。
ただし、引き落としが行われていることを認識した後も、特に対応せず漫然と振替えを継続していると、単純承認と評価されるおそれがあります。
気づいた段階で、対応方法を検討することが重要です。
④信用情報機関を利用した調査
被相続人が、銀行、クレジット会社、消費者金融などから借入れをしていたかどうかについては、信用情報機関に対して情報開示を求める方法もあります。
所定の書類を提出すれば、借入れの有無などについての回答を得ることができます。
⑤弁護士に依頼するという選択肢
信用情報の開示手続や、債務調査をご自身で行うのが難しい場合には、弁護士が代理人として調査を行うことも可能です。
また、どこまで調査を進めるべきか、相続放棄との関係で注意すべき点についても、具体的な助言を受けることができます。
当事務所でも、借金・債務調査を含めたご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。
住宅ローンについては、団体信用生命保険(団信)に加入している場合、住宅ローンの返済中に債務者が死亡すると、所定の手続きを行うことで、保険金により住宅ローンは完済されます。
そのため、団信が適用される住宅ローンについては、原則として、相続人が返済を引き継ぐ必要はありません。
他に借金がない場合には、必ずしも相続放棄をする必要がないケースもあります。
団信の仕組みと手続き
団体信用生命保険では、住宅ローンを貸し付けている金融機関が、保険契約者および保険金受取人となり、住宅ローンの債務者が被保険者となるのが通常です。
相続人が金融機関に対し、住宅ローン債務者が死亡した事実を連絡し、必要書類を提出すると、保険金は相続人を経由せず、金融機関に直接支払われます。
この団信の手続きを行うこと自体は、単純承認にはあたりません。
相続放棄をする場合の注意点(重要)
相続放棄をすると、団信によって住宅ローンが完済されたとしても、その住宅を相続することはできなくなります。
つまり、「住宅ローンは団信で消えるが、家そのものも相続できなくなる」という点には注意が必要です。
相続放棄以外の選択肢が考えられる場合
住宅ローン以外にも債務がある場合には、相続放棄をする前に、別の選択肢を検討すべきケースがあります。例えば、団信によって住宅ローンが完済された住宅を相続し、その住宅を売却した上で、売却代金を他の借金の返済に充てる、といった方法が考えられます。
どの方針が最も適切かは、借金の総額や財産の内容、今後の生活設計によって大きく異なります。判断前に専門家へ相談することが重要です。
相続放棄をしても、法律上の要件を満たしていれば、未支給年金を受け取ることは可能です。
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった時点で、本来支給されるはずであったものの、まだ支給されていなかった年金のことをいいます。
未支給年金を受給できるのは、次のいずれかに該当し、かつ、死亡当時に被相続人と生計を同一にしていた方です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
未支給年金は、相続によって受け取る「遺産」ではありません。
法律により、一定の遺族に対して固有の権利として支給されるものとされています。
そのため、相続放棄をしても、未支給年金の受給権が失われることはありません。
この点については、未支給年金は相続の対象とはならないとする最高裁判例(最高裁平成7年11月7日判決)でも、明確に示されています。
つまり、未支給年金の請求権は、相続とは別の制度として遺族に認められているため、相続放棄の影響を受けない、ということです。
相続放棄をした場合に生命保険金を受け取れるかどうかは、生命保険契約や約款で、「誰が保険金の受取人とされているか」によって異なります。
相続放棄をしても受け取れるケースと、受け取れないケースがありますので、受取人の指定内容を正確に確認することが重要です。
受取人が特定の相続人と指定されている場合
生命保険契約で、
「配偶者〇〇」「子〇〇」など、特定の人物が受取人として指定されている場合、その保険金請求権は、指定された受取人固有(「受取人の自分の」という意味です)の権利となります。
この場合、保険金は相続によって取得するものではないため、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。
受取人が「相続人」と指定されている場合
生命保険契約や約款で、保険金の受取人が「相続人」と定められている場合でも、生命保険金は、各相続人に固有の権利として支払われるものと考えられています。
そのため、この場合も、相続放棄とは関係なく、生命保険金を受け取ることが可能です。
受取人が「被相続人」とされている場合(注意)
生命保険契約や約款で、保険金の受取人が「被相続人」と指定されている場合には、保険金請求権は、被相続人の財産として相続の対象となります。
この場合、相続放棄をすると、被相続人の保険金請求権も放棄することになりますので、生命保険金を受け取ることはできません。
まとめ(重要ポイント)
- 生命保険金を受け取れるかは「受取人の指定」によって決まる
- 受取人が特定の人物、または「相続人」の場合は受取可能
- 受取人が「被相続人」の場合は、相続放棄をすると受取不可
- 判断の前に、保険契約・約款の確認が重要
よくある注意点
生命保険の受取人の指定内容は、契約書や約款を見ないと分からないことも多く、誤解したまま相続放棄をしてしまうと、本来受け取れるはずだった保険金を失うおそれがあります。
相続放棄を検討する前に、生命保険の内容についても含めて、専門家に相談することをおすすめします。
被相続人が病院で亡くなった場合、死亡後に、相続人宛てに入院費や医療費の請求書が届くことは珍しくありません。
相続放棄を検討している最中に請求書が届くと、「支払ってしまっても大丈夫なのか」「支払うと相続放棄ができなくなるのではないか」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
実際には、入院費の支払いが直ちに相続放棄を妨げるとは限りません。支払ったお金の出どころや、支払いの趣旨・金額などによって、相続放棄が可能かどうかの判断が分かれます。
注意が必要なポイント
- 誰のお金で支払ったのか
- 支払った時期はいつか
- 支払いの内容・金額が相当なものか
など、個別の事情が重要になります。
判断を誤ると、単純承認と評価されてしまうおそれもあるため、注意が必要です。
詳しい解説について
故人の入院費を支払った場合に、相続放棄ができるかどうかについては、よく寄せられるご相談の一つです。
具体的な考え方や判断のポイントについては、「よくあるご相談(故人の入院費を支払っても相続放棄は可能?」にまとめましたのでご確認ください。
先日父が病院で亡くなりました。3か月ほど入院し、入院費と治療費などの支払が残っており、先日請求書が届きました。
父は多額の連帯保証をしていたため、相続放棄をすることを考えているのですが、入院費を支払ってしまっても大丈夫でしょうか。
相続放棄を考えているなら、支払いを行わない方が無難です。
債務の弁済については、こちらの「既に支払ってしまった場合の相続放棄」にご説明しておりますとおり、単純承認とされてしまうリスクがあります。
「故人の生前の入院費だから故人の預貯金から支出しても大丈夫」と思いがちですが、入院費も他の負債と同様に被相続人の負債にすぎません。
しかし、生前、故人が医師や看護師さんにお世話になった病院に、入院費を支払わないというのは道義的にしのびないというお考えの方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、故人の財産からではなく、ご自身の財産から支払うようにしましょう。
既に入院費を支払ってしまったという場合でも、その額や諸般の事情で相続放棄が認められるケースもございますので、一度ご相談にお越し頂ければ、ケースごとの助言をさせて頂けます。
相続放棄をすると、原則として、被相続人の未払い税金(滞納税金を含む)を支払う義務も引き継ぎません。自己破産では税金などの公租公課は原則として免責されませんが、相続放棄の場合は、そもそも相続人ではなかった扱いになるため、被相続人の税金を支払う義務自体が生じないのが原則です。
また、相続放棄をした方は相続人ではないため、原則として、被相続人の準確定申告(4か月以内)を行う立場にもありません。
※ただし、相続放棄の前後に「申告・還付金の受領・納税」等をすると、手続上のリスクが問題になることがあるため、迷う場合は事前に専門家へ相談してください。
固定資産税が「届いてしまう」ことがある理由(台帳課税)
ただし、固定資産税については注意が必要です。固定資産税は、原則として毎年1月1日(賦課期日)時点で固定資産課税台帳に登録されている「所有者」等に課税されます(いわゆる台帳課税)。
そのため、相続放棄をしていても、タイミングによって納税通知書が届くことがあります。
重要:年をまたぐと「固定資産税の通知」が来やすい
たとえば、被相続人が前年中に亡くなり、相続放棄の手続をしていても、家庭裁判所の受理が翌年1月1日以降になると、1月1日時点では手続が完了していないため、台帳上「相続人(現所有者)」として扱われ、納税通知が届くことがあります。
納税通知が来たらどうする?
相続放棄をしたにもかかわらず固定資産税の通知が来た場合は、自己判断で支払う前に、まず市区町村へ連絡し、相続放棄受理通知書・受理証明書などの提出方法や取扱いを確認しましょう。
自治体側の登録・事務処理の関係で「通知が来る」こと自体は起こり得ますが、相続放棄の事実を示して取扱いを整理できるケースがあります。
年末に相続放棄を行う場合の実務的な対策
被相続人に不動産があり、相続放棄を予定していて、手続が年をまたぎそうな場合は要注意です。
この場合は、できるだけ早く相続放棄の手続を行い、必要に応じ「固定資産税が問題となる可能性」を踏まえた裁判所への説明(上申の工夫等)を行うなど、早期の受理を目指す対応が重要になります。
放棄後に多額の財産が見つかった場合
いったん家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として、取消しや撤回をすることはできません。
相続放棄の取消しや撤回を認めてしまうと、他の相続人や債権者の立場が不安定になってしまうため、法律上、強く制限されているからです。
例外的に取消しが認められる場合
もっとも、相続放棄が詐欺や強迫によって行われた場合など、極めて例外的な事情があるときには、取消しが認められる可能性があります。
この場合には、相続放棄の申述を行った家庭裁判所に対して、「相続放棄取消しの申述」を行うことになります。
ただし、単に「後から財産が見つかった」「預金が思ったより多かった」という理由だけでは、取消しや撤回は認められません。
放棄後に見つかった預金は使ってもいい?
相続放棄をした後に、被相続人名義の預金が見つかったとしても、その預金を使ってはいけません。
相続放棄後に相続財産を使用すると、相続放棄をしていないのと同じ「単純承認」と評価され、相続放棄の効果が失われてしまうおそれがあります。
見つかった財産の正しい扱い
相続放棄後に見つかった預金や財産は、次順位の相続人がいる場合には、その相続人に引き継ぐことになります。
全ての相続人が相続放棄している場合には、相続財産清算人を選任し、その管理・処分に委ねることになります。
自己判断で処分せず、必ず適切な手続に従って対応しましょう。
相続放棄は、家庭裁判所に受理されたからといって、その効力が無条件に確定するわけではありません。
相続放棄の申述をする前や、相続放棄が受理された後であっても、被相続人の財産を処分したり、使ってしまった場合には、法律上「単純承認」をしたものと評価され、相続放棄が無効になる可能性があります。
相続放棄が無効とされる典型例
たとえば、次のような行為があった場合には、相続放棄が無効と判断されるおそれがあります。
- 被相続人の預貯金を引き出して使った
- 相続財産を売却・換金した
- 被相続人名義の不動産を自分名義に変更した
- 相続財産を自己のために処分・費消した
これらは「単純承認行為」に当たる可能性が高く、相続放棄の効果を失わせる原因になります。
無効は誰が主張するのか
相続放棄が無効であることは、特に被相続人の債権者から問題にされることがあります。
債権者が、相続放棄をした者に単純承認行為があったことを知った場合、「相続放棄は無効である」と主張して、裁判を起こしてくる可能性があります。
重要な注意点
相続放棄が受理された後であっても、被相続人の財産に一切手を付けてはいけません。「もう相続放棄は終わったから大丈夫だろう」という判断は非常に危険です。
相続放棄を検討している段階から、受理後に至るまで、相続財産については現状を維持し、安易に処分・名義変更などを行わないよう十分に注意しましょう。
相続放棄が家庭裁判所に受理されることと、相続放棄が最終的に「有効かどうか」は、法律上、必ずしも同一ではありません。
そのため、相続放棄が受理された後であっても、債権者が、貸金返還請求訴訟などを提起し、その中で、「相続放棄は無効である」と主張してくる場合があります。
どのような場合に問題になりやすいか
実務上、債権者が相続放棄の無効を主張するケースはほとんどありません。
しかし、次のような事情がある場合には、相続放棄の有効性が争われる可能性があります。
- 相続放棄をする前後に、単純承認と評価される行為があった場合
- 被相続人の債務の存在を認識していながら、3か月経過後に相続放棄をした場合
- 相続放棄をした者の行動から、放棄の前提となる事情説明に疑義が生じる場合
注意すべきポイント
相続放棄が受理されたからといって、常に、債権者からの請求や争いの可能性が完全に消えるわけではありません。
相続放棄により請求が出来なくなる債権者は、相続放棄をした者の行動を確認している場合もあります。
特に、相続放棄の前後の行動や、手続きに至る経緯によっては、後になって問題が生じる場合があるため、慎重な対応が必要です。
不安を感じる場合には
相続放棄を検討している段階や、相続放棄後の行動について不安がある場合には、早めに専門家に相談し、単純承認に該当する行為がなかったか、あらかじめ確認しておくことが重要です。
改正前のルール(参考)
相続放棄をしても、これまでの法律では「一切関係なくなる」というわけではなく、一定の管理義務が残る点に注意が必要でした。
改正前の民法では、相続放棄をした人であっても、次に相続人となる人が相続財産の管理を始めることができるまでの間、自己の財産と同一の注意義務をもって、相続財産を管理し続けなければならないとされていました。
そのため、相続放棄が受理されても、「もう何もしなくてよい」とは言えず、負担が残るケースがありました。
改正後のルール(令和5年4月1日施行)
令和5年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄をした後の管理義務は、次のように整理されました。
改正民法940条1項(要旨)
相続放棄をした者は、放棄の時点で相続財産を「現に占有している場合」に限り、その財産を相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負います。
何が変わったのか(重要ポイント)
改正により、相続放棄をしただけで、当然に管理義務を負うわけではなくなりました。
例えば、被相続人が住んでいた家や土地について、
- 相続放棄をした人が現に占有していない
- 管理や使用をしていない
といった場合には、相続放棄後に管理(保存)義務を負わないことになります。
この点で、相続放棄をした人の負担は、改正前と比べて大きく軽減されたといえます。
注意点
もっとも、相続放棄時点で相続財産を現に占有している場合には、引渡しまでの間、保存義務が残る点には注意が必要です。
「占有しているかどうか」の判断が難しい場合もありますので、迷う場合には専門家に確認することをおすすめします。
相続人全員が相続放棄をすると、被相続人の財産を引き継ぐ人が誰もいない状態になります。
この場合は、民法951条の「相続人のあることが明らかでないとき」に該当し、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を申し立てることが可能となります。
相続財産清算人とは
相続財産清算人は、相続人がいない相続財産について、
- 財産の管理・換価
- 債権者への配当
- 残余財産の国庫帰属
といった手続きを行うために選任される者です。
実務上の注意点(予納金)
もっとも、相続財産清算人の選任には、裁判所に対して予納金(数十万円〜100万円前後)が必要になることが多く、実務上、容易に申し立てができないケースも少なくありません。
そのため、全員が相続放棄をしていても、清算人が選任されないまま、事実上、現状維持の状態が続いているケースが多いのが実情です。
絶対に注意すべき点
管理が負担だからといって、相続財産を勝手に処分したり、売却・換金などを行ってしまうと、「単純承認」をしたものとみなされるおそれがあります。
単純承認と判断された場合には、相続放棄の効力が失われ、被相続人の借金などを相続する結果になりかねません。
全員が相続放棄をした後の対応は、財産の内容や管理状況によって異なります。
不用意に動く前に、相続財産清算人の選任を含めた選択肢について、一度専門家に相談し、取るべき対応を整理することが重要です。
相続人全員が相続放棄をした場合や、そもそも相続人がいない場合、被相続人の財産は「宙に浮いた状態」となります。
このような場合に、家庭裁判所で選任されるのが相続財産清算人です。
もっとも、清算人の選任には費用や時間がかかるため、すべてのケースで必ず選任すべきというわけではありません。
ここでは、実務上、相続財産清算人の選任を検討すべき典型的なケースを整理します。
①不動産(特に空き家)が残っている場合
被相続人名義の土地・建物が残っている場合は、相続財産清算人の選任を検討すべき代表的なケースです。
【問題になりやすい点】
- 空き家が老朽化し、倒壊・近隣被害のおそれがある
- 草木の繁茂や不法投棄など、管理責任を問われる可能性
- 市区町村から管理や対応を求められる
- 固定資産税の通知が届き続ける
相続放棄をしていても、「現に占有している」「実質的に管理している」と評価されると、思わぬ責任を負うリスクがあります。
不動産が残っている場合は、清算人を選任して、管理・処分を委ねることが有効です。
②財産の中身が不明・複雑な場合
「誰が調べてもよく分からない財産」が残っている場合も、清算人選任を検討すべきケースです。
【典型例】
- 預金口座が複数あり、残高や取引内容が不明
- 賃貸不動産・事業用資産が含まれている
- 海外資産や未整理の権利関係がある
- 相続財産と個人財産の区別が困難
このような場合、相続人(放棄者)が関与し続けること自体がリスクになります。
第三者である清算人に調査・整理を委ねるのが合理的です。
③債権者・第三者との紛争が想定される場合
次のような場合も、相続財産清算人を選任した方が安全です。
- 債権者が相続放棄の無効を主張する可能性がある
- 相続財産の帰属について争いが予想される
- 被相続人の保証債務・連帯保証が絡んでいる
清算人が関与することで、当事者間の直接対立を避け、紛争が制度的に処理されることが期待されます。
④放置するとトラブルが拡大しそうな場合
「何もしない方が危険」なケースもあります。
- 空き家が特定空家に指定されそう
- 行政・近隣からの苦情が増えている
- 相続放棄後も事実上の管理を余儀なくされている
このような場合は、費用負担は生じても、清算人選任によって将来の責任リスクを遮断する価値があります。
逆に、選任しなくてよい可能性が高いケース
一方、次のような場合は、実務上、清算人選任に至らないことも少なくありません。
- 財産がほとんど存在しない
- 不動産がなく、現金・動産も僅少
- 債権者も事実上動いていない
- 管理・責任が現実問題として生じていない
もっとも、「今は問題がない」=「将来も問題が起きない」ではありません。
判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。
これから相続放棄を行おうとしている場合、事前に債権者に連絡する義務はありません。
また、相続放棄が家庭裁判所に受理されたとしても、裁判所から債権者へ通知や公告が行われることはありません。
相続放棄の事実は、債権者には自動的に伝わりません。そのため、相続放棄が受理された後であっても、被相続人宛て、あるいは相続人宛てに、請求書や督促状が送られてくることがあります。
請求が来た場合の正しい対応
家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届いたら、そのコピーを債権者へ郵送してください。
債権者によっては、「相続放棄受理証明書」の提出を求めてくることがあります。
その場合には、家庭裁判所で受理証明書の発行を受け、そのコピーを債権者に送付すれば足ります。
この対応を行えば、債権者が相続放棄の事実を把握し、通常、それ以降の請求は止まります。
相続放棄の準備中・審理中に連絡が来た場合
相続放棄の準備中や、既に申立てをして審理中の段階で債権者から連絡が来た場合には、
- 「現在、相続放棄の手続きを進めている(または検討している)」
- 「受理されたら、書類を送付する予定である」
と伝えれば足ります。
相続放棄を行う旨を伝えると、債権者の担当者からは「受理されたら受理証明書のコピーを送ってください」と言われるのが通常です。
債権者は相続放棄を止めることはできません
相続放棄をするかどうかは、あくまで相続人自身の意思によるものです。
債権者が、相続人に対して「相続放棄をしないよう強制する」ことはできません。
注意:やってはいけない対応
ごく稀に、相続放棄をする前に、債権者が「相続財産から支払ってほしい」と求めてくることがあります。
しかし、相続財産からの支払いをしてしまうと、「単純承認」と判断され、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
請求が来ても、安易に支払わず、必ず対応を確認してください。
相続放棄が家庭裁判所に受理されたにもかかわらず、その後も債権者から請求書や電話、督促が続くことがあります。
しかし、多くの場合、正しい対応を取れば請求は止まります。
ここでは、相続放棄後も連絡が止まらない場合の原因と、具体的な対処法を解説します。
なぜ、相続放棄をしても連絡がくるのか
①債権者が相続放棄の事実を知らない
相続放棄は家庭裁判所で行う手続ですが、裁判所から債権者へ通知が行われることはありません。
そのため、債権者は、
- 相続放棄がされたこと
- どの相続人が放棄したのか
を把握しておらず、従来どおり請求書を送付しているだけ、というケースがほとんどです。
②受理通知書を送っていない
相続放棄が受理されても、債権者にその証拠を示さなければ、請求は止まりません。
特に、複数の債権者がいる場合、一部の債権者にしか書類を送っていないということもよくあります。
③事務処理が追い付いていない
金融機関や大手業者でも、書類が届いてから社内処理が完了するまでに時間がかかることがあります。
この場合、一時的に請求が続いているだけということもあります。
正しい対処法① 受理通知書(又は受理証明書)を送る(基本対応)
相続放棄が受理されたら、次のいずれかを債権者に送付します。
- 相続放棄受理通知書(コピー)
- 相続放棄受理証明書(コピー)
送付方法は、郵送(できれば簡易書留)が安心です。
多くのケースでは、この対応だけで請求は止まります。
正しい対処法② 電話ではなく「書面」で対応する
債権者から電話がかかってくると、つい口頭で説明してしまいがちですが、原則は書面対応が安全です。
電話対応のリスク:
- 説明した内容が正確に伝わらない
- 担当者が変わると話が引き継がれない
- 不要なやり取りが長引く
書面で、「相続放棄が受理されたため、請求には応じられない」という点を明確に伝えましょう。
正しい対処法③ それでも連絡が来る場合
受理通知書・証明書を送っても連絡が止まらない場合は、次のような事情が疑われます。
- 債権者が相続放棄の有効性に疑問を持っている
- 単純承認を疑っている
- 3か月経過後の相続放棄で争う余地があると考えている
この段階では、個人での対応を続けること自体が負担・リスクになることが多いですので、専門家に相談するようにしましょう。
相続人全員が相続放棄をした場合には、原則として、相続放棄をした人が当然にマンションの管理義務を負うわけではありません。
もっとも、相続放棄をした人のうち、被相続人名義のマンションを相続放棄時点で「現に占有している者」がいる場合には、注意が必要です。
「現に占有している」とは、例えば次のような状態をいいます。
- 被相続人名義のマンションに住み続けている
- 生活の拠点として使用している
- 鍵を管理し、事実上管理・支配している状態
このように現に占有している者は、相続人または相続財産清算人にマンションを引き継ぐまでの間、自己の財産と同一の注意をもって、マンションを保存する義務を負います。
一方、相続放棄をした人が当該マンションを使用・管理しておらず、現に占有していない場合には、相続放棄後にマンションの管理義務を負うことはありません。
この点は、令和5年4月施行の民法改正により、相続放棄をした人の負担が大きく軽減されたポイントです。
相続人全員が相続放棄をすると、自宅を相続する人が誰もいない状態となります。
この場合、自宅の状況は、住宅ローンが残っているかどうかによって対応が大きく異なります。
①住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている自宅については、債権者(金融機関)が抵当権を実行し、自宅を競売により処分することになります。
もっとも、相続人全員が相続放棄をしている場合、競売手続きを進めるために必要な「書類の受領者」や「手続の窓口となる者」が存在しません。
このため、実務上は、債権者が家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を申し立てるのが一般的です。
家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると、その清算人が、競売や任意売却などの手続きを行い、自宅の所有権は最終的に第三者へ移転します。
②住宅ローンが残っていない場合
住宅ローンのない自宅についても、相続人全員が相続放棄をすると、自宅を引き継ぐ相続人はいなくなります。
この場合、相続放棄をした相続人が当然に自宅の所有者になることはありませんが、状況によっては一定の管理義務が問題になることがあります。
特に、相続放棄時点で自宅を「現に占有」している相続人がいる場合には、相続財産清算人に引き渡すまでの間、自宅を保存する義務を負う可能性があります。
管理責任を完全に免れたい場合
住宅ローンのない自宅について、管理責任を明確に解消したい場合には、相続人自らが家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、自宅を清算人に引き継ぐ必要があります。
相続財産清算人に引き渡すことで、その後の管理・処分は清算人が行い、相続人が関与する必要はなくなります。
先日、聞いたこともない役所の建設管理課から通知書が届きました。内容は、添付されている写真の建物が老朽化しており危険な状態にあること、通行人が事故に遭う危険があることから確認して対応をお願いしたい、通知書は建物所有者の共同相続人全員に送付している、というものでした。
しかし、私は記載されていた建物所有者と面識がなく、相続関係があるかどうかも分かりません。
おそらく建物所有者の方は、相当昔に亡くなられたものと思われますが、相続放棄して対応を免れることは出来ますか?
相続放棄は可能です。但し、被相続人が死亡して相続開始してから3か月以上経過していることが通常ですので、適切な対応が必要です。
通知を放置すると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
また、建物が建っている土地の固定資産税が安くなる「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が高くなる可能性もあります。
行政が「行政代執行」を行った場合、その費用を請求される可能性もあります。
相続放棄を検討している方は早急に専門家の相談を受けましょう。
近年、老朽化した空き家が社会問題化しています。
平成27年に空き家等対策特別措置法が施行され、行政は、空き家を適切に管理していない所有者に対し、助言・指導・勧告を行うことが出来るようになりました。
今回届いた通知書は、上記経緯から送付されたものと思われます。
相続放棄をした場合、その相続については、初めから相続人とならなかったとみなされます(民939条)。
相続放棄をした者が相続財産の管理をしている場合には、速やかに他の相続人等に引き継がなければなりません。
他の相続人等に引き継ぐまでは、相続財産の管理者が不在とならないよう、自己の財産と同様の注意をもって管理を継続しなければなりません(民940条1項)。つまり管理義務を負い続けます。
相続財産の管理を引き継ぐことが出来ない、または全員が相続放棄をして相続人不存在となったような場合には、そのまま管理を継続していくか、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行い、相続財産管理人に管理を引き継ぐことを検討することになります。
相続放棄が家庭裁判所に受理されたからと言って、必ずしも空き家を放ったらかしには出来ないということに注意が必要です。
民法改正(令和5年4月施行)
従前までは上記のような説明が行われてきましたが、相続放棄をした場合の管理義務について、令和5年4月1日施行の改正民法では以下の規定に改正され、管理義務者が明確化されることになりました。
改正民法940条1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
上記の改正により、空き家を現に占有していない方が相続放棄を行った場合、管理(保存)義務を負わないこととなり、改正により負担が軽くなったといえます。
ご相談のケースでは、全く見ず知らずの方の建物の話であり、占有もしていませんので、義務を負いません。
相続放棄の手続きを行っておいた方が無難と思われます。
ただ、相続放棄を行った場合、空き家の管理義務や借金・滞納税金等のマイナスの財産を相続することは無くなりますが、プラスの財産があった場合、それも相続できなくなりますので注意が必要です。
また、ご質問のような通知書が届いたケースは、被相続人が死亡してから3か月以上経過しているため、相続放棄申述書に適切な内容の上申書を付ける必要があるほか、そもそも相続を繰り返して相続人が多数になっていることが通常で、相続人調査が困難であることが多いようです。
したがって、最初から専門家に依頼して相続人調査と上申書の作成を行ってもらうことをお勧めします。
相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。
そのため、「相続放棄をしたのだから、相続税の申告も不要」と考えてしまう方が少なくありません。
しかし、相続放棄をしていても、相続税の申告が必要になるケースがあります。
生命保険金・死亡退職金には注意が必要です。
相続放棄をしても、生命保険の受取人に指定されている場合には、その保険金を受け取ることができます。
この生命保険金は、相続により取得したものではなく、受取人固有の権利として受け取るものです。
もっとも、税務上は「みなし相続財産」として扱われるため、受け取った金額によっては相続税の申告・納税が必要になります。死亡退職金(退職手当金)についても同様です。
控除枠・2割加算に注意
生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠がありますが、相続放棄をした方は法定相続人ではありません。そのため、この非課税枠の適用を受けることはできません。
また、相続放棄をした方が受け取る生命保険金や退職手当金については、原則として相続税の「2割加算」の対象となります。
申告を怠るとどうなる?
相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
相続放棄をしたからといって、税務上の手続まで自動的に不要になるわけではありません。
相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。そのため、原則として、相続放棄をした方は被相続人の準確定申告を行う必要はありません。
準確定申告は、被相続人の所得について、「相続人」の立場で行う申告です。そのため、相続放棄をしたにもかかわらず準確定申告を行ってしまうと、相続人としての地位を前提とした行為と評価され、状況によっては単純承認とみなされるおそれがあります。
特に、準確定申告により還付金を受け取った場合には、相続財産を取得したと評価され、相続放棄が認められなくなるリスクが高くなります。
相続人全員が相続放棄をし、包括受遺者もいない場合には、相続財産管理人(相続財産清算人)が選任され、相続財産法人として準確定申告が行われます。この場合、相続放棄をした元相続人が準確定申告を行う必要はありません。
国税庁HP「民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続」
限定承認とは、相続によって引き継ぐ債務を、相続財産のプラスの範囲に限定する方法です。
相続財産を清算した結果、借金の方が多かった場合でも、不足分を自分の財産で支払う必要はありません。
一方で、借金よりもプラスの財産が多かった場合には、その差額を相続することができます。
相続財産が最終的にプラスになるかマイナスになるか分からない場合に、理論上は有効な制度といえます。
限定承認が利用できる条件
限定承認は、相続放棄をした者を除く、すべての相続人が共同して行う必要があります。
相続人のうち、一人でも単純承認をしてしまった場合には、限定承認を選択することはできません。
また、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述を行う必要があります。
限定承認が実務でほとんど利用されない理由
限定承認の手続は非常に複雑です。
- 相続財産管理人の選任
- 正確な財産目録の作成
- 官報による公告
- 債権者への個別対応や清算手続
など、多くの手続きを踏まなければなりません。
手続に時間と費用がかかるうえ、相続人全員の足並みを揃える必要があるため、実務ではほとんど利用されていないのが現状です。
当事務所の対応について
このような理由から、当事務所では、限定承認のご依頼はお受けしておりません。
相続財産に不安がある場合には、限定承認ではなく、相続放棄を中心とした対応を検討することが、結果的にリスクを抑えられるケースが多いと考えています。
相続放棄の手続は、戸籍の収集や裁判所とのやり取りなど、想像以上に手間と時間がかかります。
当事務所では、相続放棄の手続を弁護士が代理人として行い、最初から最後までお任せいただけます。
基本料金
法律相談料 無料
相続放棄手数料 55,000円(税込)
複数名の場合(割引料金)
2人目以降:1名追加ごとに +22,000円(税込)
【例】
配偶者+子2名の場合
55,000円 + 22,000円 × 2 = 99,000円(税込)
※ 相続放棄は連鎖的に必要となることが多いため、 ご負担を抑えた料金設定にしています。
追加が必要になる主なケース(必要な場合のみ)
・被相続人の死亡から3か月経過後のご依頼
→ 1名につき +33,000円(税込)
・熟慮期間伸長の申立
→ 1名につき +22,000円(税込)
・相続放棄申述の有無についての裁判所照会
→ 22,000円(税込)
・信用情報の開示請求
→ 22,000円(税込)
上記料金に含まれるサービス
- 相続放棄申述書の作成
- 戸籍関係書類の取り寄せ
- 事情に応じた「上申書」の作成
- 裁判所からの電話照会への対応
- 家庭裁判所から照会書が届いた場合の回答助言
- 相続放棄受理証明書の取得
全国どの家庭裁判所への相続放棄にも同一料金で対応しています。
実費の説明
戸籍・住民票の取得や印紙代などの実費は、ご依頼時に1名につき10,000円をお預かりし、手続終了後に精算いたします。
実際に使用する実費は、通常5,000円前後となるケースが多いです。
追加費用について
追加費用が発生することはほとんどありませんが、万一実費預り金が不足する場合には(弁護士費用が追加になることはありません)、必ず事前にご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
法律相談のお申込みはこちら
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
- 離婚の相談・サポート案内
- 不倫・不貞慰謝料請求を請求したい方
- 不倫慰謝料請求を受けた方
- 婚約破棄
- 相続放棄
- 相続・遺産分割
- 遺言作成サービス案内
- 債務整理・自己破産・個人再生・過払金請求
- 家族信託
- 成年後見制度
かがやき法律事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
最寄り駅
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
電話受付時間
定休日:土曜・日曜・祝祭日